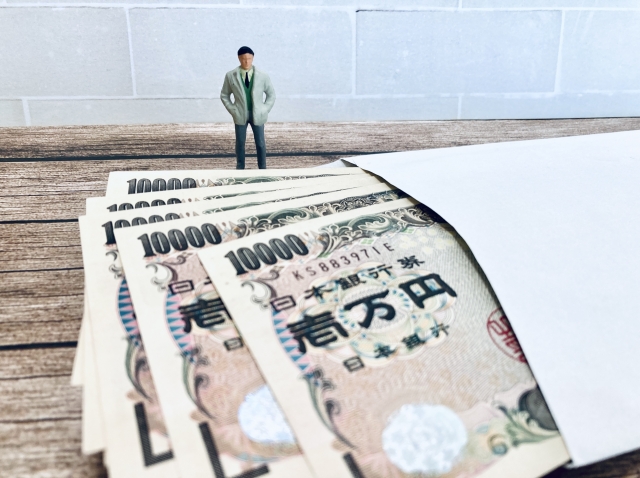物価が上昇し続けるインフレの状況下で、これまでの給与だけでは生活が苦しいと感じる場面が増えています。
将来への不安を解消するためには、現状の収入を見直し、積極的に増やす行動が不可欠です。
一方で、どのように収入を増やすべきなのかわからない人も少なくありません。
中には「行動しなければ」と思いながらも何もできていない人も多いです。
そこで、この記事では、今の会社で給与を上げる方法から、会社の給料以外に収入源を作る副業、さらには将来を見据えた転職や投資に至るまで、物価上昇に負けないための具体的な収入アップ策を網羅的に解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶会社設立の流れとは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説
▶【2025年最新版】SEO対策の基本施策と方法を解説!
▶差別化戦略とは?実際の事例やUAV/USPについても解説!

物価高なのに給料が上がらない日本の現状

現在、商品やサービスの値上げが続く一方で、給与の伸びは鈍い状況が続いています。
企業がコスト削減を優先し、売上が伸びても人件費への還元を抑制する傾向が、給与が上がらない一因です。
なぜ日本の給与は上がりにくいのか、その背景には長引くデフレ経済や企業の内部留保の推移などが関係しており、物価の上昇に賃金の改定が追いついていないのが実情です。
まずは、物価高なのに給料が上がらない日本の現状について詳しく解説します。
「実質賃金」がマイナスになりやすい状況となっている
実質賃金とは、受け取る給与の額面である名目賃金から、物価上昇(インフレ)の影響を差し引いた、実質的な購買力を示す指標です。
なぜ「給与が上がっても生活が一向に楽にならない」と感じるのか、その答えがここにあります。
例えば、給与の伸び率が1%でも、インフレ率が3%であれば、実質的な購買力は2%分減少してしまいます。
つまり、仮に名目上の給与が増えても、物価が上がり続ければ、買える商品やサービスの量が減り、実質賃金はマイナスとなるのです。
給料が上がりにくい会社や業界が残っている
給料が上がりにくい企業や業界には、いくつかの共通点が見られます。
例えば、労働集約型で付加価値を上げにくいビジネスモデルや、価格競争が激しく利益率が低い業界が代表的です。
また、大手企業からの下請けが中心で、価格決定権が弱い構造も賃金が抑制される要因です。
もし会社や業界ごとの平均年収や成長性を知りたい場合は、経済産業省などが公表するレポートを参照してみてください。
自分の所属する会社や業界がこれらの特徴に当てはまるか、それぞれ客観的に分析することも必要となります。
まずは、具体的なデータを見て、自分が置かれている状況を理解しましょう。
収入が増えないままだと起こり得る3つのリスク

収入が増えないままだと、次のようなリスクが起こり得るため、注意が必要です。
- 日々の生活水準を維持するのが困難になる
- 結婚や住宅購入など将来設計に影響が出る
- 貯蓄だけでは老後の資金が不足する可能性がある
次に、収入が増えないままだと起こりうる3つのリスクについて詳しく解説します。
日々の生活水準を維持するのが困難になる
収入が変わらないまま物価だけが上昇すると、食費や光熱費、ガソリン代といった日々の生活費の負担が増加します。
これにより、それまでと同じ生活を送っていても家計に占める支出の割合が大きくなり、自由に使えるお金が減少します。
結果として、趣味や娯楽、外食の回数を減らすなどの対応を迫られ、意図せず生活水準を切り下げなければならない状況に陥る可能性があるのです。
状況によっては、家計の収支バランスが崩れ、貯蓄を取り崩さなくてはいけない事態も想定しておくことが大切です。
結婚や住宅購入など将来設計に影響が出る
収入の停滞は、結婚や子育て、マイホームの購入といった長期的なライフプランの実現にも影響を及ぼします。
特に住宅購入を検討する際には、かなりの数の人が住宅ローンを利用しますが、収入が増えなければ返済計画にも不安が残りやすくなるわけです。
また、将来の教育費や万が一の出費に備えるための貯蓄も進めにくくなるため、人生の大きな決断を先延ばしにせざるを得ない状況や、計画そのものを見直す必要が出てくるかもしれません。
貯蓄だけでは老後の資金が不足する可能性がある
インフレが進むと、現金の価値は相対的に目減りしていきます。
例えば、現在100万円の価値があるものでも、年2%の物価上昇が続けば、10年後には同じものを買うためにより多くのお金が必要になります。
つまり、銀行に預けているだけでは、資産の購買力は少しずつ低下してしまうのです。
将来のためにコツコツと貯蓄を続けていても、インフレによってその価値が想定より低くなり、年金だけでは不足するとされる老後の生活資金を十分に確保できなくなるリスクがあるわけです。
【実践編】物価上昇に負けない収入アップの具体的な方法

次に、実践編として物価上昇に負けない収入アップの具体的な方法について見ていきましょう。
今の会社で給料を上げる方法
収入を増やすための最初のステップとして、まずは現在の職場で給与を上げる方法を検討するのが現実的です。
転職や副業に比べて環境の変化がなく、リスクを抑えながら収入アップを目指せます。
成果をアピールして昇進や昇格を交渉する
給与交渉を成功させるためには、自分の会社への貢献度や業務実績を客観的かつ具体的に示すことが大切です。
例えば、「担当プロジェクトの売上を前年比で〇%向上させた」「プロセスを改善して、月間で〇時間のコスト削減に成功した」など、具体的な数値を交えて説明することで説得しやすくなります。
評価面談などの公式な機会を活用し、事前に資料を準備したうえで、希望する役職や給与水準を論理的に伝える姿勢が求められます。
感情的にならず、あくまでビジネスとしての交渉を心がけることが大切です。
会社の制度を活用する
大半の企業では、従業員のスキルアップを支援するための制度が用意されています。
例えば、業務に関連する特定の資格を取得した場合に、毎月の給与に上乗せされる資格手当や、合格時に一時金が支給される報奨金制度などが代表的です。
また、資格取得にかかる受験費用や学習費用を会社が補助してくれる場合もあります。
まずは自社の就業規則や福利厚生の規定を確認し、どのような手当や補助があるかを把握してみてください。
これらの制度を積極的に活用しながら、自己負担を抑えつつそれぞれスキルを獲得し、直接的な収入増につなげましょう。
給料以外に収入源を作る「副業」
本業の給与だけでは物価上昇に追いつかない場合や、将来への備えを厚くしたい場合には、副業によって収入源を増やすのも効果的です。
本業以外の収入があることで経済的な余裕が生まれるだけでなく、収入が途絶えた際のリスクを分散できる他、本業とは異なる経験やスキルを得ることでキャリアを広げることにもつながります。
週末やスキマ時間で始められる副業3選
本業が忙しい人でも、週末や平日の夜といったスキマ時間を活用して始められる副業があります。
例えば、以下のようなものが一般的です。
1.企業のブログ記事やウェブコンテンツを作成する「Webライター」
2.指定されたデータを入力する「データ入力」
3.フードデリバリーサービスの配達員
以上の仕事は特別なスキルがなくても始めやすいため、自分のペースで進めるのが良いでしょう。
まずは月に5万程度の収入を目指し、自分の生活リズムに合わせて無理なく取り組めるものから試してみてはいかがでしょうか。
自分のスキルで稼げる副業
本業で培った専門的な技術や知識をはじめ、趣味で磨いてきた特技を活かして収入を得る方法もあります。
例えば、デザインが得意ならロゴ作成、プログラミングスキルがあればWebサイト制作、語学力に自信があれば翻訳といったように、自分の「得意」を商品として提供することが可能です。
最近では「ココナラ」のようなスキルシェアサービスが普及しており、個人でも手軽に自分のスキルを販売する場を見つけられます。
単に収入を得るだけでなく、自分の能力が他者の役に立つというやりがいも感じられるため、挑戦してみる価値ありです。
年収の大幅アップが可能な「転職」
現職での昇給や副業による収入増には限界がある場合、転職も効果的です。
特に、現在の会社や業界、職種の給与水準が低い場合、成長産業やより高い給与を提示してくれる企業へ移ることで、キャリアを維持しつつ収入を増やすことが期待できます。
給与水準が伸びそうなところを見つける
年収アップを目的とした転職を成功させるには、将来性があり、給与水準が伸びそうな会社や業界を見極めることが大切です。
具体的には、デジタルトランスフォーメーション(DX)の需要が拡大しているIT業界、企業の経営課題を解決するコンサルティング業界、高齢化社会を背景に成長が見込まれる医療・ヘルスケア分野などが挙げられます。
まずは、各種調査機関が発表する業界レポートを読んだり、転職エージェントから最新の市場動向に関する情報を得たりして、どの分野に自身の経験やスキルを活かせるか検討してみてください。
市場価値を得るためにスキルを習得する
転職市場で有利な条件を引き出すためには、自分の市場価値を確かなものにする努力が欠かせません。
特定の会社や業界でしか通用しないスキルだけでなく、どの職場でも求められるポータブルスキルを身につけることが大切です。
具体的には、課題解決能力や論理的思考力、プロジェクトマネジメントスキル、そして英語などの語学力が挙げられます。
また、IT分野におけるプログラミングやデータ分析のスキルも、ニーズがあると言えるでしょう。
現在の業務を通じて意識的にこれらのスキルを磨くか、必要であればそれぞれ専門のスクールなどで学ぶなど、自己投資も行ってみてはいかがでしょうか。
お金に働いてもらう「資産運用」
労働によって得る収入だけでなく、自分が持つ資産に働いてもらうことで収入を得る「資産運用」も、物価上昇に対抗するうえで有効な手段です。
銀行預金に預けているだけではインフレによって資産の実質的な価値が目減りしてしまうため、株式や投資信託といった金融商品への投資を通じて、資産そのものを増やしていく考え方が求められます。
インフレに強い資産運用の始め方
インフレ時には、現金の価値が下がる一方で商品やサービスの価格が上がるため、株式や不動産などの実物資産の価格は上昇しやすい傾向にあります。
そのため、資産運用においてはこれらのインフレに強いとされる資産を組み入れることが大切です。
投資の基本は「長期・積立・分散」であり、特定の資産に集中投資するのではなく、国内外の株式や債券など、値動きの異なる複数の資産に時間をかけて分散して投資することが欠かせません。
まずは少額から始め、経験を積みながら徐々に投資額を増やしていくのが良いでしょう。
初心者でも安心なNISA(少額投資非課税制度)の活用法
これから資産運用を始める投資初心者にとって、NISA(少額投資非課税制度)はぜひ活用したい制度です。
通常、株式や投資信託の売却益や配当金には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引で得た利益には税金がかかりません。
2024年から新しくなったNISAには、年間120万円まで積立投資に適した商品を購入できる「つみたて投資枠」と、年間240万円まで個別株などにも投資できる「成長投資枠」があります。
まずは「つみたて投資枠」を利用して、毎月コツコツと投資信託を積み立てることから始めてみてはいかがでしょうか。
収入アップと同時に進めたい固定費の見直し術

収入を増やす努力と並行して、日々の支出、特に固定費を見直すことも家計を改善するうえでとても重要です。
これらの固定費は一度見直せばその効果が継続するため、効率的な節約につながります。
具体的に見直すべきは、以下の通り。
・スマートフォンの料金プランを格安SIMに変更する
・不要なサブスクリプションサービスを解約する
・生命保険の内容を見直す
また、省エネ性能の高い家電への買い替えに際しては、自治体の補助金制度などを活用することで、初期費用を抑えつつ長期的な光熱費の支出を削減できます。
以上のように固定費を見直すだけでも、家計は若干楽になるはずです。
まとめ

物価上昇が続く現代において、将来の経済的な安定を確保するためには、現状を認識し、主体的に収入を増やすための行動を起こすことが大切です。
本記事で紹介したように、手段は一つではありません。
現職での昇給交渉、副業による収入源の複線化、成長産業への転職、そしてNISAなどを活用した資産運用など、選択肢は豊富です。
まずはすべてを一度に始めるのではなく、自分のスキルやライフステージ、リスク許容度に合わせて、実現可能なものから着手することをおすすめします。
物価上昇で先行きが不安な人もいると思いますが、備えてさえおけば最悪の事態は避けられます。