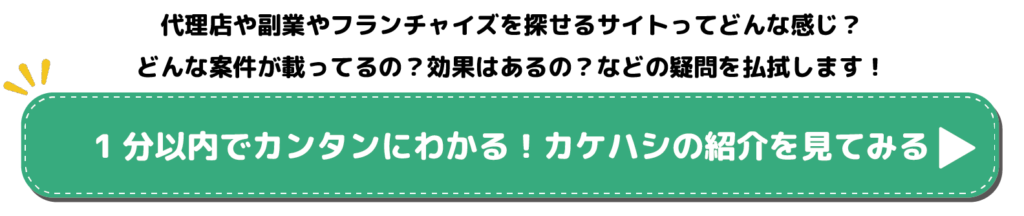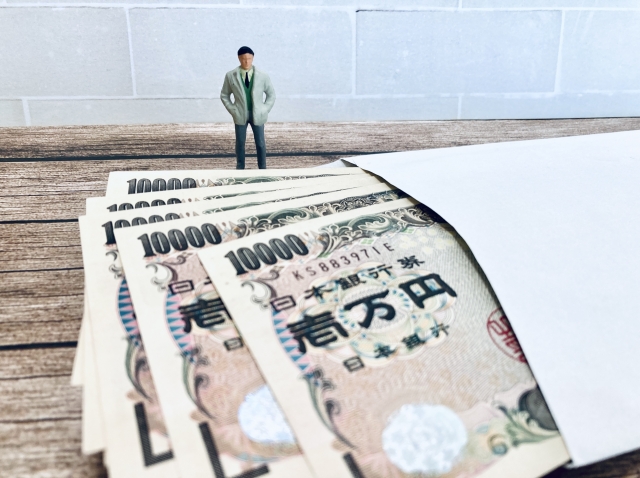リモートワークは、多様な働き方を実現する手段として多くの企業で導入が進んでいます。
しかし、導入を成功させるためには、リモートワークのメリット・デメリットを正しく理解することが重要です。
そこで、この記事では、会社がリモートワークを導入する際に得られる効果や注意すべき点を、企業視点から具体的に解説します。
自社にとって最適な働き方を見つけるための判断材料として活用いただけると幸いです。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶会社設立の流れとは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説
▶【2025年最新版】SEO対策の基本施策と方法を解説!
▶差別化戦略とは?実際の事例やUAV/USPについても解説!

INDEX
そもそもリモートワークとは?テレワークとの違いを解説

リモートワークという言葉は広く浸透しましたが、類似した言葉であるテレワークとの違いについては、いまいちわからないという方もいるはずです。
まずは、リモートワークの定義を確認し、テレワークとの意味の違いについて詳しく解説します。
リモートワークの定義:場所を選ばない柔軟な働き方
リモートワークとは、オフィスに出社せず、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、場所にとらわれずに業務を遂行する働き方を指します。
最大の特徴は、働く場所を自由に選択できる点で、通勤の負担がないのが魅力です。
従業員はライフスタイルに合わせて最適な環境で仕事に取り組めるため、生産性の向上が期待できる点がリモートワークならではの魅力といえるでしょう。
もちろん、企業にとってはオフィスという物理的な制約から解放され、より柔軟な人材活用や事業運営が可能になるという魅力も。
こうした働き方は、従業員それぞれの自律性を尊重し、成果に基づいた評価を促進するきっかけにもなるのではないでしょうか。
テレワークとの意味の違いは目的と対象範囲にある
リモートワークとテレワークはほぼ同義ですが、厳密にはニュアンスが違います。
テレワークは「tele(離れた)」と「work(働く)」を組み合わせた造語で、情報通信技術(ICT)を活用して場所や時間に捉われずに働くことを指し、政府が働き方改革の一環として推進してきた経緯があります。
一方、リモートワークはオフィスから離れて働くという点に主眼が置かれ、より自律的で自由に場所を選べる働き方として使用される言葉です。
テレワークがICT活用を前提とした「手段」としての意味合いがあるのに対し、リモートワークは「働き方」を指すのが一般的です。
なお、現在では両者を明確に区別せず使用することも珍しくありません。
在宅勤務やモバイルワークもリモートワークの一種
リモートワークは、働く場所によっていくつかの種類に分類されます。
最も代表的なのが、従業員の自宅を就業場所とする「在宅勤務」です。
通勤時間が不要になるため、育児や介護との両立がしやすいという特徴があります。
また、移動中の交通機関や顧客先、カフェなどで働く「モバイルワーク」は、営業職や外出が求められる職種にぴったりです。
本社や主要な拠点から離れた場所に設置された「サテライトオフィス」で勤務する形態も、リモートワークならではのものです。
これらの働き方は、それぞれ特徴が異なりますが、すべてオフィス以外の場所で業務を行うという点で共通しており、広義のリモートワークに含まれます。
企業がリモートワークを導入する5つのメリット

ここからは、企業がリモートワークを導入する5つのメリットについて見ていきましょう。
オフィス関連のコストを大幅に削減できる
リモートワーク導入最大のメリットは、オフィス関連の固定費を大幅に削減できる点です。
従業員の出社率が低下すれば、従来必要だった大規模なオフィススペースは不要になり、あまり賃料のかからない小規模なオフィスへの移転や一部解約が可能になります。
これにより、毎月発生する賃料や光熱費、通信費などを削減できます。
また、従業員に支給していた通勤手当も削減可能です。
オフィスに出社する人数が減ることで、デスクや椅子といった什器、コピー用紙などの消耗品にかかる費用も抑えられ、企業経営における無駄な支出を減らす効果が期待できるでしょう。
居住地を問わず優秀な人材を採用できる
リモートワークの導入は、採用活動における地理的な制約を取り払います。
従来のオフィス出社を前提とした採用では、通勤可能な範囲に居住する人材しか採用対象にできませんでした。
しかし、リモートワークを導入すれば、国内の遠隔地はもちろん、海外に住む人材も採用候補となり、採用の母集団を飛躍的に拡大させることが可能です。
それにより、特定の地域では見つけるのが難しかった専門スキルを持つ人材や、より経験豊富な優秀な人材にアプローチできる機会が格段に増加するといっても過言ではありません。
優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、採用の選択肢が広がることは企業にとってアドバンテージとなるのではないでしょうか。
従業員満足度の向上による離職率の低下
柔軟な働き方を可能にするリモートワークは、従業員満足度(ES)向上にも寄与します。
通勤という精神的・肉体的・物理的な負担から解放され、プライベートな時間を確保しやすくなるため、ワークライフバランスが改善されます。
例えば、これまで通院のために半日有給を取得していたような場面でも、業務の合間に時間調整するといった柔軟な対応が可能です。
また、育児や介護といった家庭の事情を抱える従業員にとっても、仕事と両立しやすくなるため、キャリアを諦めることなく働き続けられます。
従業員が働きやすい環境を整備することは、エンゲージメントの向上を促し、結果的に優秀な人材の離職率低下にもつながるでしょう。
災害やパンデミック発生時の事業継続性を確保できる
リモートワーク体制の構築は、BCPの観点からも重要です。
コロナ禍において、かなりの企業が出社制限を余儀なくされましたが、リモートワークを導入していた企業は比較的スムーズに事業を継続できました。
台風や地震といった自然災害、あるいはコロナのようなパンデミックが発生し、交通機関が麻痺したり外出が制限されたりした場合でも、従業員が自宅などで業務を遂行できる環境があれば、事業の停滞を最小限に抑えられます。
オフィスに機能が集中している状態は、非常時における事業停止のリスクをはらんでいますが、働く場所を分散させることで、不測の事態に対する企業の対応力をある程度担保できるのではないでしょうか。
先進的な働き方を推進する企業としてイメージが向上する
リモートワーク制度を導入し、多様で柔軟な働き方を推進していることは、企業の社会的評価やブランドイメージの向上につながります。
従業員のワークライフバランスを尊重し、時代の変化に対応する先進的な企業であるという印象を社内外に与えることが可能です。
実際に、求職者を対象とした調査で、企業選びの際にリモートワークの可否を重要な条件として挙げる人が増加しています。
このような魅力的な労働環境を提供することは、採用活動において他社との差別化要因となり、優秀な人材を引きつける強力なアピールポイントになるはず。
企業イメージの向上は、採用力強化だけでなく、それぞれの顧客や取引先からの信頼獲得にも良い影響を与えるのです。
従業員がリモートワークで得られる4つのメリット

リモートワークは、従業員にとってもメリットが豊富です。
次に、従業員がリモートワークで得られる4つのメリットについてまとめます。
通勤時間がなくなりプライベートな時間が増える
リモートワークにおける最大のメリットとして、通勤時間の削減が挙げられます。
往復で1時間以上かかっていた移動時間がゼロになることで、浮いた時間を自己啓発や趣味、家族との団らん、あるいは十分な睡眠の確保など、プライベートの充実に充てることが可能です。
これにより、日々の生活にゆとりが生まれます。
また、朝のラッシュ時の満員電車に乗る必要がなくなるため、通勤に伴う精神的・肉体的・物理的なストレスからも解放されるはずです。
削減された時間を有効活用することで、心身ともに健康的な生活を送りやすくなり、仕事への集中力やモチベーションの維持にも良い影響が期待できるでしょう。
育児や介護といったライフイベントと仕事を両立しやすい
リモートワークは、育児や介護など家庭の事情を抱える従業員が仕事とプライベートを両立させるうえで大きな助けとなることも……。
通勤時間がなくなるため、子供の保育園への送り迎えや家族の通院の付き添いといった日々の小さな用事に対応しやすくなるわけです。
また、自宅で仕事をしているため、子供の急な発熱や家族に何かあった場合でもすぐに駆けつけられるという安心感があります。
それまではライフイベントを機に離職や働き方の変更を余儀なくされるケースもありましたが、リモートワークという選択肢があることでキャリアを継続しながら家庭生活とのバランスを取ることが可能となるのではないでしょうか。
仕事と私生活の調和(ワークライフバランス)を実現できる
リモートワークは、従業員が仕事と私生活の調和、ワークライフバランスを実現するための有効な手段です。
通勤時間がなくなり、働く場所やある程度の時間的裁量を自分でコントロールできるため、生活全体の質が向上します。
例えば、業務の合間に家事を済ませたり、平日の昼間に役所での手続きを済ませたりと、時間を柔軟に使えるようになります。
近年では5Gなどの高速通信網が整備され、快適に仕事ができる環境が整いつつあり、技術的な背景も後押しとなって「仕事のために私生活を犠牲にするのではなく双方を充実させる」という働き方が可能です。
自分のペースで集中できる作業環境を構築できる
オフィス環境では、周囲の会話や電話の音など、意図せず集中を妨げられることがあるものの、リモートワークでは、自宅の書斎など、自分が最も集中できる環境を自由に構築することが可能です。
静かな空間で作業に没頭したいときや、逆に音楽を聴きながらリラックスして取り組みたいときなど、気分や業務内容に合わせて環境を調整できます。
また、自分に合った椅子やデスク、モニターなどを導入し、負担がかかりにくい最適な作業スペースを作ることも難しくありません。
リモートワーク導入前に知っておきたい企業側のデメリット

ここでは、リモートワーク導入前に知っておきたい企業側のデメリットについて見ていきましょう。
セキュリティリスクの増大と情報漏洩の懸念
リモートワークでは、従業員が社外の様々なネットワーク環境から社内システムにアクセスするため、セキュリティリスクが増大します。
オフィス内のように統一された管理が難しく、カフェなどの公共Wi-Fiを利用した場合、通信内容を盗聴される危険性がないとはいい切れません。
また、個人所有のPCで業務を行う場合、マルウェア感染のリスクや、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性も考えられるかもしれません。
業務用PCやデータを保存したUSBメモリを社外に持ち出すことによる、紛失や盗難のリスクもあるでしょう。
これらのインシデントは、機密情報や個人情報の漏洩といった重大な事態につながる懸念があり、企業はそれぞれ厳重な対策を講じることが必要です。
従業員の労働時間や勤怠状況の把握が難しい
従業員がオフィスにいないリモートワーク環境では、それぞれの労働時間を正確に把握することが難しくなります。
始業・終業時刻や休憩時間を自己申告に委ねると、実態との乖離が生まれやすくなります。
例えば、プライベートとの境界が曖昧になり、結果的に長時間労働に陥ってしまうケースや、逆に業務時間中に私的な用事を済ませるなど、勤務態度が不明確になる可能性が指摘されているのです。
管理者の目が届かないため、いわゆる「隠れ残業」が発生しやすく、従業員の健康管理の観点からも問題です。
労働基準法を遵守し、適正な労働時間を管理するためには、客観的に勤怠状況を記録できるツールの導入など、新たな仕組みの構築が求められるのではないでしょうか。
社員間のコミュニケーションが希薄化しやすい
リモートワークでは、オフィスで日常的に行われていた対面でのコミュニケーション機会が大幅に減少します。
業務上必要な連絡はチャットやメールで可能ですが、廊下での立ち話やランチタイムの雑談といった偶発的でインフォーマルなやり取りが生まれにくくなります。
こうした何気ない会話から、新しいアイデアが生まれたり、他部署の情報を得たり、人間関係が円滑になったりする効果があるため、コミュニケーションの減少はリスキーです。
コミュニケーションが業務連絡のみに限定されると、チームとしての一体感が薄れ、従業員が孤独感や疎外感を抱きやすくなる可能性も拭えません。
また、新入社員が企業文化に馴染んだり、業務上の疑問を相談したりする機会が減ることも課題です。
業務の進捗状況が見えにくくなる
リモートワーク環境下では、部下がどのような業務にどれくらいの時間をかけて取り組んでいるのか、管理者が直接確認することができません。
そのため、各メンバーの業務の進捗状況が見えにくくなり、プロジェクト全体の管理が難しくなることがあります。
誰がどのタスクを担当し、どこまで進んでいるのかが不透明になると、業務の重複や抜け漏れが発生しやすくなる他、部下が一人で問題を抱え込んでいても、管理者がサインに気づきにくく、発見が遅れてしまうリスクもあるわけです。
結果として、プロジェクトの遅延や生産性の低下につながる可能性があるため、進捗を可視化するための仕組み作りが欠かせません。
リモートワークのデメリットを克服し成功に導くポイント

次に、リモートワークのデメリットを克服し成功に導くポイントについて見ていきましょう。
堅牢なセキュリティポリシーの策定とツールの導入
情報漏洩などのセキュリティリスクに対応するためには、まず明確なセキュリティポリシーを策定し、全従業員に周知徹底することが必須です。
ポリシーには、使用を許可するデバイスの範囲、公共Wi-Fiの利用ルール、パスワードの定期的な変更、機密情報の取り扱い方法などを具体的に定めます。
ここでは単にルールを定めるだけでなく、それを遵守させるための技術的な対策も欠かせません。
安全な通信経路を確保するVPN(仮想プライベートネットワーク)の導入や、業務用デバイスを一元管理するMDM(モバイルデバイス管理)ツール、最新のウイルス対策ソフトの導入などが有効です。
定期的なセキュリティ研修を実施し、従業員の意識を高める取り組みも重要となります。
円滑な意思疎通を促すコミュニケーションツールの活用
コミュニケーションの希薄化を防ぐためには、各種ツールを積極的に活用し、意図的にコミュニケーションの機会を創出することが効果的です。
ビジネスチャットツールを導入し、業務連絡だけでなく、雑談や情報共有のための専門チャンネルを作成することで、インフォーマルな会話が生まれやすくなります。
また、Web会議システムを活用して定期的なチームミーティングや1on1ミーティングを実施し、業務の進捗確認だけでなく、メンバーのコンディションを把握する場を設けることも重要といえるでしょう。
ツールの導入と合わせて、朝会や夕会で顔を合わせる時間を設けたり、オンラインでのランチ会や懇親会を企画したりするなど、チームの一体感を醸成するための工夫があれば、従業員もより安心して働けるのではないでしょうか。
リモートワークに対応した勤怠管理方法と評価制度の構築
従業員の労働時間を適正に管理し、公平な人事評価を行うためには、リモートワークという働き方に合わせた制度の再構築も必要となるでしょう。
勤怠管理については、自己申告だけでなく、PCのログオン・ログオフ時刻を自動で記録する勤怠管理システムを導入することで、客観的な労働時間データを把握できます。
また、評価制度についてはオフィス勤務のように仕事への取り組み姿勢やプロセスが見えにくくなるため、労働時間ではなく成果に基づいて評価する仕組みへの移行が必要です。
また、目標管理制度などを活用し、評価基準を具体的かつ明確に従業員へ示すことで、納得感のある評価を実現することも忘れてはなりません。
結果的に、従業員のモチベーション維持と生産性向上につながるのではないでしょうか。
ノマドワーカーとしての働き方

最後に、ノマドワーカーとしての働き方について見ていきましょう。
会社にとらわれない働き方を見つける
ノマドワーカーは、特定の会社に縛られず、自身のスキルや専門性を活かして複数のプロジェクトに参画するのが一般的です。
仕事を見つける方法としては、以下のような方法があります。
- フリーランス向けのマッチングサイトやクラウドソーシングサービスに登録する
- SNSを通じて自身の活動を発信し依頼を受ける
- 過去の実績や人脈から紹介を得る
企業側としては、こうしたプラットフォームを活用することで、正社員採用にこだわらず、プロジェクト単位で必要なスキルを持つ専門人材を外部から調達するという選択肢を持つことができます。
それにより、事業の変動に合わせた柔軟な人員配置が可能です。
ノマドワーカーとなる方は、以上のような柔軟な働き方を目指してみてください。
安定した収入基盤を見つける
会社員と異なり、ノマドワーカーは毎月の収入が保証されていないため、安定した収入基盤を築けるかどうかが課題です。
単発の仕事だけでなく、長期的に継続して依頼される案件を獲得したり、複数のクライアントと契約したりすることで、収入源を分散させる工夫が必要不可欠。
自分のスキルを常にアップデートし、市場価値を獲得し続ける努力も欠かせません。
企業から見れば、信頼できるフリーランサーと良好な関係を築くことは、必要なときに質の良い業務を依頼できる安定した外部リソースの確保につながり、双方にとって理想的な関係となります。
まとめ

リモートワークの導入は、コスト削減や優秀な人材の確保といった企業側のメリットに加え、従業員のワークライフバランス向上にも寄与します。
一方で、セキュリティやコミュニケーション、勤怠管理などのデメリットも存在するため、事前の対策が不可欠です。
成功の鍵は、自社の状況に合わせてセキュリティポリシーやコミュニケーションのルールを定め、適切なツールや制度を導入すること。
メリットとデメリットを正しく理解し、計画的に準備を進めることで、リモートワークは企業と従業員の双方にとって有益な働き方となるでしょう。
まずは、試験的にリモートワークを取り入れてみてはいかがでしょうか。