個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合、事業収入とアルバイト収入の両方を合算して確定申告が必要です。
個人事業主のアルバイトでは、事業所得と給与所得という異なる所得区分を正しく理解し、申告手続きを進めなければなりません。
一方、どのように手続きすればいいのかわからない人もいるかもしれません。
そこで、この記事では、個人事業主とアルバイトを両立している方向けに、確定申告の必要性から具体的な手順、税金や経費に関する注意点まで詳しく解説します。

INDEX
個人事業主のアルバイトでも確定申告は必要?

個人事業主がアルバイトを始めた場合、事業収入に加えてアルバイト収入も得ることになり、複数の所得がある場合は合算して確定申告を行うことが必要です。
確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってきたり、事業の赤字と給与所得を相殺できたりと、その恩恵は計り知れません。
ここからは、個人事業主のアルバイトでも確定申告は必要なのか詳しく解説します。
原則として事業収入とアルバイト収入は合算して申告する
個人事業主としての事業収入と、アルバイト先から受け取る給与収入は、所得の種類が変わります。
事業収入は「事業所得」、給与収入は「給与所得」として扱われるのが一般的です。
確定申告では、これらの異なる種類の所得をすべて合算して年間の総所得を計算し、それに基づいて所得税額を算出します。
アルバイトを副業として行っている場合でも、この原則は変わりません。
複数の収入源がある場合、それぞれの所得を正確に把握し、一つの申告書にまとめて税務署へ提出することが義務付けられているのです。
上記の合算申告を怠ると、追徴課税などのペナルティを受ける可能性があるため、ご注意ください。
確定申告によって払いすぎた所得税が還付される場合がある
アルバイト先では多くの場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収(天引き)されています。
この源泉徴収額は、少なくとも年間の総所得に対して正確に計算された税額ではなく、あくまで概算の金額です。
そのため、確定申告で事業所得と給与所得を合算し、各種控除を適用して年間の正しい所得税額を計算すると、源泉徴収された税金の額が本来納めるべき税額を上回っていることがあります。
上記の場合、確定申告を行うことで、払いすぎていた所得税が還付金として戻ってくるので、むしろ確定申告をやっておいた方がお得です。
特に、事業所得が限られていたり、医療費控除や生命保険料控除などの適用を受けたりする方は、還付を受けるようにしましょう。
事業の赤字とアルバイトの黒字を相殺できる(損益通算)
個人事業で赤字が出てしまった場合でも、アルバイトによる給与所得があれば、確定申告で両者を相殺することが可能です。
上記の手法を損益通算と呼びます。
例えば、事業で50万円の赤字が出た一方で、給与所得が200万円あった場合、損益通算によって所得金額を150万円に圧縮できます。
結果的に所得金額が抑えられることで課税対象額も抑えられ、最終的に所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。
中でも、事業の立ち上げ期などで収入が不安定な個人事業主にとって、損益通算は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
一方、損益通算を適用するためには必ず確定申告を行う必要があるため、的確に手続きできるようにしておくと良いのではないでしょうか。
条件を満たせば確定申告が不要になるケース
個人事業主がアルバイトをしている場合でも、特定の条件を満たせば確定申告が不要になることがあります。
具体的には、アルバイト先で年末調整を受けており、給与所得以外の所得(事業所得など)の合計額が年間20万円以下の場合です。
この「20万円」は、売上から経費を差し引いた後の所得金額を指します。
例えば、事業の売上が50万円、経費が35万円であれば、その事業所得は15万円となり、20万円以下の基準を満たします。
一方、上記のパターンはあくまで所得税の確定申告が不要になるだけであり、住民税の申告は別途必要となるので、注意が必要です。
なお、還付を受ける場合や損益通算をしたい場合は、20万円以下でも確定申告をしなくてはなりません。
【確定申告の基本】事業所得と給与所得の違いを理解しよう

個人事業主がアルバイトする場合、確定申告では「事業所得」と「給与所得」という2種類の所得を扱うことになり、計算方法や経費の扱い方が違うため、正しく理解しておくことが重要です。
例えば、事業所得は売上から必要経費を差し引いて算出しますが、給与所得には原則として経費の概念がありません。
ここでは、事業所得と給与所得の違いについて詳しく解説します。
個人事業の売上から経費を引いたものが「事業所得」
事業所得とは、個人事業主として行っている事業から得られる所得のことです。
具体的には、年間の総売上高から、事業を運営するためにかかった必要経費を差し引いて計算します。
経費として認められるものには、仕入費、事務所の家賃、水道光熱費、通信費、広告宣伝費などがあり、この事業所得からさらに青色申告特別控除(最大65万円または55万円)や基礎控除などを差し引いた金額が課税対象となります。
そのため、日々の取引を正確に帳簿に記録し、領収書などの証拠書類を保管しておくことが、正しい事業所得を算出するために必要不可欠です。
アルバイト先から受け取る給料は「給与所得」
給与所得とは、アルバイトやパート、会社員として雇用契約に基づき、勤務先から受け取る給料や賞与などの所得を指します。
給与所得の計算方法は事業所得とは打って変わって、年間の収入金額(額面)から給与所得控除額を差し引いて算出するのが一般的です。
給与所得控除は、給与収入を得る人に認められている「みなし経費」のようなもので、実際の経費を個別に計算する必要はありません。
控除額は収入金額に応じて自動的に決まります。
なお、アルバイト先から年末に受け取る源泉徴収票には、上記の収入金額や源泉徴収された所得税額が記載されており、確定申告に必要です。
業務委託契約の収入は事業所得になるため注意
アルバイトという名目であっても、勤務先との契約が雇用契約ではなく「業務委託契約」である場合、収入は給与所得ではなく事業所得(または雑所得)に分類されます。
雇用契約は労働時間や場所が指定される従属的な関係ですが、業務委託契約は特定の業務の完成を目的とする対等な関係です。
もし個人事業主がアルバイトを雇う側であれば、そのアルバイトに支払う給料は自社の経費となりますが、自分が業務委託で働く場合は給与所得者にはなりません。
この場合、報酬から経費を差し引いて所得を計算する必要があり、契約形態を事前に確認することが欠かせません。
個人事業主がアルバイト収入を確定申告する5つの手順

次に、個人事業主がアルバイト収入を確定申告する5つの手順について見ていきましょう。
STEP1:アルバイト先から「源泉徴収票」を受け取る
確定申告には、アルバイト先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
源泉徴収票は、1年間に支払われた給与の総額、納めた所得税額(源泉徴収税額)、社会保険料の金額が記載された重要な書類で、年末調整後の12月か翌年1月頃に勤務先から交付されます。
年の途中で退職した場合は、退職後1ヶ月以内に発行されるのが通例となるため、忘れずにご確認ください。
なお、確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票に記載されている情報を正確に転記する必要があるので、受け取ったら必ず内容を確認し、厳重に保管しておきましょう。
STEP2:個人事業の収入と経費を計算し、帳簿を作成する
次に、個人事業に関する所得を計算します。
日々の売上や経費を記録した帳簿をもとに、1年間の総収入と必要経費を集計します。
上記の集計結果から、青色申告決算書や収支内訳書といった、事業所得の内訳を示す書類を作成するのが一般的な流れです。
なお、青色申告を行っている場合は、貸借対照表と損益計算書からなる青色申告決算書を、白色申告の場合は収支内訳書を作成することが必要です。
もし書類作成で躓きそうなら、会計ソフトをご利用ください。
会計ソフトがあれば日々の取引入力から上記の書類を自動で作成でき、計算ミスを防ぎつつ作業を効率化することが可能です。
正確な帳簿付けにより、適正な申告ができます。
ゆえに、慣れていない人は会計ソフトを利用しましょう。
STEP3:確定申告書に事業所得と給与所得の両方を記入する
確定申告書には、事業所得と給与所得の両方を記入する欄が設けられています。
記入する手順については、以下の通りです。
- 作成した青色申告決算書や収支内訳書をもとに、事業所得の金額を確定申告書の「収入金額等」の「事業(営業等)」欄と「所得金額等」の「事業(営業等)」欄に記入
- アルバイト先から受け取った源泉徴収票の内容を見ながら「収入金額等」の「給与」欄と「所得金額等」の「給与」欄に金額を転記
以上のように、別々の種類の所得を所定の欄にそれぞれ正確に記入し、すべての所得を合算することが必要となります。
もし自力での対応が厳しそうな場合は、税理士に相談すると安心です。
STEP4:源泉徴収票に記載された源泉徴収税額を転記する
給与から天引きされた所得税額は、確定申告において非常に重要な情報です。
アルバイト先の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」を、確定申告書の「税金の計算」セクションにある「源泉徴収税額」の欄に忘れずに転記してください。
上記の転記を忘れると、すでに納付済みの税金が考慮されず、二重に税金を支払うことになってしまいます。
逆に、正しく転記することで年間の所得から算出した本来の所得税額から、この源泉徴収税額が差し引かれ、最終的な納税額または還付額が確定します。
なお、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、それぞれの源泉徴収票の金額を合計して記入することが必要です。
STEP5:申告期限内に税務署へ提出し、納税または還付を受ける
すべての記入が完了した確定申告書は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの申告期間内に、管轄の税務署へ提出します。
提出方法は「税務署の窓口へ直接持参する」「郵送する」「e-Taxを利用して電子申告する」の3つ。
どの方法も決して難しくはありませんが、自宅から手続きが完了するe-Taxが便利です。
一方、申告の結果、追加で納税が必要になった場合は期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納付しなければならないため、注意が必要です。
反対に税金を払いすぎていた場合は、申告書記載の銀行口座へ還付金(申告からおおむね1ヶ月から1ヶ月半程度)が振り込まれます。
確定申告に必須!源泉徴収票のよくある疑問
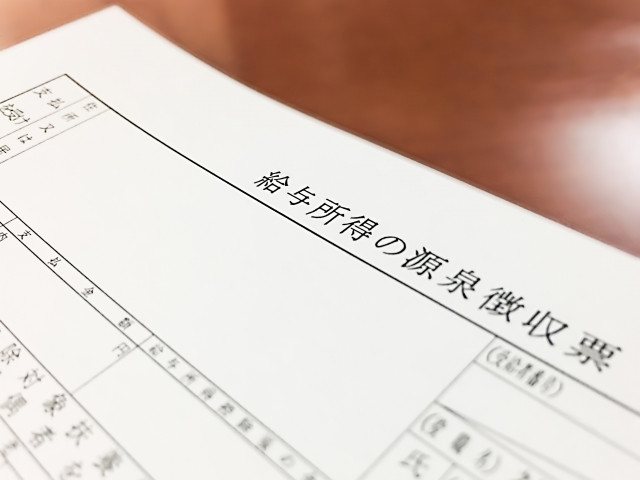
次に、確定申告に必須となる源泉徴収票のよくある疑問について見ていきましょう。
源泉徴収票がもらえない場合はどうする?
法律上、雇用主は従業員に対して源泉徴収票を交付する義務があります。
もしアルバイト先から源泉徴収票が交付されない場合は、まず経理や人事の担当者に発行を丁重に依頼しましょう。
それでも発行に応じてもらえない場合は、所轄の税務署に相談し「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するという手段を取るのが効果的です。
この届出書を提出すると、税務署からアルバイト先へ行政指導が行われることがあります。
最終手段として、給与明細など収入額がわかる書類をもとに自分で収入と源泉徴収税額を計算し、申告書を作成することも可能です。
しかし、余計なトラブルになることもあるからこそ、まずは勤務先への請求を優先してください。
源泉徴収票を紛失した場合はどうする?
源泉徴収票をなくしてしまった場合でも、心配は不要です。
発行元であるアルバイト先に連絡すれば、再発行をしてもらえます。
源泉徴収票は確定申告の添付義務はなくなりましたが、申告書を作成する上で記載内容が必須となるため、手元にないと正確な申告ができません。
再発行には時間がかかる場合もあるので、紛失に気づいたらできるだけ早く勤務先の担当部署に連絡し、再発行を依頼することが重要です。
ただし、確定申告の期限が迫っている時期は会社の業務も立て込んでいる可能性があるからこそ、余裕を持って行動しておくと安心できます。
源泉徴収税額が0円でも源泉徴収票は発行される?
毎月の給与が8万8,000円未満であるなど、所得税が源泉徴収されていない場合でも、アルバイト先は源泉徴収票を発行する義務があります。
源泉徴収票には、支払われた給与総額が記載されており、これが給与所得の申告における収入金額の根拠となります。
そのため、源泉徴収税額が0円であっても、確定申告にはこの源泉徴収票が必要です。
給与収入があったという事実を証明する公的な書類として、必ず受け取り、申告書作成時に内容を転記しなくてはいけません。
収入があったにもかかわらず申告しないと、申告漏れを指摘される可能性があるため注意が必要です。
アルバイトをすると税金や社会保険はどう変わる?

次に、アルバイトをすると税金や社会保険はどう変わるのかについて見ていきましょう。
月収8万8,000円以上で所得税が給与から天引きされる
アルバイトの月収が8万8,000円以上になると、所得税が給与から天引きされます。
これは国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいており、社会保険料等を控除した後の給与額がその基準を超える場合に適用されるのが一般的です
なお、金額はあくまで目安で、扶養親族の有無などによって変動します。
では天引きされた分はどうなるかというと、会社が本人に代わって国に納付するのが通例。
前述の通り、この源泉徴収税額は概算となるため、確定申告で年間の所得を正しく計算し、それぞれ最終的な納税額を確定させる必要があるでしょう。
原則、払いすぎている場合は還付され、不足している場合は追加で納付するので、状況に応じて適切な対応が必要です。
住民税は前年の所得をもとに翌年課税される
住民税は、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算され、翌年に課税される仕組みです。
個人事業主の場合、確定申告を行うと、その情報が税務署から各市区町村へ送られ、住民税額が決定されます。
決定した税額は、市区町村から送付される納税通知書に基づき、通常4期に分けて自分で納付(普通徴収)するのが一般的です。
なお、アルバイト収入がある場合、事業所得と給与所得を合算した総所得金額が住民税の計算基礎となるからこそ、アルバイトによって所得が増えた翌年は住民税の負担も増えることを念頭に置いておく必要があります。
勤務先の社会保険に加入できる条件とは
アルバイトでも、一定の条件を満たすと勤務先の健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入できます。
主な条件は以下の通り。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8.8万円以上であること
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること
- 学生でないこと
以上の条件を満たす場合、個人で国民健康保険や国民年金に加入している個人事業主は、勤務先の社会保険に切り替えることが可能です。
なお、社会保険に加入すると、保険料の半分を会社が負担してくれるため、自己負担が軽減されます。
例外として、アルバイト先に「扶養控除申告書」を提出しているかどうかも関係するので、加入条件については勤務先に確認するのが確実です。
まずは、自分が置かれている条件について把握してみてはいかがでしょうか。
アルバイトの通勤費は個人事業の経費にできる?

最後に、アルバイトの通勤費は個人事業の経費にできるかについて見ていきましょう。
アルバイトのための支出は事業経費として計上できない
事業所得の計算で認められる経費は、あくまで「事業を運営するために直接必要な支出」に限られます。
ゆえに、アルバイト勤務のための交通費、アルバイトで着用する制服やスーツの購入費、仕事に関連する書籍代などは、事業の経費として計上することはできません。
これらの支出は給与所得を得るためのものと見なされ、その代わりとして給与所得者には「給与所得控除」が認められています。
もし、事業とアルバイトの両方で使用する物品がある場合は、家事按分と同様の考え方で、事業で使用する割合分のみを経費として計上することが必要です。
公私の区別と同様に、事業と給与の区別も明確につけるのが通例です。
まとめ

個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合、原則として事業所得と給与所得を合算して確定申告が必要です。
確定申告では、アルバイト先から交付される源泉徴収票と、自身で作成した事業の帳簿をもとに、申告書を作成します。
なお、事業で赤字が出た場合には、給与所得と損益通算することで節税が可能です。
また、給与から源泉徴収された所得税は、確定申告によって還付される可能性もあります。
まずはアルバイトのための交通費などは事業の経費にできない点に注意し、所得の種類に応じた正しい申告手続きを行いましょう。
もしわからないことがある場合は、税理士といった専門家にご相談ください。















