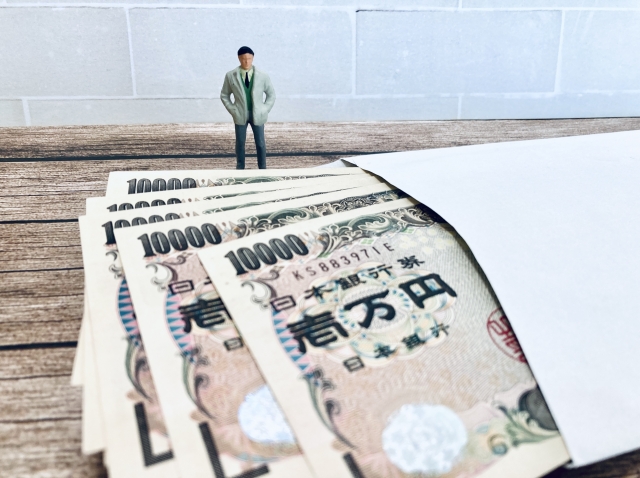「自営業」と「自由業」は、どちらも会社に所属しない働き方を指す言葉ではあるものの、両者の意味にはそれぞれ違いがあるからこそ、注意が必要です。
起業や独立を考えた場合、これらの言葉の正確な意味やフリーランスとの関係性を理解しておくことは欠かせません。
そこで、この記事では自営業・自由業の意味から、具体的な職種の例、起業・独立して働くメリット・デメリットまで詳しく解説します。

INDEX
まずは基本から!自営業と自由業の意味を解説

まずは、自営業と自由業の意味について見ていきましょう。
自営業とは?法人・個人を問わず独立して事業を行う働き方
自営業とは、組織に属さず、自身で独立して事業を営む働き方の総称です。
個人事業主として開業届を提出して活動する人だけでなく、法人を設立して会社を経営する人も自営業者に含まれます。
事業内容は多岐に渡り、飲食店や小売店、美容室といった店舗を構えてビジネスを行う人から、農家や漁師、伝統工芸の職人まで独立して生計を立てている人はすべて自営業に該当すると思って良いでしょう。
そのように、事業の規模や形態を問わず、自ら事業を運営しているのが自営業の特徴です。
自由業やフリーランスも、この自営業という枠組みの一部と位置づけられます。
自由業とは?特定のスキルを活かし時間や場所に縛られない働き方
自由業とは、自営業の一種であり、特定の組織に所属せず、自身の専門的な技術や知識といったスキルを提供することで成り立つ働き方を指します。
具体的な特徴としては、働く時間や場所に関する制約があまりなく、契約ごとに仕事を請け負うスタイルが中心である点です。
例えば、カメラマンやコンサルタント、デザイナーやプログラマー、ライターといった職種が典型例として挙げられるのではないでしょうか。
該当の職業は、大型の店舗や大規模な設備を必要とせず、スマホやパソコンなどの専門機材があれば時間も場所もを選ばずに仕事を進めることが可能です。
自営業の中でも、時間や場所が自由な働き方として区別されます。
【結論】自営業と自由業の違いは「働き方のスタイル」

自由業と自営業との決定的な違いは、事業の法人・個人の別や業種ではなく「働き方のスタイル」にあると言って良いでしょう。
自営業は、独立して事業を営む人全般を指す幅広い概念です。
店舗経営のように営業時間や営業場所に制約がある働き方も含みます。
対して自由業は、自営業の中でも特に特定のスキルを資本とし、時間や場所に縛られずに働くスタイルを指すのが一般的とされています。
つまり、自由業は自営業という枠組みに含まれる一つの働き方なのです。
言い換えると「すべての自由業は自営業に含まれるものの、すべての自営業が自由業であるとは限らない」と言えるのではないでしょうか。
混同しやすい「フリーランス」と自営業・自由業の関係性

自営業や自由業と並んでよく使用される「フリーランス」という言葉は、特定の企業や団体と雇用契約を結ばず、案件単位で契約を結ぶ「契約形態」を指します。
自営業や自由業が事業の運営形態や働き方のスタイルを指すのに対し、フリーランスは仕事の受け方に焦点を当てた言葉です。
ゆえに、個人事業主として活動する自営業者や自由業者の多くは、フリーランスという契約形態で働いていると言えるのではないでしょうか。
要するに「自営業者(または自由業者)であり、かつフリーランスである」というのが一般的と言えるでしょう。
具体的な職種でイメージ!自営業と自由業の仕事例

次に、自営業と自由業の仕事例について見ていきましょう。
自営業にあたる職種の具体例
自営業の中で、自由業のイメージとは異なる職種の例としては、物理的な拠点や設備が事業に不可欠なものが挙げられます。
例えば、飲食店経営者やカフェオーナー、パン屋、小売店主、美容師、整体師などは、店舗を構えてサービスを提供するため、場所や営業時間に制約があります。
同様に、広大な土地が必要な農家、漁船や港を拠点とする漁師も自営業の典型例です。
また、一人親方として活動する左官や大工といった建設業者も、現場に赴いて仕事をするので、働く場所が指定されるのが一般的です。
これらの職種は、それぞれ独立して事業を営んでいる点では自営業と言えるものの、時間や場所の自由度があまりない点で自由業とは区別した方が良いでしょう。
自由業にあたる職種の具体例
自由業は専門的なスキルを活かし、時間や場所に縛られずに働ける職種が中心です。
例えば、代表的なものとしてはイラストレーターやWebデザイナー、プログラマー、編集者や翻訳家、ライターなどが挙げられます。
それらの職種は、インターネット環境さえあれば仕事を進めることが可能なのが特徴です。
また、音楽家をはじめ、コンサルタントやジャーナリスト、俳優、フォトグラファーといった職種も自由業に含まれます。
クライアントとの打ち合わせや取材、撮影で特定の現場に赴くことはあっても、業務時間は自身の裁量で決められるからこそ、自由業と表現しても問題ないのではないでしょうか。
自営業であり自由業でもある職種の具体例
自営業と自由業の両方の側面を持つ職種も数多く存在します。
そもそも自由業は自営業という枠組みに含まれ、自由業の職種はすべて自営業と言えます。
その中でも特に両方の性質を併せ持つ典型例が、公認会計士や司法書士、税理士や弁護士といった「士業」を生業としている人たちです。
これらの職業は、高度な専門技術や専門知識を活かして独立している点で自由業の特性を持っているものの、多くの人が事務所を構えて事業を営むため、自営業としての側面も色濃いです。
また、個人で学習塾を経営する講師や特定の事務所に所属しないファイナンシャルプランナーも、事業拠点と専門スキルを持つ点で両方の特徴を兼ね備えています。
ただ、分類については明確な基準があるわけではないので、人によって認識は千差万別です。
独立前に知りたい!自営業・自由業として働くメリット

ここからは、自営業・自由業として働くメリットについて見ていきましょう。
自分の裁量で仕事内容やスケジュールを決められる
自営業・自由業として働く最大のメリットは、仕事の進め方に関する裁量権がある点です。
どのような仕事を引き受けるか、どのクライアントと取引するかを自分で選べます。
また、働く時間や休日も自由に設定でき、朝型の生活や夜型の生活、週休3日という具合に自身のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
平日に休みを取って旅行に出かけたり、学校行事に参加したりすることも可能。
会社組織のルールや人間関係に縛られることなく、自分の価値観や目標に基づいて仕事に取り組める点は自営業・自由業の魅力と言えるでしょう。
オフィスや自宅など働く時間や場所を自由に選択できる
自営業・自由業は、働く時間や場所を自由に選べるのもメリットです。
職種によっては通勤の必要もなく、自宅の書斎やリビングを仕事場にできます。
この結果、通勤の手間を削減し、その分仕事やプライベートの充実に充てられます。
また、気分転換にカフェやコワーキングスペースで仕事をしたり、実家に帰省しながら業務を続けたりすることも可能です。
状況によっては国内の住みたい地域に移住したり、海外で生活しながら日本のクライアントと仕事をしたりと、より自由なライフプランも実現できるのではないでしょうか。
成果次第で会社員以上の収入を得ることも可能
自営業や自由業の収入は、会社員のような固定給ではなく、努力が直接反映される成果報酬型となっているのが一般的です。
ゆえに、収入に上限がありません。
専門スキルを習得し、単価の良い案件を獲得したり、効率的に複数の仕事をこなしたりすることで、会社員時代の収入を超える可能性も十分あります。
事業が軌道に乗れば、人を雇用して事業を拡大したり、新たなサービスを展開したりすることで、さらなる収入アップを目指すことも可能です。
自分の頑張りや工夫がダイレクトに報酬として返ってくる点は、仕事へのモチベーションにも繋がるでしょう。
定年を気にせず生涯現役で働き続けられる
会社組織には一般的に定年制度がありますが、自営業や自由業には定年がありません。
自身の健康と働く意欲さえあれば、年齢に関係なく生涯現役で働き続けることが可能です。
これは、長年のキャリアで培ってきた技術や知識といったスキル、経験や実績、人脈を活かし続けられることを意味します。
むしろ、年齢を重ねることでかえって信頼性や専門性を得られる職種も珍しくありません。
それぞれの気力や体力に合わせて仕事量を調整するなど、自分のペースで働き続けられる点は、人生100年時代における働き方としてメリットしかないのではないでしょうか。
覚悟も必要!自営業・自由業として働くデメリット

ここでは、自営業・自由業として働くデメリットについて見ていきましょう。
収入が不安定で月によって変動しやすい
自営業・自由業で最も大きなデメリットは、収入が不安定であることです。
会社員のように毎月決まった給料が保証されているわけではなく、仕事の受注状況やクライアントの都合によって、月々の収入は常に変動します。
案件が途切れれば収入がゼロになるリスクも……。
また、怪我や病気で働けなくなった場合、会社員のような傷病手当金などの公的な保障が受けられず、自身の貯蓄や民間の保険で備えておく必要があるでしょう。
安定した収入を確保するには、常に新規顧客を開拓する営業努力や複数の収入源を持つといった戦略が必要となり、常に気が休まることはありません。
仕事の獲得から経理まで全て自分で行う必要がある
独立すると、専門分野の仕事だけをしていれば良いわけではありません。
会社では営業、経理、総務といった部署が分担してくれていた業務も、自営業や自由業ではすべて1人でこなす必要が出てきます。
具体的には仕事を見つけるための営業活動、クライアントとの交渉や契約手続き、請求書の発行や入金管理、年に一度の確定申告といった経理・税務作業など、多岐に渡るタスクが発生するわけです。
これらの事務作業に時間を取られ、本業に集中できないこともあるのではないでしょうか。
そのため、専門スキルだけでなく事業全体を運営するマネジメント能力が欠かせません。
社会的信用が得にくくローン審査で不利になる場合がある
一般的に、自営業や自由業は会社員に比べて社会的信用がありません。
これは、収入が不安定であるという認識が背景にあるためです。
その結果、自動車ローンや住宅ローンといった金融契約、クレジットカードの作成、賃貸物件の入居審査など、様々な場面で不利になる場合があります。
特に独立して間もない時期は実績がないので、審査に通らないことも珍しくありません。
ローンを検討している場合は、会社員のうちに手続きを済ませておくか、独立後数年間の確定申告で安定した収入を証明できるような事業計画を立てる必要があります。
逆に、定期的に収入があることさえ証明できれば、問題はないです。
仕事とプライベートの区別がつきにくくなる
働く時間や場所が自由であることは自営業・自由業の魅力であるものの、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりやすいというデメリットも生み出します。
中でも自宅で仕事をしていると、深夜まで際限なく働き続けてしまったり、逆に家族がいることで仕事に集中できなかったりすることは珍しくありません。
オンとオフの切り替えがうまくいかず、心身の健康を損なう原因にもなりかねません。
ゆえに、意識的に仕事の開始時間と終了時間を決めたり、仕事専用のスペースを設けたりして自己管理を徹底し、自分なりのルールを作ることが重要です。
まとめ

自営業は法人・個人を問わず独立して事業を営む人全般を指す広範な言葉、自由業は自営業の中でも特に専門スキルを活かして時間や場所に縛られずに働くスタイルを指します。
例外として、フリーランスは特定の組織に属さず案件ごとに契約する働き方を指します。
どの働き方も、自分に裁量権があったり、収入の上限がなかったりといったメリットがある一方、収入の不安定さや自己管理の難しさといったデメリットもあるからこそ、慎重な判断が必要です。
まずは各言葉の意味と起業や独立に伴うメリット・デメリットを正しく理解し、自身のキャリアプランを検討することが重要です。