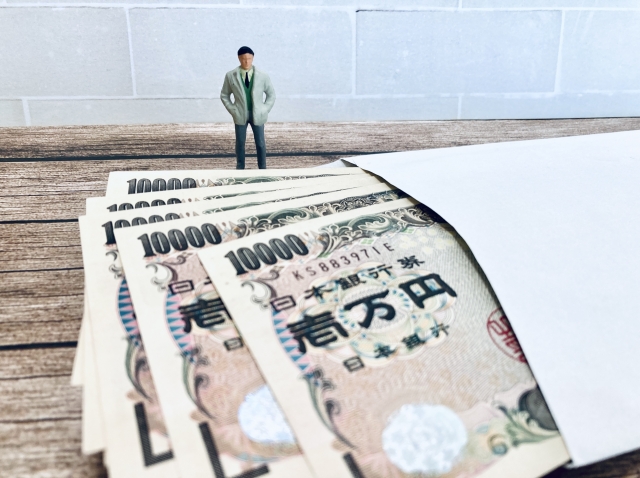障がい者グループホームの経営は、社会貢献性が高いだけでなく、安定した収益が見込める事業として注目されており、国の障害福祉サービス報酬を主な収入源とするからこそ、景気の動向に左右されにくいのが特徴です。
一方で、どれくらいの年収になるのか気になる人もいるかもしれません。
そこで、この記事では、グループホーム経営で目指せる年収の目安から、具体的な収支モデル、収入と支出の内訳、経営を成功させるためのポイントまで、実践的な情報を詳しく解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶会社設立の流れとは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説
▶高齢者向けビジネス成功例を調査!市場の特徴やおすすめのビジネスを知ろう!
▶訪問介護の開業に必要な資金・費用は?申請の流れや助成金まで解説

INDEX
障がい者グループホーム経営で目指せる年収の目安

障がい者グループホーム経営における経営者の年収は、施設の規模や定員、提供するサービス内容、加算の取得状況によって変動します。
例えば、定員4名から10名程度の小規模な施設を1棟運営する場合、オーナーの役員報酬として得られる年収の目安は500万円〜1,000万円程度が一般的です。
複数の事業所を展開するなど大規模な事業規模では、より高い年収を目指せます。
ただ、上記はあくまで順調に運営できた場合の目安であり、安定した収益を確保するには、収入構造の理解と適切なコスト管理が求められます。
【収支モデル】具体的な年収シミュレーション

障がい者グループホーム経営の収益性をより具体的に理解するには、実際の収支モデルに基づいたシミュレーションを見るのがわかりやすいです。
ここからは、比較的一般的な「定員4名、世話人等を人員基準通りに配置」した施設を例に、月間および年間の収入と支出を算出し、最終的に得られる利益額を試算します。
収入のシミュレーション(定員4名の場合)
定員4名のグループホームにおける主な収入源は、国保連から支払われる訓練等給付費と、利用者から徴収する家賃や食費で賄うのが一般的です。
例えば、障がい支援区分3の利用者4名が入居した場合、訓練等給付費は約130万円程度になります。
これに利用者1人あたり約5万円の家賃・水道光熱費・食費を加えると、4名分で約20万円が加わります。
それを合計すると、月間の収入は約150万円となり、年間の収入に換算すると約1,800万円が見込まれる計算です。
ただ、上記はあくまで通常のモデルであり、夜間支援体制加算などの各種加算を取得することで、さらに収益を上乗せすることも不可能ではありません。
支出のシミュレーション(人件費・家賃など)
別途、運営にかかる支出のシミュレーションが必要です。
支出の中で最も大部分の割合を占めるのは人件費。
サービス管理責任者や世話人、夜間支援員など、必要な人員を配置した場合、給与や社会保険料を合わせて月々70万円から80万円程度の人件費が発生します。
また、他の支出として物件の家賃も見逃せません。
家賃は、地域にもよるものの10万円から15万円程度が必要となります。
その他、利用者へ食事を提供するための食材料費、水道光熱費、日用品や備品などの雑費、車両の維持費などを合わせると、月間の総支出額は100万円から120万円程度になることが想定されるでしょう。
これを年間に換算すると、約1,200万円から1,440万円の支出となる計算です。
シミュレーションから見る最終的な利益額
上記の収入と支出のシミュレーションを基に、最終的な利益額を算出します。
年間の収入が約1,800万円、年間の支出が約1,200万円から1,440万円と仮定すると、年間の利益は約360万円から600万円となるのが一般的です。
その利益から法人税が引かれ、残った分が内部留保や経営者の役員報酬の原資となります。
このシミュレーションはあくまで一例であり、実際には物件を自己所有して家賃を抑えたり、福祉専門職員配置等加算といった収益性の高い加算を取得したりすることで、利益額は変動するのが一般的です。
ゆえに、緻密な事業計画と効率的な運営が、収益性に直結するのではないでしょうか。
障がい者グループホームの収入を構成する3つの要素

障がい者グループホームの経営を安定させるためには、主に3つの要素から構成される収入の仕組みを正確に理解することが重要です。
ここでは、障がい者グループホームの収入を構成する3つの要素について詳しく解説します。
収益の約9割を占める国からの「訓練等給付費」
グループホームの収益の大部分、約9割を占めるのが「訓練等給付費」です。
これは、障害者総合支援法に基づいて提供される福祉サービスの対価として、国民健康保険団体連合会(国保連)から事業者に支払われる公的な報酬となります。
仕組みは単純で、利用者がサービスを利用するごとに報酬が算定され、翌々月に支払われるというもの。
それらの報酬単価は、利用者の障がい支援区分や施設の定員、職員の配置体制などによって細かく定められており、安定した事業運営の根幹を支える重要な収入源です。
景気の影響を受けにくく、計画的な経営が可能となるという特徴を持っています。
さらなる収益増を目指せる「各種加算」
訓練等給付費の基本報酬に加えて、専門的な人員を配置したり、手厚い支援体制を整えたりすることで得られるのが「各種加算」です。
これは、ハイクオリティなサービス提供を評価し、報酬を上乗せする制度であり、収益性を向上させるための重要な要素となります。
例えば、夜間の支援体制を強化する「夜間支援体制加算」、社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職を配置する「福祉専門職員配置等加算」、地域の医療機関との連携体制を構築する「医療連携体制加算」など、様々な種類があります。
それらの加算を戦略的に取得することが、収益の最大化に繋がるわけです。
利用者が負担する家賃や水道光熱費など
訓練等給付費とは別に、利用者から直接受け取ることができる費用もあります。
具体的には、事業所が定めた家賃、居室や共有スペースで利用する水道光熱費、食事の提供にかかる食材料費などです。
これらの費用は、サービス提供に必要な実費相当分として徴収するもので、事業所の収益の一部を構成するもの。
ただ、利用者の経済的負担を軽減する目的で、国や自治体から家賃補助(特定障害者特別給付費)が支給される制度もあります。
そのため、家賃設定では、地域の相場や補助制度を考慮することが重要です。
障がい者グループホームの運営で発生する主な支出

次に、障がい者グループホームの運営で発生する主な支出について見ていきましょう。
運営コストの大部分を割合を占める人件費
グループホームの運営コストの中で、大部分の割合を占めるのが人件費です。
障害福祉サービスは、利用者への直接的な支援が中心となる労働集約型の事業であり、法律で定められた人員配置基準を満たす必要があります。
具体的には、以下の通り。
- 事業所全体を統括する「管理者」
- 利用者の個別支援計画を作成する「サービス管理責任者」
- 日常生活の支援を行う「世話人」
- 夜間の見守りや緊急時対応を担う「夜間支援員」
以上の職員の給与や賞与、法定福利費が支出として含まれるわけです。
障がい者グループホームでは適切な人材を確保し、定着させることがサービスの質に直結するからこそ、人件費は経営上、最も重要な投資の一つと言えます。
物件の家賃や建物のメンテナンス費用
事業所として使用する建物の維持管理費用も継続的に発生する支出の1つです。
例えば、賃貸物件で運営する場合、毎月の家賃が固定費としてかかります。
家賃に関しては、立地や築年数、敷地面積によって金額が変動するので、事業計画の段階で慎重な物件選定が求められるでしょう。
自己所有物件の場合でも、固定資産税や火災保険料、定期的な修繕のための費用が発生するため、トラブルを予想することが必要となるのではないでしょうか。
具体的には、経年劣化による外壁の補修や設備の交換など、まとまった支出となる可能性があるので、長期的な視点で修繕計画を立て、資金を積み立てておくことが重要です。
また、消防設備の定期点検など、法律で義務付けられているメンテナンス費用も考慮に入れる必要があります。
日々の食事提供に必要な食材料費
利用者に対して食事を提供する場合、材料の購入費用も日常的な支出となります。
食材料費は、利用者から実費相当額を徴収することになるがゆえに、直接的な利益には結びつきませんが、資金繰りの面では重要な管理項目です。
栄養バランスやアレルギーへの配慮、利用者の嗜好を考慮しながら、無駄なく食材を仕入れる必要があり、献立の作成や買い出し、調理といった業務負担も発生します。
経営方針によっては、外部の配食サービスを利用する選択肢もあり、人件費や管理の手間を削減できる可能性があるものの、1食あたりのコスト計算が必須です。
開業時に準備すべき初期費用の内訳

次に、開業時に準備すべき初期費用の内訳について見ていきましょう。
物件の取得やバリアフリー化の工事費用
初期費用の中で最も比重を占めるのが、物件の取得や整備に関する費用です。
賃貸物件を利用する場合、保証金をはじめ敷金や礼金、仲介手数料、前家賃などが必要となり、都心部では初期費用だけで数百万円が必要となることもあります。
物件を新たに建築または購入する場合は、より高額な資金が求められます。
加えて、障がいを持つ利用者が安全かつ快適に生活できるよう、既存の建物を改修する必要が生じるケースも珍しくありません。
例えば、玄関へのスロープ設置、廊下や浴室への手すりの取り付け、段差の解消といったバリアフリー化工事の費用も見込んでおくことが必要です。
ベッドや家電など生活に必要な備品の購入費
利用者が入居した日から共同生活を始められるように、必要な備品をすべて揃える費用も初期投資に含まれます。
各利用者の居室には、ベッド、寝具、カーテン、収納家具が必要です。
また、リビングや食堂などの共有スペースには、テーブル、椅子、ソファ、テレビといった家具に加え、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器などの大型家電も必要です。
調理器具や食器類、掃除用具といった日用品も一式購入しなければなりません。
それだけでなく、消防法で設置が義務付けられている消火器や自動火災報知設備などの防災関連の備品購入費も忘れてはならない項目と言えるでしょう。
これらを合計すると、100万円から200万円程度の費用がかかります。
事業開始に向けた法人設立や採用活動の経費
障がい者グループホームを運営するためには、株式会社や合同会社、NPO法人といった法人格の取得が必須となります。
法人を設立するには、定款の作成・認証や法務局への登記手続きが必要で、登録免許税や司法書士への報酬も発生するのが一般的です。
また、事業を開始する前に、管理者やサービス管理責任者といった有資格者を確保しなければなりません。
ゆえに、求人サイトへの広告掲載費用や人材紹介会社への手数料など、採用活動のための経費も初期費用として計上しておく必要があるのではないでしょうか。
上記のように事務的な手続きや準備にかかる費用も、事業計画に盛り込んでおかなければいけません。
障がい者グループホーム経営で失敗しないための3つのポイント

次に、障がい者グループホーム経営で失敗しないための3つのポイントについて見ていきましょう。
ポイント1:質の高いサービスを支える人材の確保と育成
障がい者グループホームの質は、現場で働く職員の専門性や人柄に依存します。
ゆえに、事業成功の最も重要な鍵を握るのは、質の高い人材を確保し、継続的に育成していくことにあるわけです。
特に、利用者の個別支援計画を作成するサービス管理責任者は事業運営の要となるため、経験豊富で信頼できる人材を見つけることが欠かせません。
また、採用後も定期的な研修や面談の機会を設け、職員のスキルアップやモチベーション維持を図ることも、離職を防ぎ、安定したサービス提供に必要不可欠です。
だからこそ、働きやすい職場環境を整え、職員が長期的に活躍できる体制を築くことが求められます。
ポイント2:利用者を安定的に集めるための営業戦略
どれだけ素晴らしい施設やスタッフを揃えても、利用者がいなければ事業は成り立ちません。
施設を開設したからといって、自然と入居希望者が集まるわけではないのです。
利用者を安定的に確保するためには、地域における地道な営業活動が求められます。
具体的には、地域の相談支援事業所や自治体の障害福祉担当課、病院の医療ソーシャルワーカーなど、利用者の紹介につながる可能性のある関係機関へ定期的に訪問し、施設のパンフレットを渡したり、空室情報を提供したりして、良好な関係を築いていくことが重要です。
事業所の特色を明確に伝え、信頼を得ていくのは経営の安定化に直結します。
ポイント3:自己資金の負担を軽減する補助金の活用
グループホームの開業には多額の初期費用がかかり、自己資金だけですべてを賄うのは現実的ではないでしょう。
そこで重要になるのが、国や自治体が設けている補助金や助成金制度の積極的な活用です。
例えば、国や自治体によっては、施設の建設や改修、防災設備の整備にかかる費用の一部を補助する制度が存在します。
これらの公的支援を最大限に活用するのは、初期投資を抑え、開業後の資金繰りを安定させる上で非常に有効な手段となるのではないでしょうか。
ただ、補助金の種類や要件、申請期間は自治体によって変わるので、開業を計画する段階から情報収集を始め、専門家のアドバイスも受けながら、計画的に申請準備を進めることを忘れないようにしてください。
経営前に知っておきたい障がい者グループホームの基礎知識

最後に、経営前に知っておきたい障がい者グループホームの基礎知識について見ていきましょう。
障がい者の地域生活をサポートする共同住居
障がい者グループホームは、法律上「共同生活援助」と呼ばれる障害福祉サービスの1つで、身体・知的・精神などの障がいを持つ者が、専門スタッフである世話人や生活支援員のサポートを受けながら、共同生活を送る住まいのことを指します。
大規模な入所施設とは異なり、より家庭に近い環境で、一人ひとりの個性や能力に応じて自立した生活を送るのが主な目的。
食事や入浴の介助といった身体的な支援だけでなく、金銭管理の相談、関係機関との連絡調整、日中の活動に関する助言など、利用者が地域社会の一員として安心して暮らしていくための幅広いサポートを提供する、障がい者にとって重要な社会資源です。
サービス内容で分けられる3つの事業類型
障がい者グループホームは、提供するサービス内容に応じて主に3つの類型に分類されており、どの類型で事業を行うかによって人員配置基準や報酬単価が違います。
- 一つ目:「介護サービス包括型」で、事業所の職員が日常生活の支援に加えて、食事や入浴、排せつなどの介護も一体的に提供する最も一般的な形態
- 二つ目:「外部サービス利用型」で、日常生活の相談や支援は事業所の職員が行い、専門的な介護が必要な場合は外部の居宅介護事業所と契約する形態
- 三つ目:「日中サービス支援型」で、24時間支援体制を整え、日中も施設内で活動する利用者に対して手厚いサポートを提供する形態
どの類型を選択するかは、対象とする利用者の障がい特性や地域のニーズを踏まえて決定する必要があるからこそ、慎重な判断が必要です。
まとめ

障がい者グループホーム経営の年収は、施設の定員、加算の取得状況、コスト管理といった複数の要因によって変動します。
収益の約9割を占める訓練等給付費を安定的に確保しつつ、人件費や家賃などの支出を適切にコントロールすることが、健全な経営の基盤です。
障がい者グループホームで成功するためには、質の高い人材の確保と育成、関係機関との連携による安定した利用者獲得、初期投資や運営コストの負担を軽減するための補助金活用が重要なポイントとなります。
事業開始前には、共同生活援助というサービスの役割や事業類型を深く理解し、綿密な事業計画を立てることが重要です。