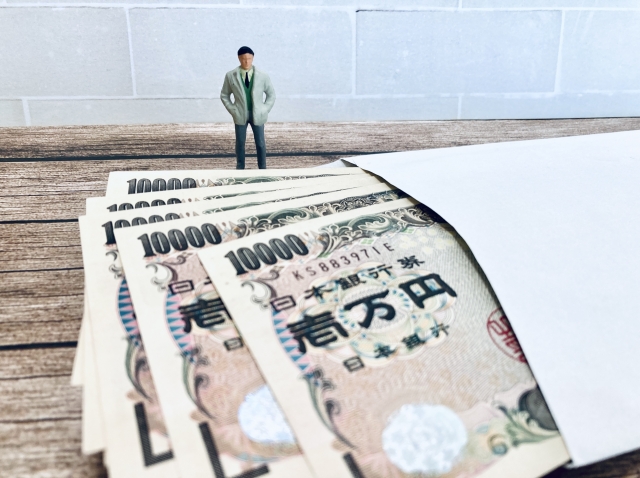バーを開業したいと考えた際「開業資金はいくら必要なのか」が気になるものです。
特に、飲食業界が未経験の場合、費用の内訳や相場がわからず不安に感じるでしょう。
人によっては、いくらかかるのかまったくわからない人もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事ではバーの開業資金の目安をはじめ、具体的な内訳や費用、資金を安く抑えるコツについて詳しく解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶飲食店によくあるプレオープンとは何?目的やメリットを解説します
▶路面店とは?テナントの違いを解説!
▶開業資金の集め方!起業にはいくら必要?ノウハウを得ながら収入を得るお得な貯め方もご紹介!

INDEX
バーの開業に必要な資金は総額〇〇円が目安

バーの開業に必要な資金は、店舗の規模や立地、コンセプトによって変動するものの、一般的には500万円から1,000万円程度が目安です。
一方、こじんまりした店舗は500万円未満で開業できるケースもありますが、都心部の一等地でこだわりの内装を施す場合は1,000万円を超えることも珍しくありません。
だからこそ、物件取得や内外装工事などの「初期費用」と開業後の経営を支える「運転資金」、それぞれの内容を正確に把握することが重要です。
物件取得や内装工事にかかる「初期費用」の内訳
初期費用は、開業準備段階で必要となる一度きりの支出です。
主な内訳は、物件取得費(保証金、礼金、仲介手数料など)、内外装工事費、厨房設備費、備品購入費などが挙げられます。
- 物件取得費:家賃の6ヶ月から10ヶ月分が相場
⇒バーの開業資金において大部分の割合を閉める - 内外装工事費:物件の状態によって変動
⇒スケルトン物件の場合は高額になる傾向がある - その他
⇒グラスや皿、レジシステムといった備品、製氷機や冷蔵庫などの厨房機器の購入にも費用がかかる
ゆえに、初期費用は潤沢な資金が必要となると言えるでしょう。
開業後の経営を支える「運転資金」の内訳
運転資金は、開業直後から経営が安定するまでの期間、店舗運営に必要な費用です。
主な内訳としては、毎月の家賃、スタッフを雇用する場合の人件費、お酒や食材の仕入れ費、水道光熱費、広告宣伝費などが含まれます。
特に開業当初は売上が不安定になりがちなため、少なくとも3ヶ月分、多めに見積もって6ヶ月分程度の運転資金を準備しておくと資金繰りも安心。
運転資金を確保しておくことが、安定した経営の土台となるのではないでしょうか。
バーの開業資金を調達する3つの方法

バーの開業に必要な資金は、複数の方法を組み合わせて調達するのがセオリーです。
主な調達方法としては「自己資金」「金融機関からの融資」「家族や知人からの支援」の3つが挙げられます。
自己資金で準備する
自己資金は、返済の必要がない最も安全な開業資金です。
金融機関から融資を受ける際にも、自己資金の額は審査における重要な評価項目となり、一定額を用意できているとそれだけで信用を得られます。
開業資金全額を自己資金で準備できれば、返済のプレッシャーなく経営に集中できます。
他方、十分な額を貯めるには時間がかかるため、計画的に準備を進めることが重要です。
まずは目標額を設定し、コツコツと貯蓄を始めてみてください。
日本政策金融公庫から融資を受ける
自己資金だけでは不足する場合、日本政策金融公庫からの融資も効果的です。
日本政策金融公庫は、政府系金融機関であり、民間の銀行に比べて新規開業者への融資に積極的で、比較的低い金利で借入できる可能性があります。
「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」といった制度を活用すれば、これから事業を始める人にとって心強い味方となってくれるでしょう。
なお、融資を受けるには、事業計画書の提出と面談が必要になるので、しっかりとした準備が求められます。
家族や知人から支援してもらう
場合によっては、家族や知人から資金を借り入れる方法もあります。
金融機関からの融資と比べて、手続きが簡便で柔軟な条件で借りられる可能性がある点が魅力です。
ただ、親しい間柄であっても金銭の貸し借りはトラブルの原因になりかねません。
ゆえに、借入額、返済期間、金利などを明記した借用書を必ず作成することが重要です。
また、年間110万円を超える金額を贈与として受け取ると贈与税の対象となるため、税務上のルールも確認しておく必要があります。
親しい間柄の人同士でお金の貸し借りをすると関係性にも影響を与えるので、まずはバーをやることに対して応援してくれる人に相談してみましょう。
開業資金をできるだけ安く抑える4つのコツ

バーの開業には一定の資金が必要ですが、工夫次第で費用を抑えることが可能です。
具体的に、開業資金を安く抑える具体的な方法として「居抜き物件の活用」「中古品の導入」「補助金・助成金の利用」「DIYによる内装工事」の4つが挙げられます。
初期費用が安い「居抜き物件」を活用する
居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備が残された物件のこと。
居抜き物件を活用することで、内装工事費や設備購入費を削減できる可能性があります。
例えば、東京や大阪といった都心部では一から内装工事を行うと高額になりがちなものの、居抜き物件を活用すれば予算の圧迫も避けやすいです。
しかし、残された設備が古かったり、自分のお店のコンセプトに合わないレイアウトだったりするケースもあるため、契約前に物件の状態を細かくご確認ください。
中古の厨房機器や備品をそろえる
製氷機やコールドテーブル、シンクといった厨房機器や、グラス、皿などの備品は、新品で揃えるとかなりの金額になるため、中古品を積極的に活用するのが有効です。
厨房機器専門の中古販売店やインターネットオークションなどを利用すれば、状態の良いものを安価で手に入れることもできます。
ただし、保証期間の有無やメンテナンスの状況がそれぞれ変わってくるので、長期的に使用できるかを見極めましょう。
国や自治体の補助金・助成金制度を利用する
国や地方自治体は、新規創業者を支援するための補助金や助成金制度を設けています。
これらの制度は返済不要の資金となっているので、積極的に活用を検討すべきです。
代表的なものとしては「創業支援等事業者補助金」や、各自治体が独自に実施している制度があります。
一方、制度によって対象者や申請条件、受付期間が異なるからこそ、自身の事業計画に合致するものがないか、開業を計画している地域の自治体や商工会議所のホームページなどで事前に情報収集することが重要です。
DIYで内装工事費を節約する
店舗の内装工事費は、開業費用の中でもかなりの割合を占める項目の一つ。
それらの費用を節約するには、DIYも活用したいところです。
壁の塗装や棚の取り付け、簡単な家具の組み立てなど、専門的な技術を要しない部分を自分自身で行うことで、業者に依頼する費用を削減できます。
反対に、ガスや水道、電気といった専門知識が必要な工事は専門業者に依頼すべきです。
内装工事に関しては比較的時間と労力がかかるものの、こだわりを持つことでコスト削減になるのと同時にお店への愛着も深まります。
資金の前に確認!バー開業に必須の資格2選

ここからは、バー開業に必須の資格2選について見ていきましょう。
飲食店営業に不可欠な「食品衛生責任者」
食品衛生責任者は、飲食店を経営する上で必ず必要となる資格。
各店舗に1名、この資格を持つ者を置くことが食品衛生法で義務付けられています。
資格は、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講することで取得可能です。
講習は1日で完了することがほとんどで、その内容は公衆衛生学や食品衛生学など、食の安全に関する基本的な技術や知識が中心。
経営者自身が取得しておくのが一般的ではあるものの、従業員でも問題はありません。
可能であれば、開業準備の早い段階で取得しておいてください。
収容人数30名以上で必要になる「防火管理者」
防火管理者は、店舗の収容人数が30名以上(従業員含む)の場合に必要となる国家資格。
火災による被害を防ぐため、消防計画の作成や避難訓練の実施、消防用設備の点検など、防火管理の責任を担うのが一般的です。
資格には、店舗の延べ面積に応じて甲種と乙種の2種類があり、日本防火・防災協会などが実施する講習を受講し、効果測定に合格することで取得できます。
お客様と従業員の安全を守ることは経営の基本だけに、店舗の規模に応じて必要な資格を必ず取得しましょう。
バーの営業スタイルによって必要な届出・許可

ここでは、バーの営業スタイルによって必要な届出・許可について見ていきましょう。
すべての飲食店で必要な「飲食店営業許可」
バーを含むすべての飲食店を開業するためには、管轄の保健所から「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
許可を得るには、店舗の施設が食品衛生法に基づく基準を満たしていることが必要です。
具体的には、シンクの数や手洗い設備の設置、厨房の面積などが細かく定められています。
物件を契約する場合は、該当の物件で許可が取得できる見込みがあるか、図面を持参して保健所に事前相談することが、後の手戻りを防ぐ上で重要となるでしょう。
深夜0時以降も営業する場合の「深夜酒類提供飲食店営業届」
深夜0時を過ぎて、主としてお酒を提供する営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業届」を管轄の警察署に提出しなければいけません。
許可制ではなく届出制ですが、営業開始の10日前までに行う決まりです。
また、カラオケ設備を設置してお客様に利用させる場合も、該当の届出の対象となることがあります。
なお、書類の提出時には店舗の図面やメニュー表といった情報が求められます。
ゆえに、必要な書類は事前に集めておくことが重要です。
接待行為を行う場合に申請する「特定遊興飲食店営業許可」
スタッフがお客様の隣に座ってお酌をしたり、歓談したりする「接待行為」を行うバーを経営する場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、「特定遊興飲食店営業許可」または「風俗営業1号許可」が必要となります。
接客を伴うお店の許可は、飲食店営業許可や深夜酒類提供の届出と比べて取得の要件が厳しく、店舗の場所や構造、申請者の経歴が審査の対象。
無許可で接待行為を行うと厳しい罰則が科されるからこそ、安定した経営のためにも正規の手続きを踏めるようにしておくと安心ではないでしょうか。
未経験でも安心!バー開業までの7ステップ

次に、バー開業までの7ステップについて見ていきましょう。
STEP1:お店のコンセプトと事業計画を固める
まず行うべきは、どのようなバーにしたいのかというコンセプトを明確にすることです。
ターゲットとする客層、提供するお酒や料理の種類、お店の雰囲気や内装のイメージなどを具体的に固めます。
コンセプトが決まったら、それに基づいて詳細な事業計画書を作成します。
この事業計画書には、売上予測や資金計画、返済計画などを盛り込み、実現可能な経営の青写真を描いておくとより具体的な行動が可能です。
計画書は後の資金調達時にも必要となるからこそ、正確に作成しておいてください。
STEP2:開業資金の調達計画を立てる
次に、事業計画書で算出した必要な開業資金を、どう準備するかの調達計画を立てます。
具体的に自己資金でいくら用意できるかを確認し、不足する金額を明確にします。
また、不足分については日本政策金融公庫などからの融資を検討すると良いです。
なお、融資を申請する場合は事業計画書の内容が審査の鍵となるため、説得力のある資料を作成することが欠かせません。
ゆえに、複数の調達方法を組み合わせることも視野に入れ、無理のない資金計画を立てることが、後の安定した経営に繋がるはずです。
STEP3:コンセプトに合った物件を探す
コンセプトと予算が決まったら、次はお店の顔となる物件探しです。
ターゲットに設定している顧客が集まりやすい立地なのか、周辺の競合店の状況はどうなっているのかなど、慎重に調査します。
具体的には、東京や大阪といった都市部では家賃が安くないため、事業計画の売上予測と照らし合わせつつ、無理なく支払える範囲で選ぶことが重要です。
また、内装や設備の自由度が高いスケルトン物件か、初期費用を抑えられる居抜き物件かなど物件の種類もコンセプトに合わせて検討します。
STEP4:内装・外装の工事と設備の搬入
物件の契約が完了したら、コンセプトに基づいて内装・外装の工事に着手します。
信頼できる施工業者を選び、デザインやレイアウトについて綿密な打ち合わせを重ねるとよりイメージに合った店にすることが可能です。
工事のスケジュールと並行して製氷機や冷蔵庫といった厨房機器、カウンターやテーブル、椅子などの什器、音響設備などの備品を選定し、搬入のタイミングを調整します。
お客様が心地よく過ごせる空間を創り上げる重要な工程となるので、より具体的なイメージを持つことが重要です。
STEP5:必要な資格の取得と行政への届出
店舗の工事と並行して、開業に必要な資格取得と行政手続きを進めてください。
「食品衛生責任者」や店舗規模に応じた「防火管理者」の資格を取得します。
さらに管轄の保健所に「飲食店営業許可」を申請し、深夜営業を行う場合は警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業届」を提出します。
なお、手続きは申請から許可・受理まで時間がかかるため、早めの準備が肝心です。
国や自治体の補助金の申請も同時に行っておくと効率的です。
STEP6:お酒や食材の仕入れ先を決める
併せて、お店のコンセプトに合ったお酒や食材を仕入れる取引先を決定しましょう。
例えば、特定の国のワインに特化するなら専門のインポーター、幅広い種類のお酒を扱うなら業務用の酒販店など、複数の業者から見積もりを取り、品質や価格、配送ロットなどを比較検討します。
相談する際は、少量でも対応してくれるか、珍しいお酒を取り寄せられるかなど、お店の個性に合わせて柔軟に対応してくれる業者を見つけることが、魅力的なメニュー作りに繋がるはずです。
STEP7:集客活動とオープン準備
開店日が近づいてきたら、お店のオープンを告知し、集客活動を開始します。
SNSアカウントを開設して情報を発信したり、Webサイトを作成したり、近隣にチラシを配布したりと、様々な方法でアピールすることが重要です。
スポーツバーであれば、今後の試合の放映スケジュールを告知するのも良いでしょう。
同時に、スタッフの採用とトレーニング、メニューの最終調整、レジの操作確認など、開店に向けた最終準備を進め、万全の態勢でお客様を迎えられるようにしておくとより安心ではないでしょうか。
開業後に失敗しない!バー経営を成功させる3つの秘訣

最後に、バー経営を成功させる3つの秘訣について見ていきましょう。
初めてでも入りやすい雰囲気を作る
バーに対して「常連でないと入りにくい」というイメージを持つ人は珍しくありません。
ゆえに、新規顧客を獲得するには、未経験の人や一人客でも気軽にドアを開けられるような雰囲気作りが重要です。
店の前にメニューや料金を明記した看板を置いたり、外から店内の様子が見えるように窓を設けたりするだけでも顧客の不安を取り除けます。
また、スタッフが明るく声をかける、初めてのお客様にも分かりやすくシステムを説明するなど、温かい接客を心掛けるのも良いでしょう。
リピーターが通いたくなる独自の魅力を提供する
数多くのバーの中から自分のお店を選んでもらい、繰り返し通ってもらうためには、他店にはない独自の魅力が必要欠かせません。
具体的にどのような要素がリピーターに繋がるかは判断が難しいものの、希少なウイスキーやこだわりのワインの品揃えが求められたり、最新のカラオケ設備や大型スクリーンでのスポーツ観戦が求められたりします。
いわゆるお店の「売り」を明確にすることが重要です。
また、マスターの個性的な人柄や季節のフルーツを使ったオリジナルカクテル、居心地の良い空間も他店と差別化できる武器となるのではないでしょうか。
SNSを活用して効果的に宣伝する
現代のバー経営において、SNSは欠かせない集客ツールです。
InstagramやX(旧Twitter)、Facebookなどを利用して、お店の情報を積極的に発信することで、未来のリピーターに興味を持ってもらいやすくなります。
具体的には、新しく入荷したお酒の紹介や美しいカクテルの写真、店内の雰囲気などを投稿して、お店の魅力を視覚的に伝えてみてください。
また、イベントの告知やフォロワー限定の特典を用意するなど、SNSを通じてお客様とのコミュニケーションも図りましょう。
まとめ

バーを開業するには、物件取得費や内装工事費などの初期費用と、数ヶ月分の運転資金を合わせた開業資金の準備が欠かせません。
資金計画を綿密に立て、自己資金や融資などを組み合わせて調達する必要があります。
また、居抜き物件の活用や補助金の利用など、コストを抑える工夫も重要です。
資金面の他にも、食品衛生責任者などの資格取得や行政への届出も必要となるでしょう。
ゆえに、事前の入念な準備と開業後の地道な努力が、安定したバー経営の成功、しいてはファンの獲得に繋がるのではないでしょうか。