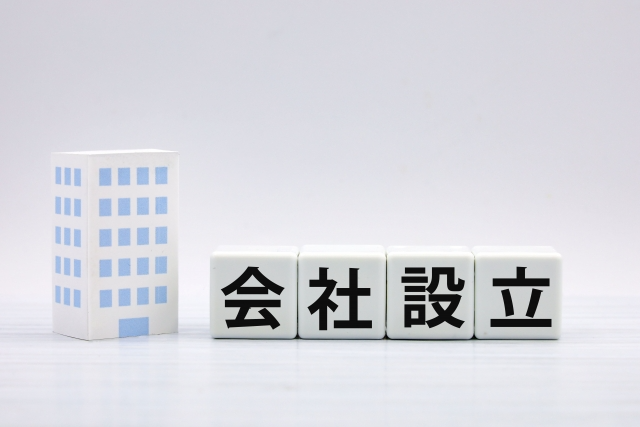自営業を始めたいけれど、どう踏み出せば良いかわからない人も珍しくありません。
自営業を始めるには、事前の準備と正しい手順の理解が不可欠です。
そこで、この記事では自営業という働き方の基本から、起業へ向けた具体的なステップ、知っておくべきメリット・デメリットまで網羅的に解説します。

INDEX
そもそも自営業とは?会社員との違いをわかりやすく解説

自営業とは、会社や企業に所属せず、自身で事業を営んで生計を立てる働き方を指します。
最近よく目にする個人事業主やフリーランスが、代表的な自営業の一種です。
会社員との相違点としては、企業と雇用契約を結んでいるかどうかという点にあります。
会社員は決められた時間働くことで毎月固定の給与を得られますが、自営業は自分の裁量で仕事を進める代わりに、収入は事業の成果に直結し、安定は保証されません。
また、福利厚生や社会保険の面でも会社員とは別物で、税金や年金の手続きはすべて自分で行うのが一般的(別途で税理士などプロに頼むことは可能)です。
あなたはどっち?自営業に向いている人の5つの特徴

自営業は、誰にでも成功できる働き方ではありません。
儲かるという魅力的な側面だけでなく、向き不向きが存在するため、注意が必要です。
では、自営業に向いている人にはどのような人がいるのでしょうか。
自営業に向いている人の特徴としては、以下の5つの特徴が挙げられます。
- 自己管理能力が高いこと
⇒時間やタスク、体調をすべて自分で管理しなくてはいけない - 主体的に行動できること
指示を待つのではなく自ら仕事を見つけて課題を解決していく力が求められる - 責任感を持っていること
⇒事業の成功も失敗もすべて自分の責任となる - 専門的なスキルがあること
- 変化やリスクを楽しむ精神を持っていること
以上の特徴を持つ人は、自営業でもうまくやっていけるはずです。
一方で、筆者のように変化やリスクへの対応が苦手でも、10年以上自営業としてやっている人もいます。
まずは、自分が自営業に向いているのか、実際にやってみるのが良いでしょう。
自営業の始め方を5つのステップで徹底ガイド

次に、自営業を始めるための5つのステップについて見ていきましょう。
Step1. 事業内容を決めてビジネスモデルを構築する
まずは自身のスキルや経験、実績、興味関心を活かせる事業内容を選ぶのが鉄則です。
例えば、飲食業界の経験があればカフェや飲食店、文章を書くのが得意ならライター、ITスキルがあればネット関連のビジネスなど、具体的なアイデアを洗い出しましょう。
事業内容が決まったら、次に「誰に」「何を」「どのように提供して」「どうやって収益を上げるか」というビジネスモデルを構築してください。
ターゲット顧客は誰か、提供する商品やサービスの価値は何かを明確にすることで、事業の方向性が定まり、競合との差別化を図ることができます。
Step2. 事業の成功確率を高める事業計画書を作成する
事業計画書は、事業の構想を具体的に言語化・数値化した設計図です。
作成する目的は、事業内容を客観的に整理し、実現可能性を確認することと、金融機関から融資を受ける際に提出を求められるためです。
具体的には、事業のコンセプトや提供するサービス、市場の分析、競合との差別化戦略、そして売上や利益の見込みを立てる収支計画などを盛り込みます。
計画を具体的にすることで、事業の課題や成功への道筋が明確になります。
書き方が分からない場合は、日本政策金融公庫のウェブサイトにあるテンプレートを活用したり、個人事業主本などの書籍を参考にしたりすると良いかもしれません。
Step3. 開業に必要な資金を準備する
開業には、事業を始めるための設備投資といった開業資金と、事業が軌道に乗るまでの運転資金が必要です。
必要な金額は業種によって変わり、パソコン一つで始められる仕事なら実質0円の場合もあれば、店舗を構える場合は800万円以上の資金が必要になることもあります。
もし自己資金だけで不足しそうな場合は、資金調達をご検討ください。
例えば、親族からの借入の他、日本政策金融公庫の新創業融資制度や地方自治体の制度融資、補助金・助成金など様々な選択肢が活用できます。
利用できるものをすべて利用することで、スムーズな開業が可能です。
まずは事業計画に基づいて必要な金額を算出し、最適な調達方法を選びましょう。
Step4. 開業に必要な届出を税務署へ提出する
個人で事業を開始する場合、原則として事業開始から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出する必要があります。
この届出を出すことで、正式に個人事業主として認められます。
また、節税効果が期待できる青色申告を利用したい場合は、同じく税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
それらの書類は事業開始から2ヶ月以内、または該当年の3月15日までに提出するのが一般的です。
なお、飲食店や建設業など業種によっては、保健所や都道府県などへの許認可申請が別途必要になるので十分にご注意ください。
可能であれば、事前に自身の事業に該当するか確認しておきましょう。
Step5. 事業スタートに向けて必要なものを揃える
開業の届出が完了したら、事業運営に必要な物品や環境を整えます。
業種によって必要なものは異なりますが、共通して準備すべきものとして、事業用の銀行口座、名刺、印鑑、パソコンなどが挙げられます。
また、日々の取引を記録するための会計ソフトの導入も必須です。
店舗を構える場合は、物件の契約や内装工事に加え、商品を販売するためのレジやキャッシュレス決済端末の準備も進めなければなりません。
もし、自宅以外で仕事をする場合はオフィスの契約や備品の購入も必要です。
自営業を始める前に知っておきたいメリット
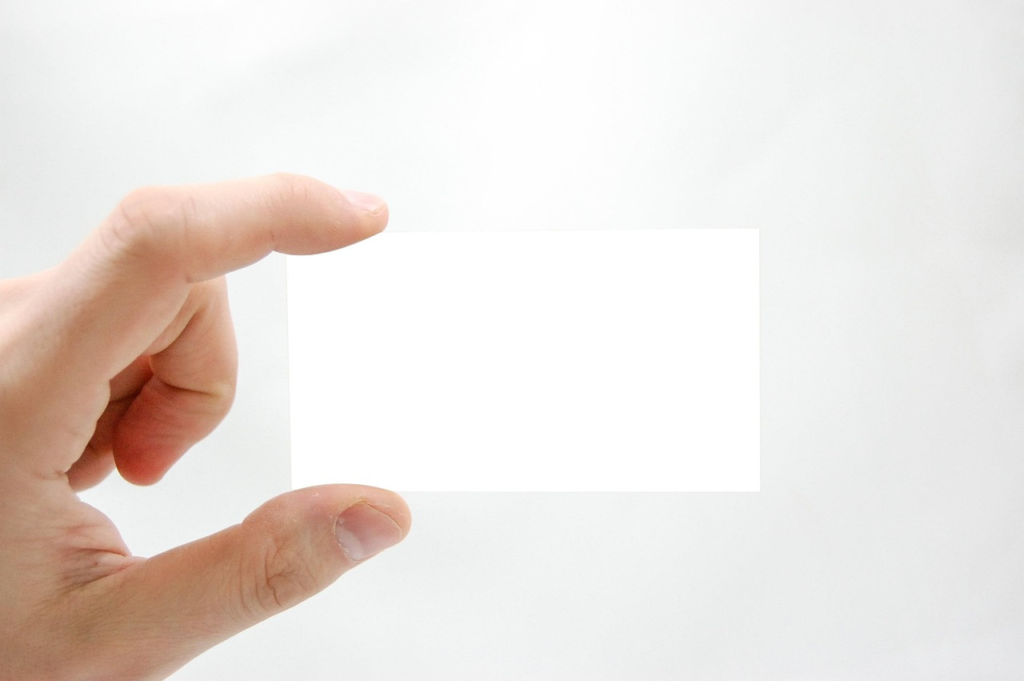
ここからは、自営業を始める前に知っておきたいメリットについて見ていきましょう。
働き方の自由度が高く自分のペースで仕事ができる
自営業のメリットの一つは、働く時間や場所を自分で自由に決められる点にあります。
会社員のように決まった出社時間やオフィスに縛られることなく、自分のライフスタイルに合わせて仕事のスケジュールを組むことが可能です。
例えば、午前中に仕事を済ませ、午後はプライベートに充てることも夢ではありません。
また、仕事量も自分でコントロールできるため、休暇を取得しやすいのも利点です。
上記のような自由な働き方は、育児や介護など家庭の事情と仕事を両立させたい人にとっても魅力と言えます。
頑張った分だけ収入アップを目指せる
会社員の場合、給与は会社の規定によって決まっており、個人の成果が大幅な収入増に直結することは稀です。
一方、自営業は事業の売上が直接自分の収入となるので、上限がありません。
提供するサービスのクオリティを確保したり、新たな顧客を獲得したりと自分の努力次第で収入を伸ばせるのも魅力の1つと言えるでしょう。
場合によっては、複数の事業を手掛けて収入源を得ることもできます。
会社の給与体系に縛られず、自分の頑張りや成果が正当に評価され、収入という形で返ってくる点は仕事へのモチベーションに繋がりやすいのではないでしょうか。
好きなことを仕事にできる満足感がある
自営業では、自分の興味があることや情熱を注げる分野を事業のテーマに選べます。
会社では組織の方針に従う必要がありますが、自営業なら自分の「好き」を追求し、商品やサービスとして提供することが可能です。
自分の好きなことを仕事にできると、日々の業務に対するモチベーションが維持され、任されている仕事にもやりがいや充実感を感じられるでしょう。
顧客から直接感謝の言葉をもらう機会もあり、社会に貢献しているという実感を得やすいのも自営業ならではの満足感に繋がるのではないでしょうか。
定年を気にせず長く働き続けられる
大半の企業では定年制度が設けられていますが、自営業には定年がありません。
ゆえに、自分の意欲と健康が続く限り、年齢に関係なく仕事を続けることが可能です。
長年培ってきたスキルや経験、実績、人脈を活かして生涯現役として社会と関わり続けることができます。
むしろ、年齢を重ねることで専門性が得られ、より顧客からの信頼が厚くなるような業種も珍しくありません。
人生100年時代において、自分のペースで働き続けられるという選択肢は将来のキャリアプランを考える上で利点しかないと言っても過言ではありません。
自営業を始める際に覚悟すべきデメリット

ここでは、自営業を始める際に覚悟すべきデメリットについて見ていきましょう。
収入が不安定になりやすい
自営業のデメリットとしては、収入が不安定であることが挙げられます。
会社員のように毎月決まった日に固定給が振り込まれるわけではなく、事業の売上や取引先の状況によって収入は変動するのが一般的です。
開業当初は顧客が限られ、収入がゼロの月が続く可能性も十分に考えられるでしょう。
また、病気や怪我で働けなくなれば、収入が一気に途絶えてしまうこともあるのではないでしょうか。
常に先の見えない収入の不安と隣り合わせというのは、なかなかのストレスです。
そうした背景から、この記事を書いている筆者も安定した生活を維持するために継続的な営業努力と資金管理を欠かさないようにしています。
会社員より社会的信用を得にくい場合がある
自営業者は収入が不安定なだけに、会社員に比べて社会的信用を得にくいです。
具体的には、金融機関での住宅ローンや事業資金の融資審査、賃貸物件の入居審査、クレジットカードの新規作成などが、会社員よりも厳しくなるケースが少なくありません。
上記の審査では、過去数年分の確定申告書を通じて事業の安定性や収益性が評価されます。
事業が軌道に乗るまでは、社会的な信用の面で不便を感じる場面があることを理解しておく必要があるでしょう。
税金や年金の手続きはすべて自分で行う必要がある
会社員の場合、所得税の源泉徴収や年末調整、社会保険料の納付などは会社が代行してくれるものの、自営業になると手続きのすべてを自分自身で行わなければなりません。
毎年2月から3月にかけて行う確定申告はもちろんのこと、国民健康保険や国民年金の加入手続きと保険料の納付も自己責任となります。
税金や社会保障に関する知識を身につけ、帳簿付けや各種手続きを期限内に正確に行うことも必要です。
上記の事務作業を怠ると追徴課税などのペナルティを受ける可能性もあるからこそ、負担に感じる人も珍しくありません。
経理や事務作業の負担が増える
自営業者は、商品開発や営業活動といった本来の事業活動に加え、経理や事務作業もすべて自分でこなすことが必要です。
日々の売上や経費の記帳、請求書や領収書の発行・管理、契約書の作成など、事業運営に付随するバックオフィス業務は多岐にわたります。
これらは売上には直接結びつかないものの、事業を継続していく上で欠かせない業務です。
一方、本業が忙しくなるほど、それぞれの事務作業が負担となることもあります。
ゆえに、効率化のために会計ソフトを導入したり、税理士などの専門家に一部を委託したりすることも検討する必要が出てくるのではないでしょうか。
自営業を始めてから後悔しないための注意点
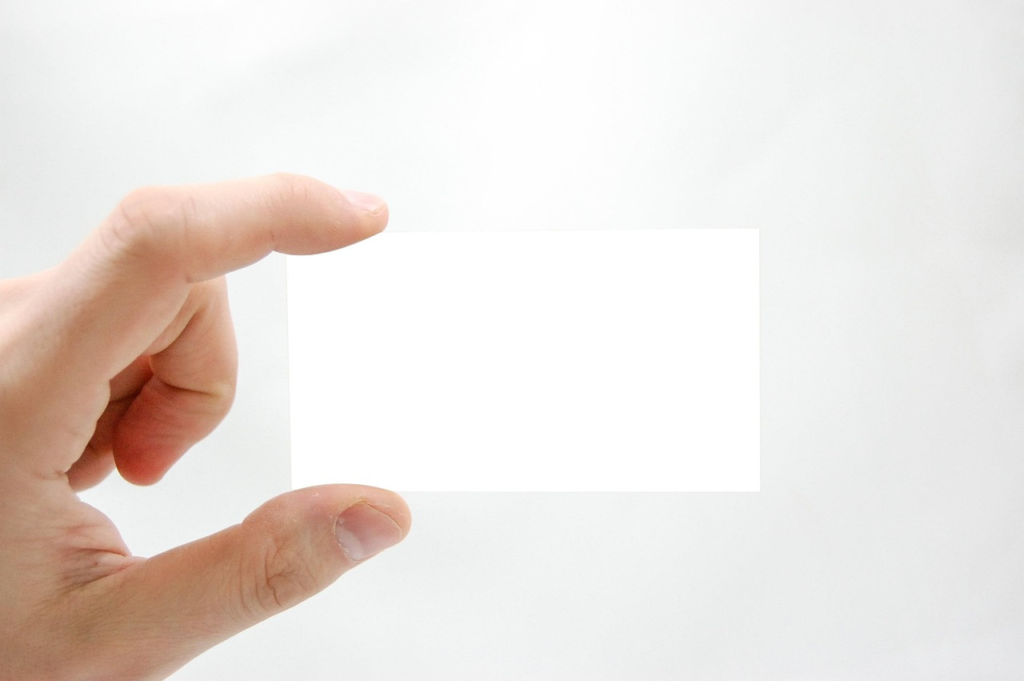
最後に、自営業を始めてから後悔しないための注意点について見ていきましょう。
事業が軌道に乗るまでの生活費を確保しておく
自営業を始めてすぐに安定した収入が得られるとは限りません。
事業が軌道に乗り、毎月十分な利益が出るまでには、数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。
この間の生活を支えるため、事業を運営するための開業資金や運転資金とは別に、それぞれ個人の生活費を必ず確保しておきましょう。
目安としては、半年から1年分の生活費を貯蓄として用意しておくのが理想です。
資金的な余裕は精神的な安定につながり、目先の売上に一喜一憂することなく、腰を据えて事業に取り組むための基盤となります。
働きすぎによる健康管理を徹底する
自営業は労働時間に制約がなく、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちなため、長時間労働に陥りやすい傾向があります。
一方、事業主自身が働けなくなってしまうと収入が完全に途絶える他、会社員のように有給休暇や傷病手当金といったセーフティーネットもないので、自営業者にとっては健康が最も重要な資本となるのです。
だからこそ、意識的に休日を設け、十分な睡眠を取り、定期的に健康診断を受けるなど、自分自身で健康管理を徹底することが事業を継続するための鍵となるでしょう。
会社員のうちにクレジットカードやローンを契約しておく
自営業者は、収入が不安定と見なされ、社会的信用度が会社員より低いと判断されることがあるため、独立直後はクレジットカードの新規作成や自動車ローン、住宅ローンといった各種ローンの審査に通りにくくなる可能性があります。
もし将来的に大きな買い物や契約を考えているのであれば、安定した収入がある会社員のうちに済ませておいてください。
また、事業で使用する可能性のあるクレジットカードも、個人用とは別に作っておくと経費管理が楽になるので、信用があるうちに必要な契約は済ませておくべきです。
まずは何が必要なのか、一度精査してみてはいかがでしょうか。
まとめ

自営業を始めるには、事業内容の決定から事業計画の作成、資金準備、必要な届出まで、計画的にステップを踏んでいくことが重要です。
自由な働き方や収入アップの可能性といった魅力的なメリットがある一方で、収入の不安定さや自己責任の増大といったデメリットも存在します。
自営業を始めるなら両側面を深く理解し、事業が軌道に乗るまでの生活費の確保や健康管理など、起こりうるリスクへの備えを万全にしておいてください。
まずは本記事で解説した手順と注意点を参考に、着実な一歩を踏み出しましょう。