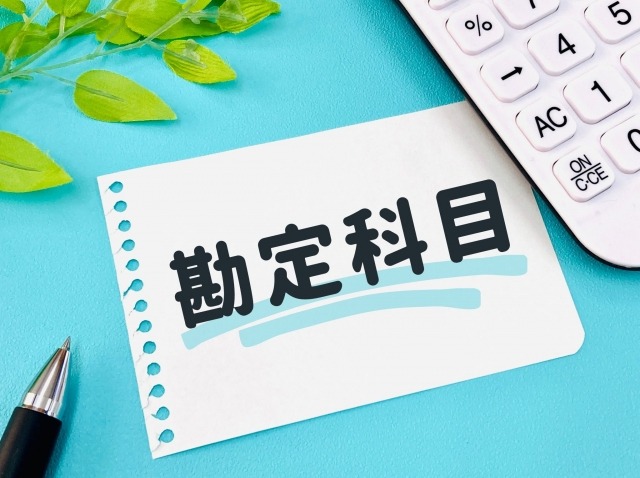会社に所属せず、自力で事業を営む「独立」は会社員にとって魅力的な選択肢の一つです。
一方、独立の意味や具体的な方法、成功の秘訣を理解している人は珍しいかもしれません。
そこで、この記事では独立して自分らしいキャリアを築くために必要な技術や知識、メリット・デメリット、仕事の選び方について網羅的に解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶独立起業/開業に失敗しないために気をつけるポイントとは?
▶自営業の始め方|起業するには?必要な準備と手順を解説
▶まずはここから!小さく始める初心者向けビジネス術

INDEX
「独立」の基本的な意味とは?類似語との違いを解説

「独立」は、組織に頼らず自らの力で生計を立てるという意味合いが含まれます。
会社を辞めてフリーランスになる、個人で事業を始める、自ら組織を設立するなど、その形態は実に様々です。
この独立の形をより具体的に理解するためには、「起業」や「開業」といった類似語との意味の違いを知っておくと良いでしょう。
それぞれの言葉が指すニュアンスを把握することで、自身の目指す方向性がより明確になるのではないでしょうか。
「起業」との意味の違い
「起業」とは、文字通り「事業を興すこと」を指し、特に新しいビジネスモデルやサービスを創出するニュアンスが強い言葉です。
一般的に、個人事業主として活動を始めるよりも、法人格を持つ企業を設立するケースで使われる傾向にあります。
一方「独立」はより広義な概念で、組織から離れて自力で事業を行うこと全般を指します。
フリーランスとして個人で活動する場合も独立に含まれるなど、すべての独立が起業に当てはまるわけではありません。
起業は、独立の一つの形態であり、事業の新規性や成長性を重視する場合に用いられる言葉と理解しておくと良いです。
「開業」との意味の違い
「開業」は、新たに事業を始める点では「起業」と似ていますが、より具体的な事業の開始を指すのに使われる言葉です。
中でも、弁護士や税理士、医師などが事務所を構えたり、飲食店や美容室といった物理的なお店を開いたりする場合によく用いられます。
個人事業主として活動を開始する際に行政機関へ提出する「開業届」があるように、事業のスタートを公に示す意味合いも含まれた言葉と言えるでしょう。
具体的には「独立」という枠組みの中で、具体的な事業をスタートさせる行為が「開業」に当たると言えます。
個人で事業を始める時には、これらの開業という手続きが最初のステップとなることがほとんどです。
まずはそれぞれの言葉の意味を理解し、自分が思い描く理想のキャリアを築いてみてはいかがでしょうか。
会社員から独立する4つのメリット

ここからは、会社員が独立する4つのメリットについて見ていきましょう。
成果次第で収入の上限なく稼げる可能性がある
会社員の場合、給与テーブルや評価制度によって収入の上限がある程度決まっていますが、独立すれば自身の成果が直接収入に反映されます。
提供するサービスの価値を高めたり、多くの顧客を獲得したりすることで、収入を青天井に伸ばせる可能性があるのは大きな魅力です。
もちろん、事業が軌道に乗るまでは不安定な時期もありますが、自分の努力次第でお金を稼げるという事実は、仕事に対するモチベーションアップに繋がるでしょう。
会社員時代には得られなかった経済的リターンを目指せる点は、独立の醍醐味の一つと言えるのではないでしょうか。
働く時間や場所を自由に決められる
独立すると、会社員のようにオフィスや勤務時間に縛られることがなくなります。
例えば、フリーランスのような働き方では、いつ・どこで仕事をするかを自分の裁量で決められるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
朝型の人は午前から仕事を開始し、午後は趣味の時間に充てるのも不可能ではありません。
また、場所に捉われない職種であれば、自宅やカフェ、あるいは旅先で仕事をすることも夢ではありません。
夜型の人も、通勤に追われることなく無理なく働くことが可能です。
育児や介護など、家庭の事情に合わせて仕事量を調整しやすい点も魅力と言えます。
職場の人間関係によるストレスが軽減される
会社組織で働く上で、上司や同僚との人間関係に悩む人は珍しくありません。
独立すれば、仕事相手を自分で選べるようになることで、こうした組織特有のしがらみから解放され、人間関係のストレスが大幅に軽減される可能性があります。
もちろん、顧客や取引先とのコミュニケーションは不可欠ですが、相性の悪い相手や理不尽な要求をする相手とは距離を置くという選択も可能です。
それぞれ自分のペースで仕事を進め、関わる人を選べる環境は、精神的な安定と肉体的なパフォーマンスの向上にも繋がるかもしれません。
自分が本当にやりたい仕事に集中できる
会社では、組織の一員として与えられた役割をこなすことが求められ、必ずしも自分の興味や情熱がある分野の仕事ばかりを担当できるわけではありません。
独立のきっかけとして、自身の好きなことを追求したいという思いが挙げられます。
独立すれば、事業の方向性から仕事内容まで、すべて自分で決定可能です。
結果的に、本当にやりたい仕事に時間とエネルギーを集中することが可能になります。
自身の情熱を注げる分野で専門性を獲得していくことは、今後のやりがいと満足感をもたらし、事業を成功させるための強力な原動力となるはずです。
会社員から独立する3つのデメリット

ここでは、会社員から独立する3つのデメリットについて見ていきましょう。
収入が不安定になるリスクがある
独立後に気になることといえば、やはり収入が不安定になるリスクです。
会社員のように毎月決まった日に固定給が支払われる保証はなく、仕事の受注状況や景気の動向によって収入は変動します。
案件が途切れれば、収入がゼロになる可能性も否定できません。
筆者も一時的に収入がゼロになったこともありました。
ゆえに、独立当初は会社員時代よりも収入が減ることを覚悟しておく必要があります。
安定した事業収益が得られるようになるまでの生活費の目安を立て、半年から1年分程度の生活費と事業の運転資金を準備しておくなど、金銭的な備えが必須です。
事業に関するすべての責任を一人で負う必要がある
会社員時代はトラブルやミスが多少発生しても、最終的には会社が責任を負ってくれます。
しかし、独立した後は事業に関するすべての責任を自分一人で負わなければなりません。
営業、実務、経理、法務といった本業以外のあらゆる業務を自身で管理し、問題が発生した際には自ら解決する必要があるわけです。
独立では事業に失敗した場合のリスクも、すべて受け入れる覚悟が必要。
このプレッシャーは想像以上に凄まじく、人によってはそのストレスで体調を崩すことも珍しくありません。
社会的な信用を得にくくなる場合がある
会社の看板がなくなることで、社会的な信用を得にくくなる場面があります。
例えば、独立直後は実績が乏しく、金融機関からの融資やクレジットカードの新規作成、住宅や自動車のローン審査、賃貸物件の契約が難しくなりがちです。
これは、収入の不安定さから返済能力を疑問視されやすいためです。
そのため、まずは事業を継続して安定した収益実績を積み上げ、徐々に社会的な信用を獲得する必要があります。
【タイプ別】独立して成功しやすい仕事の選び方とおすすめの職種

次に、独立して成功しやすい仕事の選び方とおすすめの職種について見ていきましょう。
未経験からでも挑戦しやすい仕事の例
特別な専門スキルや多額の初期投資がなくても、未経験から独立を目指せる仕事は数多く存在します。
例えば、Webライターやブログ運営、SNS運用代行、動画編集などは、パソコン一つあれば始められる代表例です。
上記の仕事は、初期費用が0円で済むこともあり、リスクを抑えてスタートできます。
また、ネット通販の運営代行や軽貨物ドライバーなども比較的参入障壁が低い職種です。
一方、始めやすい分、競合もいるからこそ、継続的にスキルを磨き、他の人との差別化を図る努力が求められるでしょう。
スキルや専門知識を活かせる仕事の例
会社員時代に培ったスキルや専門知識は、独立における強力な武器となります。
例えば、ITエンジニアやWebデザイナー、マーケターといった職種は即戦力として比較的高単価の案件を獲得しやすいのではないでしょうか。
また、法人向けの営業経験が豊富であれば、営業代行やコンサルタントとして独立する道も考えられます。
公認会計士や税理士、弁護士などの士業資格を持っている場合、専門性を活かして事務所を設立することも可能です。
まずはこれまでのキャリアを棚卸しし、その力を最大限に活かせる分野を選ぶことが、スムーズな独立成功への近道です。
店舗や事務所を構えて開業する仕事の例
物理的な拠点となる店舗や事務所を構えて独立するスタイルもあります。
飲食店やカフェ、美容室、学習塾、整体院などがその代表例です。
このタイプの独立は、地域に根ざしたビジネスを展開できるという魅力があります。
顧客と直接顔を合わせることで、信頼関係を築きやすく、リピーターを獲得しやすいのが特徴です。
物件取得費や内装工事費、設備投資など多額の初期費用が必要となる点は気を付けたいものの、入念な資金計画と事業計画があれば成功も夢ではありません。
一方で、立地選定が事業の成否を左右するからこそ、事前の市場調査が必須です。
もし絶対に失敗したくないということであれば、具体的な情報の収集と戦略の立案が必要となります。
会社からの独立に向いている人の3つの特徴
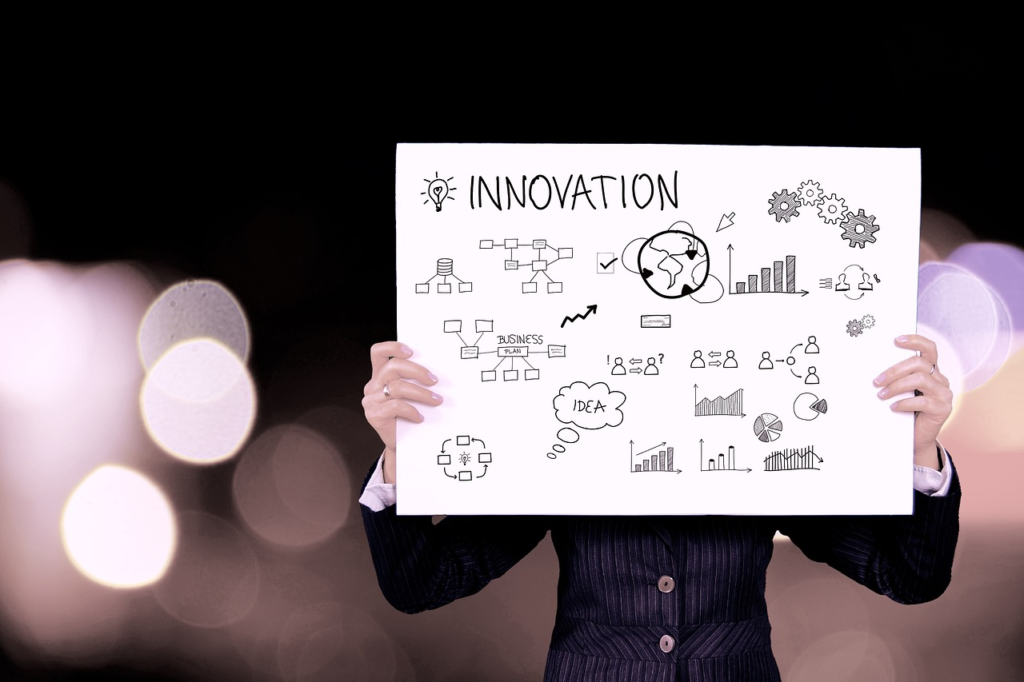
ここからは、会社からの独立に向いている人の3つの特徴について見ていきましょう。
自ら課題を見つけて主体的に行動できる人
独立すると、会社員時代のように上司から仕事の指示を与えられることはありません。
自ら市場のニーズを察知し、解決すべき課題を見つけ出し、ビジネスチャンスに変えていく主体性が不可欠です。
例えば、サービスの改善点を発見してすぐに行動に移したり、新しい営業先を自ら開拓したりするなど、常に能動的に動く姿勢が求められます。
時間の使い方や用途も含め、誰かに管理されるのではなく、自分で目標を設定し、達成に向けて計画的に行動できる人は、独立に向いていると言えるでしょう。
自己管理能力が高く、責任感が強い人
自由な働き方ができる分、独立後はすべてを自分で管理しなければなりません。
日々のタスク管理やスケジュール調整はもちろん、金銭管理や体調管理もすべて自己責任。
とりわけ独立前は、会社が管理してくれていた税金や社会保険料の支払いも自分で行う必要が出てくるのではないでしょうか。
ゆえに、誘惑に負けず、やるべきことを着実にこなす自己規律と一度引き受けた仕事は最後までやり遂げる責任感がなければ、顧客からの信頼を得ることは不可能です。
まさに自己管理能力は、事業を継続させるための基盤となります。
新しい知識やスキルの学習意欲が高い人
ビジネスの世界は常に変化しており、昨日までの常識が今日には通用しなくなることも珍しくありません。
例えば、専門分野の最新情報はもちろんマーケティングやIT、経理、法務といった関連分野の技術や知識も積極的に学び続ける意欲を忘れてはなりません。
会社員時代のように研修制度が用意されているわけではないからこそ、自らセミナーに参加したり、書籍を読んだりして能動的にスキルをアップデートしていく姿勢が求められます。
上記のように独立前に学習する習慣を身につけることは、将来的にも役立つはずです。
会社を辞めて独立するまでに必要な準備と手順

ここでは、会社を辞めて独立するまでに必要な準備と手順について見ていきましょう。
STEP1:事業内容を具体化し、事業計画書を作成する
まずは、漠然としたアイデアを具体的な事業計画に落とし込むことから始めます。
「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを明確にし、ターゲット顧客、市場規模、競合との差別化、収益モデルなどを詳細に検討するのがおすすめです。
これらの内容を事業計画書として文書化することで、それぞれの計画が頭の中で整理され、事業の実現可能性や課題が客観的に見えてくるでしょう。
とりわけ事業計画書は、金融機関から融資を受けるのに求められる重要な書類です。
むしろ、事業計画書なしに金融機関を説得するのは不可能と言えます。
もしどのように事業計画書を作成すれば良いかわからない場合は、日本政策金融公庫など国が提供しているテンプレートを参考に作成すると良いのではないでしょうか。
STEP2:必要な資金を計算し、調達方法を検討する
事業計画が固まったら、独立に必要な資金を具体的に計算します。
資金は、店舗や事務所の契約金、設備購入費などの「設備資金」と、事業が軌道に乗るまでの運転資金や自身の生活費を含む「運転資金」に大別されます。
運転資金は最低でも半年分は確保しておくのが理想です。
資金の調達方法としては、自己資金が基本ですが、不足分は日本政策金融公庫からの融資、国や市、地方自治体が提供する補助金・助成金の活用も検討すべきです。
上記の方法から複数の方法を組み合わせれば、無理のない資金計画を立てられるでしょう。
STEP3:家族の理解を得て、独立のタイミングを見極める
独立は、自分だけでなく家族の生活にも影響を及ぼします。
配偶者や子供がいる場合、収入が不安定になるリスクや、事業に多くの時間を費やすことになる可能性について事前にしっかりと話し合い、理解と協力を得ておくことが不可欠です。
家族という最も身近な応援団は、事業が軌道に乗るまでの困難な時期の精神的な支えです。
また、会社の繁忙期を避け、後任への引き継ぎを十分に行えるよう、退職のタイミングも慎重に見極める必要があります。
後の仕事のことを考えると、円満に退職することも独立する上で欠かせません。
STEP4:開業届の提出など、必要な行政手続きを進める
退職日が決まり、独立の準備が整ったら、必要な行政手続きを進めます。
個人事業主として独立して活動を始める場合、事業を開始してから1か月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出するのが一般的です。
同時に、最大65万円の所得控除が受けられるなどの節税効果が見込める「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておくと良いでしょう。
また、飲食店や古物商など、事業内容によっては保健所や警察署からの許認可が必要な場合もあるからこそ、事前に確認しておくと安心ではないでしょうか。
独立で失敗しないために押さえておきたい注意点

最後に、独立で失敗しないために押さえておきたい注意点について見ていきましょう。
まずは副業やスモールビジネスから始めてリスクを抑える
いきなり会社を辞めて退路を断つのではなく、まずは副業として小さなビジネスを始めてみるのが賢明な方法です。
社会人として安定した収入を得ながら事業を試すことで、そのビジネスに将来性があるのか、自分自身に適性があるのかをリスク回避しながら見極めることができます。
副業で得た顧客や実績は、本格的に独立した際の大きなアドバンテージとなりますし、稼いだお金を独立資金に充てることも可能です。
うまくいかなかった場合でも、本業があるため生活に困ることはなく、精神的な余裕を持って挑戦できるのが最大の利点と言えます。
会社員時代から人脈を広げておく
独立後、事業を軌道に乗せる上で最も重要になる資産の一つが「人脈」です。
顧客の紹介、有益な情報交換、困ったときの相談相手など、人との繋がりがビジネスを助けてくれる場面は少なくありません。
会社に所属している立場は、社外の人と接する機会も多く、信用を得やすいです。
この利点を活かし、会社員時代から意識的に異業種交流会やセミナーに参加するなどして、社外のネットワークを積極的に確保しておくことをおすすめします。
将来の顧客やビジネスパートナーになり得る人との関係を築いておくことは、その後の貴重な財産となります。
円満退職を心がけ、前の職場との良好な関係を保つ
退職時に揉めると、業界内で悪い評判が拡散される可能性があります。
そのため、独立を伝える場合は、できるだけ早い段階で直属の上司に相談し、就業規則に従って手続きを進めるのが理想です。
業務の引き継ぎは、後任者が困らないように丁寧に行うのが社会人としてのマナー。
前の職場と良好な関係を保つことの意味は、単に気持ち良く辞めるというだけでなく、将来的なビジネスチャンスに繋がる可能性を秘めているからです。
実際に、前の職場が独立後の最初の顧客になったり、業務委託先になったりすることもあります。
まとめ

独立とは、単に会社を辞めることではなく、自らの力で事業を営み、生計を立てる生き方そのものを意味する言葉です。
一見すると、独立は自由に働ける素晴らしい選択肢のように思えます。
一方、こうした働き方は収入や働き方の自由といった魅力的な側面がある反面、収入の不安定さや全責任を負う厳しさも伴います。
ゆえに、周到な事業計画、十分な資金準備、そして家族の理解という3つの基盤を固めることが必要となるはずです。
まずは本記事で解説した手順や注意点を参考に、現実的な視点を持ちながら、独立への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
何よりもまずは、とにかくやってみるのが良いでしょう。