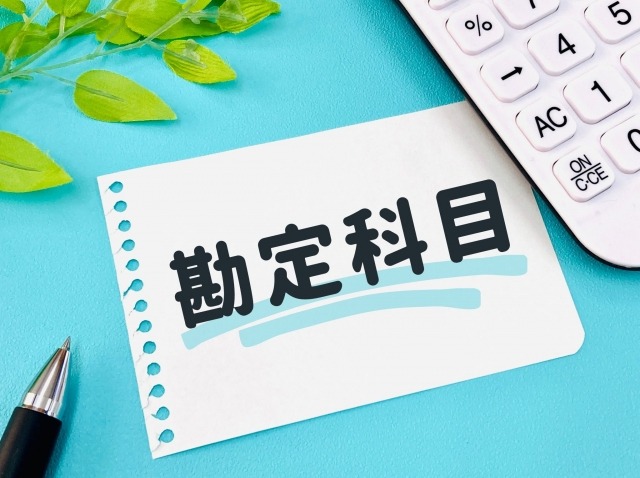支払調書の提出義務は、源泉徴収義務のある事業者が特定の報酬や料金を支払った場合に生じるのが一般的です。
税務署へ提出が必要となる支払いの範囲は法律で細かく定められており、対象となる支払いか、また支払金額が基準を超えているかを確認しなければなりません。
従業員への給与支払いは支払調書ではなく源泉徴収票の提出対象となるなど、混同しやすい点も存在するため、正確な知識が求められるでしょう。
そこで、この記事では支払調書の提出義務について詳しく解説します。

INDEX
支払調書とは?税務署に提出する目的を解説

支払調書とは、法定調書の一種であり、特定の支払いを行った事業者が、その支払いの明細を記載して税務署に提出する書類です。
税務署は、提出された支払調書の情報をもとに、支払いを受けた個人の所得を正確に把握し、適正な申告が行われているかを確認します。
これにより、税の申告漏れや脱税を防ぎ、公平な課税を実現することを目的としています。
ゆえに、支払調書の扱いについては注意が必要です。
支払調書の提出義務が発生する2つの要件
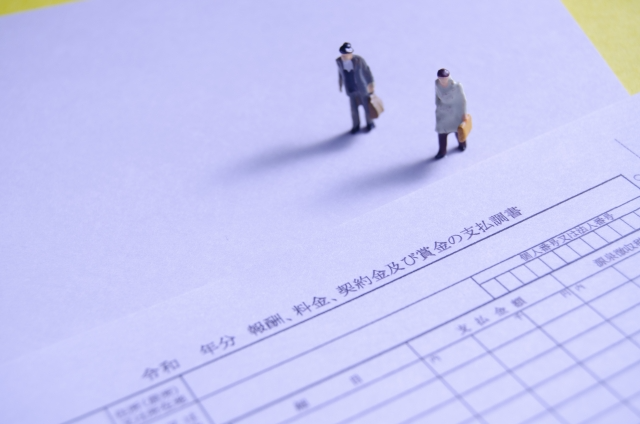
支払調書の提出義務は、すべての事業者に課されるわけではありません。
義務が発生するかどうかは、主に2つの要件を満たすか否かで判断されるのが一般的です。
具体的には、支払いを行う者が源泉徴収義務者であること、そして支払った金額が法律で定められた一定の範囲を超えていることが求められます。
上記の両方を満たした場合に、支払調書を税務署へ提出する義務を負うわけです。
ここからは、支払調書の提出義務が発生する2つの要件について詳しく解説します。
要件1:支払者が源泉徴収義務者であること
支払調書の提出義務を負うのは、源泉徴収義務者です。
源泉徴収義務者とは、従業員への給与や特定の報酬を支払う際に、所得税を天引き(源泉徴収)して国に納付する義務がある者を指します。
会社などの法人は設立されると自動的に源泉徴収義務者となります。
また、従業員を雇用している個人事業主も同様に源泉徴収義務者です。
一方、2人以下の家事使用人のみに給与を支払う個人は、源泉徴収の義務がありません。
そのため、このような個人は弁護士などに報酬を支払っても支払調書の提出義務は生じません。
要件2:支払金額が一定の範囲を超えていること
支払者が源泉徴収義務者であっても、支払った金額が一定の基準に満たない場合は、支払調書の提出義務はありません。
この基準となる金額は、支払いの内容によって異なります。
例えば、弁護士や税理士への報酬、作家への原稿料などでは、同一の相手に対する年間の支払金額の合計が5万円を超える場合に提出が必要です。
一方で、不動産の使用料や斡旋手数料の場合は、年間の支払金額の合計が15万円を超える場合に提出義務が生じます。
そのため、支払いの種類ごとに定められた金額を確認することが重要です。
【種類別】支払調書の提出が必要になる具体的なケース

支払調書の提出義務は所得税法で定められた特定の報酬料金の支払いに対して発生します。
具体的には、弁護士や税理士といった士業への報酬、作家への原稿料やイラストレーターへの画料、講演料、その他(不動産の家賃や地代、売買の斡旋手数料)が対象です。
これらの支払いを源泉徴収義務者が行い、かつ年間の支払額が規定の金額を超える場合に税務署への提出が必要となるわけです。
ここでは、支払調書の提出が必要になる具体的なケースについて詳しく解説します。
弁護士や税理士などへの報酬・料金
弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士などの特定の資格を持つ専門家に対して支払う報酬や料金は、支払調書の提出対象となります。
提出が必要となるのは、同一人に対するその年中の支払金額の合計が5万円を超える場合です。
この報酬には、訴訟に関する着手金や成功報酬、顧問料などが含まれます。
また、謝礼、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものであっても、実質的に報酬と同じ性質を持つ場合は合算して判断する必要があるので、注意が必要です。
なお、源泉徴収の対象となるそれらの報酬を支払った場合は、支払調書の作成と提出を忘れないようにしなければなりません。
作家やイラストレーターへの原稿料・画料
作家やライターへの原稿料、画家やイラストレーターへの画料、写真家への報酬、デザイナーへのデザイン料なども、支払調書の提出対象です。
これも、同一の個人に対するその年中の支払金額の合計が5万円を超える場合に提出義務が生じます。
一方、報酬の支払先が法人の場合は源泉徴収の対象とならず、支払調書の提出も不要。
あくまでも、支払先が個人の場合に限られます。
懸賞応募作品の入選者などへ支払う賞金についても、一人に対して年間5万円を超える場合は支払調書の提出が必要です。
講演料やコンパニオンへの謝礼
大学教授や評論家などに支払う講演料や、通訳・翻訳の料金も支払調書の提出対象です。
これにはモデルや外交員、プロ野球選手、プロサッカー選手へ支払う報酬も含まれます。
また、宴会等において接待を行うコンパニオンやホステスに支払う料金も対象です。
上記のような謝礼に関する報酬や料金は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が5万円を超える場合に提出義務が発生します。
なお、非居住者に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる人的役務の提供などの対価を支払う場合も、支払調書の提出が求められることが珍しくありません。
不動産の使用料(家賃や地代など)
不動産の使用料等の支払調書の提出も義務付けられています。
対象となるのは、法人および不動産業を営む個人事業主が、個人や法人(不動産業者を除く)に対して土地や建物などの不動産の使用料、例えば家賃や地代を支払った場合です。
上記の他、権利金・礼金・更新料なども含まれます。
この不動産使用料に関する支払調書は、同一人に対するその年中の支払総額が15万円を超える場合に提出しなければなりません。
一方、法人が借りている社宅の家賃を従業員に代わって貸主に支払っているようなケースは、支払調書の提出対象外です。
不動産の売買や貸付けの斡旋手数料
不動産の売買や貸付けの仲介を依頼し、対価として支払う斡旋手数料も支払調書の提出対象です。
主に「不動産の売買又は貸付けの斡旋手数料の支払調書」という名称の書類を提出します。
この義務を負うのは、法人および不動産業者である個人事業主です。
提出が必要となる基準は、同一の相手方に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超える場合。
なお、不動産の使用料等の支払調書とは様式が違い、提出基準額も変わるため、混同しないよう注意が必要な他、不動産取引に関わる支払いは、種類に応じて適切な調書を作成する必要があります。
給与の支払いは支払調書ではなく源泉徴収票を提出する
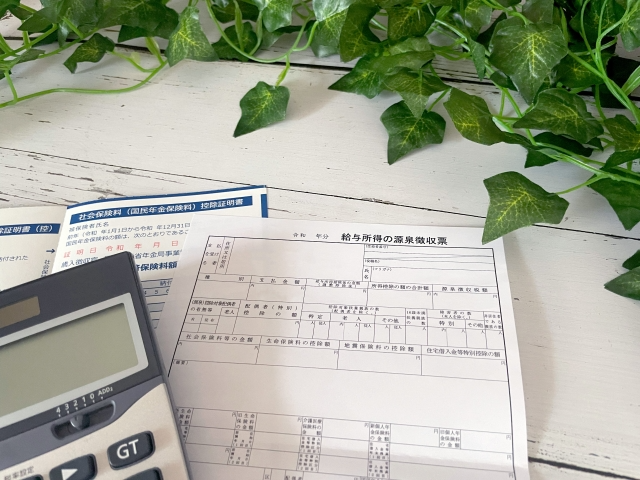
従業員へ支払う給与や賞与は、支払調書の提出対象ではありません。
一方で「給与所得の源泉徴収票」を作成し、税務署へ提出する義務があります。
支払調書と源泉徴収票は、どちらも法定調書ですが、対象となる支払いの内容が明確に区別されているため、注意が必要です。
同様に従業員へ退職金を支払った場合は「退職所得の源泉徴収票」の提出が一般的です。
報酬と給与を混同し、誤った書類を提出しないよう注意が必要となります。
支払調書の提出先と提出期限

作成した支払調書は、定められた提出先へ期限内に提出しなければなりません。
提出先は、原則として支払者の事業所の所在地を管轄する税務署です。
提出期限は、支払いが行われた年の翌年1月31日までと定められています。
(当期限は給与所得の源泉徴収票など他の法定調書とも共通)
具体的な様式や記載方法は、国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認すべきです。
ここからは、支払調書の提出先と提出期限について詳しく解説します。
提出先は所轄の税務署
支払調書の提出先は支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を管轄する税務署です。
本社で経理業務を一元管理している場合は、本社の所在地を管轄する税務署にすべての支払調書を提出します。
一方、支店や営業所がそれぞれ独立して支払いに関する事務を行っている場合は、各支店・営業所の所在地を管轄する税務署へ個別に提出することになります。
ゆえに、自社の経理体制を確認し、どの税務署が提出先となるのかを事前に把握しておくことが重要です。
なお、誤った税務署へ提出すると手続きが遅延する可能性があるため、ご注意ください。
提出期限は支払った年の翌年1月31日
支払調書の提出期限は、原則として、支払いを行った年の翌年の1月31日です。
例えば、2024年1月1日から12月31日までの間に支払った報酬に関する支払調書は、2025年1月31日までに税務署へ提出する必要があります。
この期限が土日祝日に当たる場合は、その翌開庁日が期限。
なお、1月は年末調整関連の書類提出も重なり、税務署の窓口が混雑しやすい時期となるので、書類の作成や準備は早めに進め、余裕を持って提出手続きを完了させましょう。
支払調書の提出方法【e-Tax・郵送・窓口】

支払調書の提出方法には主に3つの方法があります。
- 国税電子申告・納税システムe-Taxを利用したオンラインでの電子申告
- 作成した書類を信書として郵送する方法
- 管轄税務署の窓口へ直接持参して提出する方法
e-Taxは24時間いつでも提出可能で、事務効率化に最適です。
郵送や窓口提出は電子申告の環境がない場合に選択できる方法と言えるでしょう。
まずは、自社の状況に応じて最も適した方法を選んでみてはいかがでしょうか。
支払調書の提出義務が免除される条件

支払調書の提出義務は、すべての支払いに対して発生するわけではありません。
まず、支払金額が種類ごとに定められた基準額に満たない場合は、提出が免除されます。
例えば、弁護士への報酬が年間5万円以下であれば提出は不要です。
また、支払者が源泉徴収義務者でない場合も提出義務はありません。
なお、所得税法で提出が義務付けられている報酬等以外の支払い、例えば生命保険契約に基づく保険金や一時金などの支払調書は、相続税法など別の法律に基づくものであり、提出要件は別です。
ゆえに、必要に応じて確認が必要となります。
支払調書を提出しなかった場合の罰則規定

支払調書の提出は所得税法で定められた義務です。
正当な理由がなく提出期限までに提出しなかった場合や、虚偽の情報を記載した支払調書を提出した場合には、罰則が適用される可能性があります。
この違反に対する罰則は、所得税法第242条の五において「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
意図的な不提出や虚偽記載はもちろん、単純な提出忘れであっても、税務調査などで指摘される場合があるからこそ、それぞれ法令を遵守し、正確な事務処理を徹底することが必須です。
支払調書を作成・提出する際の注意点

支払調書を適切に作成し提出するためには、いくつかの注意点を理解しておくべきです。
例えば、支払調書は税務署への提出が義務ですが、報酬の支払先である本人への交付は法律上の義務ではありません。
また、支払先が個人の場合はマイナンバーの記載が必須となるため、適切な管理が求められます。
作成した支払調書は、法定調書合計表とあわせて提出することも忘れてはならない点です。
ここでは、支払調書を作成・提出する際の注意点について詳しく解説します。
支払先への交付は法律上の義務ではない
支払調書は税務署へ提出するための書類であり、報酬の支払先である本人へ交付することは法律で義務付けられていません。
この点は、給与を受け取った本人への交付が義務である源泉徴収票とは異なります。
一方、取引先が確定申告を行う際に、支払われた金額を確認する資料として支払調書を求めることがあるなど、実務上は慣例として写しを交付するのが一般的です。
交付する際は、あくまで任意の一環であり、支払内容の通知という位置づけになります。
交付する場合も、マイナンバーを記載しないなど配慮が必要です。
支払先が個人の場合はマイナンバーの記載が必要
税務署に提出する支払調書には、支払いを受ける相手が個人の場合、その人の個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられています。
このため、報酬などを支払う際は、事前に相手方からマイナンバーを提供してもらう必要があります。
マイナンバーは特定個人情報に当たるので、収集時には利用目的を明確に伝え、取得後は紛失や漏洩がないように厳重に管理しなければなりません。
なお、税務署へ提出する書類にのみ記載し、支払先本人へ交付する写しには記載しないように注意が必要。
法定調書合計表もあわせて提出する
支払調書を税務署に提出する際は、単体で提出するのではなく、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添付する必要があります。
この合計表は、その年に提出するすべての法定調書の内容を種類別に集計し、総括するための書類です。
例えば「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出対象となる人員と支払金額の合計や、「給与所得の源泉徴収票」の合計額などを記載するのが一般的。
支払調書と法定調書合計表はセットで提出するものと認識し、忘れずに作成しなければなりません。
一定枚数以上はe-Taxでの提出が義務化されている
法定調書の提出において、電子申告が義務化される基準が設けられています。
具体的には、基準年(前々年)に提出した法定調書の種類ごとに、その枚数が100枚以上であった場合、当年の提出はe-Taxまたは光ディスク等による電子的な方法で行わなければなりません。
例えば、前々年に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を120枚提出していた場合、今年も同調書は紙媒体での提出は認められず、e-Taxなどでの提出が必須となるわけです。
この義務化の対象になるかどうかは、法定調書の種類ごとに判定されます。
まずは、自社がどの条件に当てはまるのかを確認しておくと安心です。
まとめ

支払調書の提出義務は、源泉徴収義務者が所得税法で定められた特定の報酬や料金などを規定の金額以上支払った場合に発生します。
支払調書に関しては、対象となる支払いの種類や金額の基準を正確に把握し法定調書合計表とともに翌年1月31日までに所轄の税務署へ提出することが求められます。
義務を怠ると罰則が科されることもあるため、自社が支払っている金銭が支払調書の対象となるかを確認し、適正な手続きを行うことが必要です。
具体的な手続きの方法については、あらかじめよく確認しておくと安心です。