チェーン店とは、同一のブランド名や商標を使用し、統一された経営方針のもとで多店舗展開を行う事業形態の総称です。
そして、その運営方法によって「直営店」と「フランチャイズ」の2種類に大別されます。
この違いを理解することは、独立開業や就職先を検討する上で非常に重要です。
この記事では、チェーン店とフランチャイズの違いとは何か、それぞれの仕組みやメリット・デメリットを事業者と労働者の両方の視点から詳しく解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶【フランチャイズ用語】臨店の意味と目的を説明します!
▶評判の悪いフランチャイズを見極める方法とは?悪徳案件を回避する危険察知力の向上情報
▶プレオープンとは何?目的やメリット、成功の秘訣を徹底解説

INDEX
【結論】フランチャイズはチェーン店の一種|まずは関係性を理解しよう

一般的に「チェーン店」と「フランチャイズ」は対立する言葉として捉えられがちですが、実際にはフランチャイズはチェーン店の一つの形態です。
チェーン店という大きな枠組みの中に、本部が直接運営する「直営店(レギュラーチェーン)」と、本部と契約した加盟者が運営する「フランチャイズチェーン」が存在します。
つまり、私たちが普段目にするチェーン店の多くは、直営店かフランチャイズチェーンのいずれかの方法で運営されています。
本部が直接運営する「直営店(レギュラーチェーン)」とは
直営店(レギュラーチェーン)とは、事業を展開する本部が、資本を100%投下して自ら店舗を設置し、直接運営する形態のチェーン店を指します。
店舗の土地や建物、設備などはすべて本部の資産であり、店長やスタッフも本部の正社員や契約社員として雇用されます。
そのため、人材育成や店舗運営、提供する商品・サービスの品質管理まで、すべて本部の厳格な管理下で行われるのが特徴です。
これにより、全店舗で均一なサービスレベルを維持しやすく、ブランドイメージの統一を図ることが可能になります。
利益はすべて本部に帰属し、新たな出店や事業拡大のための投資に活用されます。
個人や法人が加盟して運営する「フランチャイズチェーン」とは
フランチャイズチェーンとは、事業本部と、独立した個人または法人の加盟店が契約を結んで店舗を運営する形態です。
加盟店は、本部に加盟金やロイヤリティを支払う対価として、本部の商標やブランド名を使用する権利、確立された経営ノウハウや商品、サービスの提供を受けることができます。
経営の主体はあくまで加盟店のオーナーであり、スタッフの雇用もオーナー自身が行います。
本部からのサポートを受けられるため、未経験者でも事業を始めやすいという利点がありますが、本部の定めたルールやマニュアルに従う義務も生じます。
【一覧比較】直営店とフランチャイズの5つの仕組みの違い

直営店とフランチャイズは、同じブランドの看板を掲げていても、その内部の仕組みは大きく異なります。
事業者として独立を考える場合や、労働者として就職先を選ぶ際には、これらの違いを正確に理解しておくことが重要です。
ここでは、経営の主体、利益の仕組み、雇用の関係、運営の自由度、そして出店時の初期費用という5つの観点から、両者の違いを一覧で比較できるように具体的に解説していきます。
経営の主体は誰か?(本部かオーナーか)
最も根本的な違いは、経営の主体が誰であるかという点です。
直営店の場合、経営の主体は事業者である本部自身です。
店長は本部の従業員という位置づけであり、店舗の運営に関する最終的な意思決定権は本部にあります。
すべての店舗は本部の指揮命令系統のもとに置かれます。
一方、フランチャイズ店の経営主体は、本部と契約を結んだ加盟店のオーナーです。
オーナーは独立した事業者であり、自己の責任において店舗を経営します。
本部から経営指導は受けますが、あくまで店舗運営の責任者として、日々のオペレーションや人材管理を担うことになります。
利益の仕組みはどうなっている?(ロイヤリティの有無)
利益の仕組みにも明確な違いがあります。
直営店で得られた売上から経費を差し引いた利益は、すべて経営主体である本部のものとなります。
店長やスタッフには、その貢献度に関わらず、本部規定に基づいた給与が支払われます。
対してフランチャイズ店では、店舗の利益は原則としてすべてオーナーのものになります。
しかし、オーナーはブランドの使用権や経営ノウハウ提供の対価として、毎月本部に「ロイヤリティ」を支払う義務があります。
このロイヤリティがあるため、売上が同じでも手元に残る利益は直営店とフランチャイズで異なり、オーナーの経営手腕が収益に直結します。
スタッフは誰に雇用される?(本社採用か店舗採用か)
店舗で働くスタッフの雇用主も異なります。
直営店の場合、店長はもちろん、正社員、アルバイト、パートに至るまで、すべてのスタッフは本部が直接雇用します。
そのため、労働条件や給与体系、福利厚生は本社の規定に準じ、全店舗で統一されています。
一方、フランチャイズ店で働くスタッフは、加盟店のオーナーが雇用主となります。
採用活動から給与の支払い、労務管理まで、すべてオーナーの責任で行われます。
したがって、同じブランドの店舗であっても、オーナーの方針によって時給やシフトの柔軟性、福利厚生などの待遇が大きく異なるケースが一般的です。
店舗運営における自由度の高さ
店舗運営の自由度においても差が見られます。
直営店は、ブランドイメージとサービス品質の統一を最優先するため、本部が作成した詳細なマニュアルに沿った運営が厳格に求められます。
商品構成や価格設定、販売促進活動など、店舗独自の裁量で変更できる範囲は非常に限定的です。
これに対しフランチャイズ店は、契約の範囲内であれば、オーナーの裁量が認められる場合があります。
例えば、地域特性に合わせた独自のキャンペーンを実施したり、推奨仕入れ先以外から一部商品を仕入れたりすることが可能なケースもあります。
ただし、これも本部の方針次第であり、自由度は契約内容によって大きく左右されます。
出店時の初期費用はどちらが負担するのか
店舗を新たに出店する際の初期費用の負担者が異なります。
直営店の場合、物件の取得費用や内外装工事費、厨房機器などの設備投資、開業前の広告宣伝費など、出店にかかるすべての費用は本部が負担します。
これは本部による事業投資の一環です。
一方で、フランチャイズ店として開業する場合、これらの初期費用は原則として加盟店のオーナーが負担することになります。
具体的には、加盟金や保証金、研修費用を本部に支払うほか、店舗の建設費や設備費なども自己資金や融資によって賄う必要があります。
開業資金の有無が、どちらの形態を選択できるかを決める大きな要因の一つです。
事業者向け|フランチャイズ(FC)に加盟して開業するメリット
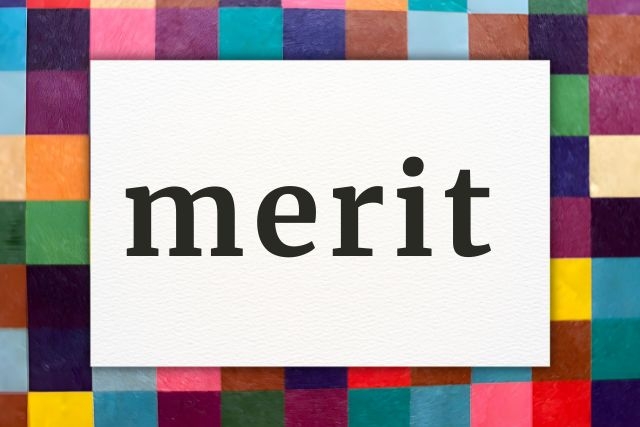
独立開業を目指す事業者にとって、フランチャイズチェーンへの加盟は非常に魅力的な選択肢となり得ます。
ゼロから事業を立ち上げる場合に比べて、成功の確率を高めるための様々な利点があるからです。
フランチャイズチェーンのメリットを最大限に活用することで、事業経験が少ない人でもスムーズに経営を軌道に乗せることが期待できます。
ここでは、事業者の視点から見たフランチャイズ加盟の主なメリットを3つのポイントに絞って解説します。
本部の知名度やブランド力を利用して集客できる
フランチャイズに加盟する最大のメリットは、本部の持つ知名度やブランド力を最初から利用できる点にあります。
既に多くの消費者に認知されている有名ブランドの看板を掲げて開業できるため、個人で一から店を始める場合と比べて、集客に関する苦労を大幅に軽減可能です。
通常、新規開業時には店の名前や存在を知ってもらうための多大な広告宣伝費と時間が必要ですが、フランチャイズならその必要がありません。
テレビCMや全国規模のキャンペーンなど、本部が行う大規模な販売促進活動の恩恵も受けられ、開業初日から安定した売上が期待できるのは大きな強みです。
経営ノウハウの提供など手厚いサポートを受けられる
長年の事業活動を通じて本部が蓄積してきた成功のための経営ノウハウを、体系的なパッケージとして提供してもらえる点も大きなメリットです。
商品開発や効率的なオペレーション、原材料の安定的な仕入れルート、効果的な広告宣伝の手法、さらにはスタッフの採用や教育方法に至るまで、事業運営に必要なあらゆる知識とスキルを学ぶことができます。
また、開業前の研修だけでなく、開業後もスーパーバイザー(SV)と呼ばれる担当者が定期的に店舗を巡回し、経営に関するアドバイスや問題解決のサポートをしてくれるため、安心して店舗運営に集中できます。
未経験の業界でもスムーズに事業を始めやすい
確立されたブランド力と手厚いサポート体制があるため、全く経験のない業界であっても比較的スムーズに事業を開始できます。
個人で独立する場合、事業計画の策定から資金調達、物件探し、内装工事、仕入れ先の開拓、許認可の申請まで、すべてを自分一人で手探りで進めなければなりません。
しかし、フランチャイズであれば、これらの複雑なプロセスについても本部が手順を指導してくれます。
成功事例に基づいたマニュアルと運営システムが完備されているため、大きな失敗をするリスクを低減させながら、短期間で事業を軌道に乗せることが可能です。
事業者向け|フランチャイズ(FC)加盟で注意したいデメリット
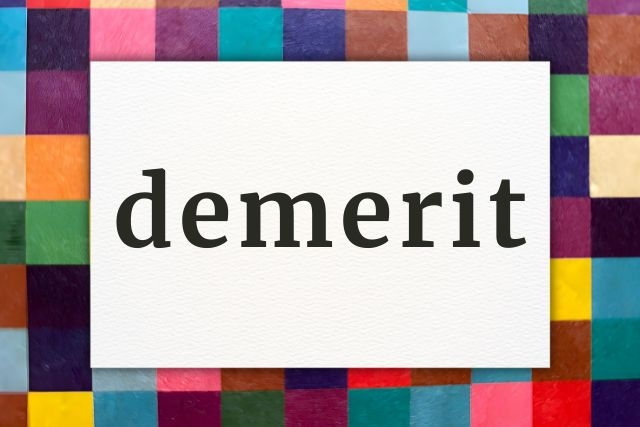
フランチャイズ加盟は多くのメリットがある一方で、事業者として独立する上で注意すべきデメリットや制約も存在します。
手厚いサポートやブランド力といった恩恵は、自由度の制限や金銭的な負担と表裏一体の関係にあります。
契約を結ぶ前にこれらのデメリットを十分に理解し、自身の事業計画や経営方針と照らし合わせて慎重に検討することが、後悔のない選択をするために不可欠です。
毎月のロイヤリティ(対価)の支払いが必要になる
フランチャイズに加盟すると、ブランド名の使用権や経営ノウハウ提供の対価として、毎月本部にロイヤリティを支払う義務が生じます。
ロイヤリティの算出方法は、売上に対して一定の割合を支払う「売上歩合方式」や、売上に関わらず毎月決まった額を支払う「固定額方式」など様々です。
この支払いは、たとえ店舗の売上が赤字であったとしても免除されることはありません。
そのため、常にロイヤリティの支払いを念頭に置いた資金計画を立てる必要があり、収益性が低い状況では経営を圧迫する大きな要因となり得ます。
契約期間やルールに縛られ経営の自由度が低い
フランチャイズ契約を締結すると、加盟店は本部が定めた運営マニュアルやルールを遵守する義務を負います。
ブランドイメージの統一性を保つため、取扱商品やサービス内容、店舗の内外装、営業時間、広告宣伝の方法など、運営の細部にわたって制約が課せられます。
そのため、オーナー自身が「もっとこうしたい」という独自のアイデアや改善策を持っていても、それを自由に実行することは困難です。
また、契約期間が定められており、期間満了前に自己都合で廃業する場合には、高額な違約金が発生する可能性もあるため注意が必要です。
加盟店の評判が悪化するとブランドイメージが低下する
フランチャイズは、全加盟店で一つのブランドを共有する運命共同体です。
そのため、自店の経営努力とは無関係なところで、ブランド全体のイメージが損なわれるリスクを常に抱えています。
例えば、他の加盟店が食中毒や不適切な従業員の行動などの問題を起こし、ニュースで報道された場合を考えてみましょう。
その結果、ブランド全体の評判が悪化し、全く問題のない自店の売上まで減少してしまう可能性があります。
このように、自分たちではコントロールできない外部の要因によって、経営が大きな影響を受ける可能性がある点はデメリットと言えます。
労働者向け|直営店で働くメリット
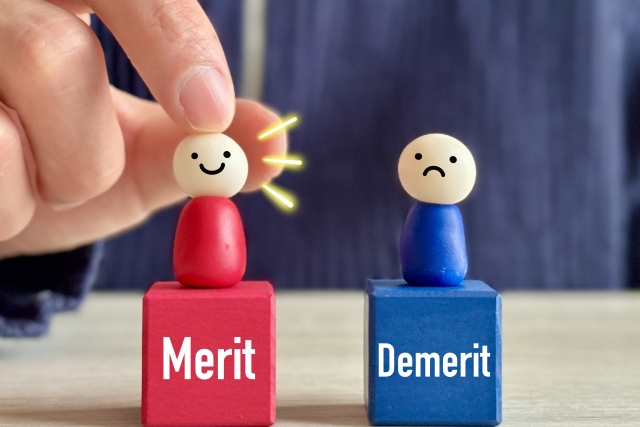
就職や転職を考えている労働者にとって、企業の直営店で働くことには多くのメリットがあります。
特に、安定した環境で長期的なキャリアを築きたいと考える人にとって、直営店は魅力的な選択肢となるでしょう。
本社の正社員として雇用されることで得られる手厚い待遇や、明確なキャリアパスは、フランチャイズ店での勤務とは異なる大きな利点です。
ここでは、労働者の視点から直営店で働くことのメリットを具体的に解説します。
本社採用のため福利厚生や研修制度が充実している
直営店で働く最大のメリットの一つは、経営母体である本社の正社員または契約社員として雇用されるため、福利厚生が充実している点です。
多くの場合、本部は大企業であるため、社会保険完備はもちろんのこと、住宅手当、家族手当、退職金制度、財形貯蓄制度などが整っています。
また、教育制度が体系化されているのも特徴です。
入社時の新人研修から始まり、階層別のスキルアップ研修、資格取得支援制度などが用意されており、未経験からでも着実に専門知識やスキルを身につけながら成長していくことが可能です。
キャリアパスが明確で店長や本部社員を目指せる
直営店での勤務は、多様なキャリアパスが描ける点も大きな魅力です。
店舗スタッフとして経験を積んだ後、実力や実績が評価されれば、店長へと昇進する道が開かれています。
さらにその先には、複数の店舗を統括するエリアマネージャーやスーパーバイザーといった管理職へのステップアップも可能です。
また、店舗での現場経験を活かして、本社の商品開発、マーケティング、人事、店舗開発といった専門部署へ異動するキャリアチェンジのチャンスもあります。
明確な評価制度とキャリアプランが用意されているため、目標を持って働くことができます。
給与や雇用形態が安定している
企業の直営店で働く場合、給与や雇用形態が安定しているというメリットがあります。
本社の給与規定に基づいて給与が支払われるため、個別の店舗の売上成績によって給与が大きく変動することは基本的にありません。
業績に応じた賞与(ボーナス)が支給されることも多く、安定した収入を見込むことができます。
また、正社員として雇用されることが多いため、長期的な雇用が保障されています。
企業の経営基盤が安定している限り、安心して働き続けることができる環境は、生活設計を立てる上で大きな安心材料となります。
労働者向け|直営店で働くデメリット

直営店での勤務は、安定性や充実した福利厚生といった多くのメリットがある反面、いくつかのデメリットも存在します。
全国規模で事業を展開する大企業ならではのルールや制約があり、それが人によっては働きにくさと感じられるかもしれません。
就職先として直営店を選択する際には、メリットだけでなく、これから解説するようなデメリットも理解した上で、自身の価値観やライフプランに合っているかを判断することが大切です。
マニュアルが厳格で店舗独自の工夫がしにくい
直営店では、全店舗で商品やサービスの品質を高いレベルで均一に保つため、非常に詳細で厳格な業務マニュアルが定められています。
接客時の言葉遣いから商品の陳列方法、清掃の手順に至るまで、あらゆる業務が標準化されており、従業員はそれに忠実に従うことが求められます。
そのため、個人のアイデアや創意工夫を店舗運営に活かしたいと考える人にとっては、裁量の余地が少なく、仕事が単調で窮屈に感じられる可能性があります。
決められたルールの中で、正確かつ効率的に業務を遂行する能力が重視される環境です。
本部の方針による転勤や店舗異動の可能性がある
直営店を全国に展開している企業の場合、本部の人事戦略の一環として、転居を伴う全国規模での転勤や、近隣店舗への異動を命じられる可能性があります。
これは、従業員のキャリアアップや人材育成、組織の活性化などを目的として行われるもので、個人の希望が常に通るとは限りません。
「地元でずっと働きたい」「家族の事情で引越しはできない」といった希望がある人にとっては、この転勤の可能性が大きなデメリットとなり得ます。
自身のライフプランと、企業の転勤に関する方針を、入社前によく確認しておく必要があります。
あなたはどっち向き?独立・就職先を選ぶ際のポイント

これまで解説してきたように、フランチャイズと直営店は、事業者と労働者の双方にとって、それぞれ異なるメリットとデメリットを持っています。
どちらの形態がより良いという絶対的な答えはなく、自身の目的や状況、価値観によって最適な選択は変わります。
ここでは、独立開業を目指す人と、就職・転職を考えている人、それぞれの立場から、どちらの働き方が向いている人なのか、選択のポイントを整理します。
【独立・開業したい人】未経験から挑戦するならフランチャイズ
もし業界未経験から独立・開業に挑戦したいのであれば、フランチャイズへの加盟が適しています。
本部の確立されたブランド力と経営ノウハウを活用できるため、事業立ち上げのリスクを大幅に低減させることが可能です。
手厚い研修や運営サポートを受けられるため、経営に自信がない人でも安心してスタートできます。
また、個人で開業するよりも金融機関からの融資を受けやすい傾向にある点も利点です。
ただし、経営の自由度が低いことや、ロイヤリティの支払い義務があることを受け入れ、本部の方針に従って事業を運営する覚悟が求められます。
【就職・転職したい人】安定したキャリアを築くなら直営店
安定した環境で着実にキャリアを積み重ねていきたいと考えるなら、直営店への就職が向いています。
本社の正社員として雇用されるため、充実した福利厚生のもとで安心して働くことができます。
給与体系や評価制度も明確で、店長やエリアマネージャー、さらには本部社員といったキャリアアップの道筋が描かれていることが多いです。
マニュアルに沿って着実に業務をこなし、組織の一員として貢献することにやりがいを感じるタイプの人に適しています。
ただし、本部の方針による転勤の可能性や、業務における裁量の少なさは受け入れる必要があります。
チェーン店とフランチャイズに関するよくある質問

ここまでチェーン店とフランチャイズの違いについて詳しく解説してきましたが、まだ具体的なイメージが掴みきれない点や、細かな疑問が残っているかもしれません。
ここでは、コンビニエンスストアの運営形態やロイヤリティの相場など、多くの方が疑問に思う点について、よくある質問の例を挙げてQ&A形式で簡潔に回答します。
コンビニは直営店ですか?それともフランチャイズですか?
結論として、コンビニの多くはフランチャイズ店ですが、一部に直営店も存在します。
店舗数の大半は、個人や法人がオーナーとして経営するフランチャイズ店です。
一方で、本社の新商品や新サービスのテスト、社員研修の場として活用するために、本部が直接運営する直営店も一定数あります。
フランチャイズの「ロイヤリティ」の相場はどのくらいですか?
ロイヤリティの相場は業種や本部の方針によって大きく異なりますが、一般的には「売上の3~10%」程度が目安とされます。
その他、毎月決まった金額を支払う「固定額方式」を採用している本部もあります。
契約前には、金額だけでなく算出方法もしっかりと確認することが重要です。
個人経営の飲食店とフランチャイズの違いは何ですか?
最大の違いは、本部との契約関係があるかどうかです。
個人経営の飲食店は、コンセプトやメニュー、価格設定などすべてを自由に決められる反面、ブランド力や経営ノウハウはゼロから築く必要があります。
一方フランチャイズの飲食店は、本部の支援を受けられる代わりに、ルールに従う必要があります。
まとめ

チェーン店とは事業形態の総称であり、その運営方法によって本部が直接手がける「直営店」と、加盟者が運営する「フランチャイズ」に分けられます。
両者は経営の主体や利益の仕組み、運営の自由度など多くの点で異なります。
例えば、あるブランドが100店舗展開している場合、その店舗数の内訳は直営店が10店舗、フランチャイズが90店舗というケースも珍しくありません。
たとえ3店舗の小規模チェーンであっても、運営形態は様々です。
独立開業を目指すならリスクを抑えやすいフランチャイズ、安定したキャリアを求めるなら直営店というように、自身の目的やライフプランに応じて最適な選択をすることが重要です。















