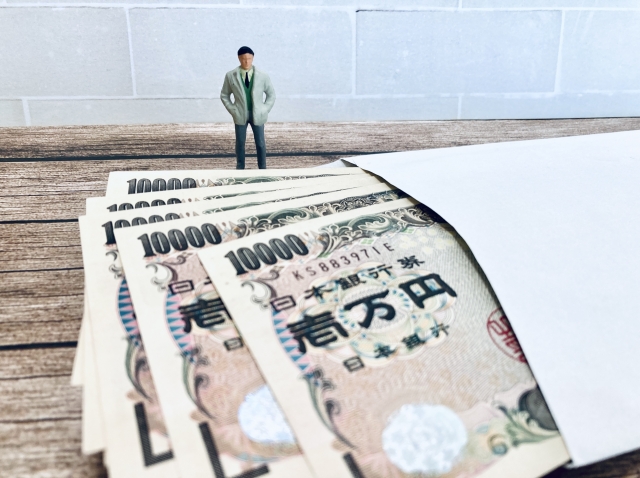自営業の年収について、その定義から平均、計算方法、そしてどうすれば年収を増やせるのかまで、体系的に理解できるように解説します。
多くの方が気になる年収とは何か、収入、手取りとの違い、平均年収の実態、そして手取りの計算方法や年収を増やすための具体的なステップについても触れていきます。
これらの情報を得ることで、自身の現状を把握し、今後の事業計画やライフプランを考える上で役立てられるでしょう。

自営業の年収とは?

自営業における年収とは、一般的に事業による「所得」を指すことが多いです。
これは、1年間の総収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
会社員の場合は給与や賞与の合計額が年収となりますが、自営業では売上から経費を差し引いた利益が、税金や社会保険料の計算の基礎となるため、この所得金額が非常に重要になります。
この違いを理解することが、自営業の収入について考える上で最初のステップとなります。
収入、所得、年収、経費の違い
自営業において、「収入」「所得」「年収」「経費」という言葉はそれぞれ異なる意味を持ちます。
- 収入:事業によって得た売上金額
⇒商品やサービスを提供してお客様から受け取った代金の総額 - 経費:事業を行う上でかかった費用
⇒仕入れ費用、家賃、光熱費、通信費、旅費交通費、広告宣伝費など
※経費は収入から差し引くことが可能 - 所得:収入から経費を差し引いた残りの金額
⇒所得が、税金や社会保険料を計算する際の基準となる
⇒「自営業の年収」とは、この所得金額を指すのが一般的
⇒会社員の年収は額面給与の合計だが、自営業の場合は総収入から経費を差し引いた所得がそれに近い考え方となる
このように、それぞれの言葉が指す内容を正しく理解することが、自営業の収入について考えるうえで重要です。
確定申告書での所得確認方法
自営業者が所得を把握するには、確定申告書を見るのが最も確実な方法です。
確定申告書には、1年間の収入や経費、最終的な所得金額が詳細に記載されています。
具体的には、確定申告書Bの第一表にある「所得金額等」の欄を確認しましょう。
ここには、事業所得として計算された金額や、その他の所得の合計金額が記載されます。
所得金額等の合計が、自営業者における年収として参照されるのが一般的です。
なお、確定申告は毎年行う必要があり、確定申告書は税金の計算だけでなく、自分の経営状況を把握するための重要な書類となります。
もし、過去の確定申告書が見当たらない場合は、税務署に問い合わせて開示請求することも可能です。
会社員の年収との比較
自営業の年収を考える際に、会社員の年収と比較することはよくあります。
ただ、両者には構造的な違いがあるため、単純な数字だけで比較することは難しいです。
会社員の場合、年収は給与や賞与といった形で支払われ、そこから所得税や住民税、社会保険料などが源泉徴収されます。
一方、自営業の場合は、売上から事業にかかった経費を差し引いた所得が基準となります。
同じ年収額面であっても、自営業者は国民健康保険や国民年金といった社会保険料を全額自分で負担する必要があり、さらに事業で使用した経費を差し引くことができるため、手元に残る金額(手取り)は千差万別です。
また、会社員には給与所得控除がありますが、自営業者にはありません。
これらの違いから、たとえ年収の額面が同じでも手取り額や税負担、社会保障の面で差が生じるため、会社員と比較する場合は単に年収の数字だけでなく、上記の要素を含めて総合的に判断することが重要です。
自営業の平均年収
ここからは、自営業の平均年収について見ていきましょう。
平均年収の実態
国税庁などの統計データを見ると、自営業者の平均年収は会社員の平均年収と比べてあまり変わらないという調査結果があります。
現に平成30年の調査では自営業が約417万円だったのに対し、会社員は約422万円でした。
ただ、これはあくまで平均値であり、自営業の場合、収入にばらつきがあるのが実情です。
フリーランスとして働いている筆者も、収入は月ごとにばらつきがあります。
中には、高い年収を得ている自営業者もいれば事業を始めたばかりで収入がない、あるいは赤字となっている人も存在するため、平均年収という数字だけで自営業全体を捉えることはできません。
平均年収が低いと感じる人もいるかもしれませんが、あくまでも色んな所得層が含まれているためにそう感じるだけであって、個々の事業の成功度合いによって何十万円も何百万円も年収が変わってくるのが自営業の特徴です。
所得階級別の分布
自営業者の所得は、特定の階級に集中しているわけではなく、幅広い分布を示しています。
国税庁の統計データによると、事業所得者の所得階級別では、300万円超から1,000万円以下の層が比較的ボリュームゾーンを形成していることが示されていますが、一方で所得が0円や低い階級の割合も珍しくないです。
これは、事業が軌道に乗るまでの期間や景気の影響を受けやすい業種など、色んな要因が影響していると考えられるでしょう。
特に所得が思うように得られていない人の中には、開業間もない事業者や副業として小規模に事業を行っている人なども含まれるのではないでしょうか。
そのため、自営業の所得分布は会社員と比較するとばらつきがあり、平均値だけでは実態を捉えることができません。
職種による年収の違い
自営業の年収は、職種によっても異なります。
例えば、IT系の専門職(Webエンジニアやデザイナーなど)は、比較的設備投資の金額が低く、専門スキルに対する報酬も比較的高いため、より所得が確保しやすい傾向にあります。
一方、飲食店のように店舗を構えたり、在庫を抱えたりする必要がある業種は、初期投資や毎月の固定費がかさむため、一定の年収を得にくい傾向です。
また、タクシー運転手のように、働く時間や集客努力によって収入が変動する職種によっては安定しないこともあるでしょう。
上記のように、同じ自営業であってもどのような事業を行うかによって収入の構造や平均的な年収水準は変わってきます。
自営業を始める、あるいは現在の事業で年収をさらに確保したいと考えている人は、自分の職種の特性や市場の状況を理解することが重要です。
高収入を目指すのであれば、一定の需要があり、専門性が求められる分野を検討したり、自分のスキルを磨いたりすることを忘れてはいけません。
自営業の手取り額
ここでは、自営業の手取り額について見ていきましょう。
手取りの計算方法
自営業者の手取りは、会社員のように給与明細を見ればわかるものではありません。
手取りを計算する方法は、以下の通りです。
- 年間の売上から必要経費を差し引いて「所得」を算出する
- 所得から所得税・住民税・個人事業税(該当する場合)、国民健康保険料・国民年金保険料といった社会保険料を差し引く
⇒税金や社会保険料の計算は、所得額や家族構成、加入している社会保険などによって変化する
⇒所得税は累進課税制度が適用されるため、所得が高くなるにつれて税率も上がる
⇒住民税は原則として所得の10%程度ですが、均等割も加算される
⇒国民健康保険料や国民年金保険料も、所得に応じて金額が変動
手取りの計算方法を正確に理解するには、以上の税金や社会保険料の計算方法についても把握しておく必要があります。
手取り額=(売上-経費)-(所得税+住民税+個人事業税+社会保険料)という計算式が基本となりますが、各種控除の適用により金額は変わってくるでしょう。
年収別の手取り目安
自営業者の手取り額は、所得や年収だけでなく、経費の額や適用される控除、さらには住んでいる地域によっても変動するため、一概にいくらとは言えません。
しかし、一般的な目安として、所得の約6割〜7割程度が手取りになると言われます。
年収200万、300万、400万、500万、600万、700万、800万といった年収別に手取りの目安を見ていくと、年収が高くなるにつれて税金や社会保険料の負担も増えるため、手取りの割合は低くなるもしくは大幅に減ることがあります。
例えば、年収が低い場合は税率が低く、社会保険料の負担も比較的少ないため手取り率は高めになりますが、年収が増えるにつれて所得税の税率が上がり、社会保険料の金額も増えるため、年収に対する手取りの割合は減少するのです。
しかし、これはあくまでも一般的な目安であり、節税対策などを適切に行うことで手取りを増やすことも可能です。
具体的な手取りについては次の項目を参考にしてみましょう。
年収200万円の場合
自営業で年収200万円の場合、手取り額は一般的に150万円前後が目安となるでしょう。
年収200万円の場合、所得税の税率は比較的低く、社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)の負担も年収が高い層に比べると抑えられます。
しかし、上記の金額は住んでいる地域や家族構成によって変動します。
例えば、基礎控除やその他の所得控除を適用することで、課税される所得金額がさらに減少し、結果として所得税額が少なくなる可能性がある他、国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、開業初年度など所得が低い場合は保険料を抑えられることが可能です。
年収200万円は、自営業としてはスタート段階で、手取りを増やすためにはまず売上を安定させつつ、経費の管理を徹底することが重要です。
年収300万円の場合
自営業で年収300万円の場合、手取り額はおよそ220万円から230万円程度が目安と考えられます。
年収300万円になると、所得税の税率が年収200万円の場合よりも上がりますが、それでも税負担はまだ比較的抑えられていると言えます。
国民健康保険料や国民年金保険料の金額も、年収に応じて増加しますが、手取りに占める割合は大きく変動しないことが多いです。
この年収帯では、事業が軌道に乗り始め、安定した収入が得られるようになってきていると考えられるでしょう。
手取りをさらに増やすためには、単に売上を増やすだけでなく、経費の適正な計上や利用できる所得控除の活用といった節税対策も視野に入れることが効果的です。
年収400万円の場合
自営業で年収400万円の場合、手取り額の目安は約290万円程度になることが想定されます。
年収が400万円になると、所得税や住民税、そして社会保険料の負担がより顕著になります。
特に所得税は累進課税のため、税率が段階的に上がる他、年収400万円を超えると個人事業税の課税対象となる可能性も出てくるはずです。
個人事業税は事業所得が290万円を超えた場合に課税され、税率は業種によって異なりますが、多くの場合は5%です。
この個人事業税も手取り額に影響を与えるでしょう。
税金や社会保険料の負担が増えるため、手取りを維持または向上させるためには、一層の節税対策が重要となります。
例えば、青色申告による特別控除の活用や、経費として計上できるものを漏れなく計上することなどが効果的です。
年収500万円の場合
自営業で年収500万円を達成した場合、手取り額の目安はおおよそ360万円程度になるでしょう。
年収500万円となると、所得税の税率がさらに高くなり、住民税や社会保険料の負担も増加します。
個人事業税についても、課税される可能性が高く、その税額も所得に応じて増えるのが一般的です。
この年収レベルでは、税金や社会保険料の合計額が年収に占める割合が無視できないものとなります。
そのため、いかに効果的な節税を行うかが、手取り額を最大化するための鍵です。
青色申告の活用はもちろんのこと、小規模企業共済への加入やiDeCoの活用など、将来のための資産形成と同時に税負担を軽減できる制度の利用も検討しましょう。
年収600万円の場合
自営業で年収600万円の場合、手取り額は約420万円程度が見込まれます。
年収600万円になると所得税の税率がさらに上がり、住民税や社会保険料の負担も一層大きくなります。
それらの年収帯では、税金や社会保険料の合計額が年収の大部分を占めるようになるため、手取りを効果的に増やすためには売上を伸ばす努力に加え、積極的に節税対策に取り組むことが不可欠です。
年収600万円の場合、所得税や住民税、個人事業税に加え、国民健康保険料や国民年金保険料といった社会保険料の負担も計り知れません。
上記の合計額をいかに抑えるかが、手元に残る金額を左右するはず。
経費の適切な管理や所得控除の活用はもちろん、事業の効率化による経費削減も、手取りを増やす手段の1つとなるでしょう。
年収700万円の場合
自営業で年収700万円に達した場合、手取り額の目安は約470万円程度になると考えられます。
年収が700万円になると、所得税の税率がさらに高くなり、税負担が増加します。
住民税や社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)の金額も所得に比例して増えるため、全体的な負担は相当なものです。
この年収帯では、税金や社会保険料の合計額が手取りに与える影響が非常に大きくなります。
そのため、積極的に節税対策を行うことが、手取りを維持・向上させるために重要です。
他の年収と同様に青色申告特別控除を最大限に活用したり、事業に関わる経費を漏れなく計上したりする他、専門家である税理士に相談することで、自身の状況に合わせた最適な節税方法を見つけるのも良いでしょう。
年収800万円の場合
自営業で年収800万円(所得)を稼いだ場合、手取り額は約530万円程度が見込まれます。
年収が800万円になると、所得税の税率がさらに高くなり、税負担が非常に大きくなる他、住民税や社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)の負担も所得に応じて増加するため、全体として差し引かれる金額が大きくなるわけです。
この年収帯では、税金や社会保険料の負担がかなりの割合を占めるため、手取りを増やすためには、より高度な節税対策が必須です。
例えば、小規模企業共済やiDeCoなどを活用した所得控除の利用、さらには事業規模が大きくなってきた場合は法人化を検討することで、税負担を軽減できる可能性があります。
年収800万円以上になると、税理士などの専門家と連携し、計画的な税務対策を行うことが重要となるでしょう。
年収による税金と社会保険料
自営業者が支払う税金と社会保険料は、年収(所得)によって大きく変動します。
主な税金としては、所得税、住民税、場合によっては個人事業税があります。
- ・所得税:累進課税制度が採用されており、所得が高くなるにつれて税率も段階的に上がる
⇒例えば、所得が非課税枠を超えるところから税金が発生し、年収400万、600万、800万と所得が増えるにつれて、より高い税率が適用される部分が増えていく - 住民税:所得割と均等割があり、所得割は原則として所得の10%
- 個人事業税:事業所得が290万円を超える場合に課税され、税率は業種により変わる
社会保険料としては、国民健康保険料と国民年金保険料があります。
これらの保険料も、所得に応じて金額が計算されるため、注意が必要です。
会社員の場合は健康保険や厚生年金に加入し、保険料は会社と折半ですが、自営業者は全額自己負担となります。
また、年収が一定額を超えると消費税の課税事業者となる場合もあるわけです。
そうした税金や保険は、手取り額に直接影響するため、自身の年収レベルでどのくらいの負担が発生するのかを把握しておくことが重要です。
税金と社会保険料の計算は複雑なため、正確な金額を知りたい場合は税理士に相談するか、自治体や年金事務所に問い合わせることをおすすめします。
確定申告について
次に、確定申告について見ていきましょう。
確定申告が必要な所得
自営業者の場合、原則として所得が発生すれば確定申告が必要です。
具体的には、事業所得や不動産所得などがあり、それらの合計額から基礎控除などを差し引いた後の金額がプラスになる場合は、確定申告をして納税する必要があります。
しかし、年間の所得の合計額が48万円(基礎控除額)以下の場合は、所得税の確定申告は不要となるのが一般的です。
これは、所得が基礎控除額を下回るため、所得税がかからないためです。
しかし、所得が0円の場合でも、住民税の申告が必要な場合や、国民健康保険料の計算のために申告が必要な場合もある他、副業として自営業を行っている会社員の場合も、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合には確定申告が必要となります。
まずは、自分の所得が確定申告の必要がある金額かどうかを確認し、期限内に適切に手続きを行うことが重要。
所得が100万円以下でも、状況によっては確定申告が必要になるケースがあるため注意しましょう。
確定申告の種類
自営業者が行う確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
- 白色申告:事前の申請が不要で帳簿付けの方法も比較的シンプルだが、利用できる控除が少ないという特徴がある
- 青色申告:事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要と日々の取引を複式簿記という方法で記帳する必要があるが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられたり、赤字を最長3年間繰り越せたりする
以上のように青色申告は白色申告と比べて税制上の魅力があるのが特徴です。
特に、事業所得がある程度ある場合は、青色申告を選択することで税負担を大きく軽減できる可能性があります。
どちらの申告方法を選択するかは、事業の規模や経理処理にかけられる時間などを考慮して判断しましょう。
長期的に事業を続けていくのであれば、青色申告を選択し、適切な帳簿付けを行うのが良いでしょう。
確定申告の利点
自営業者が確定申告を行うことには、税金を正しく納めるという義務を果たすだけでなく、様々な利点があります。
最大の利点の一つは、所得税や住民税、国民健康保険料などの税金・社会保険料の金額が確定し、自身の負担額を正確に把握できることです。
これにより、今後の資金繰りや事業計画を立てやすくなるでしょう。
また、青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越し、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など様々な税制上の利点があります。
それらの控除や特例を適用することで、課税される所得金額が減少し、結果として税負担を軽減することが可能です。
なお、確定申告書は自分の所得を公的に証明する書類となるため、住宅ローンや事業用ローンの申請、クレジットカードの作成、保育園の利用申し込みなど、様々な場面で提出を求められることがあります。
適切な確定申告を行い、自身の所得を証明できるようにしておくことは、社会的な信用を得るうえでも重要です。
自営業の年収を増やすには
次に、自営業の年収を増やすにはどうすればいいかについて見ていきましょう。
売上を確保する
自営業の年収を増やすための最も直接的な方法は、売上を増やすことです。
売上増加のためには、様々な取り組みが考えられます。
- ・提供する商品やサービスの単価を上げる
⇒そのためには、自身の専門性を高めたり、付加価値をつけたりすることが必要 - 顧客数を増やすための営業活動や集客施策を行う
⇒新規顧客獲得はもちろんのこと、既存顧客のリピート率を高めることも安定した売上につながる
⇒リピーターを増やすためには、顧客満足度を高めることや定期的な情報提供、特典の提供などが考えられる
⇒紹介による新規顧客の獲得も効果的 - 新たな商品やサービスを展開したり、既存の事業と関連性のある分野で複業する
⇒売上の柱が増え、年商を拡大することに繋がる
上記のように、市場のニーズを把握し、競合との差別化を図りながら、戦略的に売上を増やすための努力を継続することが重要と言えるでしょう。
経費を適切に計上する
自営業の年収は、売上から経費を差し引いて計算されるため、経費を適切に計上することは税負担を軽減し、結果として手取り額を増やすことに繋がります。
事業に関わる支出であれば、領収書などを保管し、漏れなく経費として計上しましょう。
例えば、事務所の家賃や光熱費、通信費、仕事で使用する文房具や消耗品、打ち合わせの飲食費、事業に関する書籍の購入費、セミナー参加費、さらには事業で使用する車両の維持費なども経費にすることが可能です。
自宅を仕事場として使用している場合は、家賃や光熱費の一部を按分して経費にすることもできるでしょう。
また、従業員を雇用している場合は、給与も経費となるでしょう。
経費を適切に計上すれば、課税される所得金額を減らすことができるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。
しかし、個人的な支出を事業の経費として計上することは認められていません。
ゆえに、何が経費として認められるかを正確に理解し、適切に処理することが重要です。
所得控除を活用する
所得控除とは、所得税額を計算する際に、所得金額から一定額を差し引くことができる制度です。
所得控除を適用することで、課税される所得金額が減少し、結果として所得税の負担を軽減することができます。
自営業者が利用できる主な所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金保険料)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などがあります。
これらの控除は、それぞれの要件を満たす場合に適用することが可能です。
例えば、国民健康保険料や国民年金保険料を支払った金額は全額社会保険料控除として所得から差し引くことが可能。
また、一定額以上の医療費を支払った場合も医療費控除が利用できるでしょう。
所得控除を最大限に活用するためには、自身がどのような控除を受けられるのかを把握し、確定申告の際に適切に申告しましょう。
控除に関する証明書が必要な場合もあるため、日頃から関連書類を整理しておくと良いでしょう。
青色申告を活用する
自営業者が手取り額を増やすための有効な方法の一つが、青色申告の活用です。
青色申告を選択することで、白色申告にはない様々な税制上の利点があります。
最大の利点は、青色申告特別控除です。
正規の簿記(複式簿記)で記帳し、e-Taxで申告を行うなどの要件を満たすことで、最大65万円を所得から控除することができます。
これにより、課税される所得金額を大幅に減らすことができるため、所得税や住民税の負担を大きく軽減できるでしょう。
また、青色申告では事業で発生した赤字(損失)を翌年以降最長3年間繰り越して、将来の所得から差し引くことが可能です。
それにより、事業が不安定な時期でも税負担を軽減できます。
家族への給与を必要経費として計上できる青色事業専従者給与の制度や、30万円未満の固定資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例も駆使すれば、大幅に負担を軽減できるでしょう。
上記の利点を最大限に活用することで、間接的に手取り額を増やすことが可能です。
ただし、青色申告を行うためには、事前の申請や日々の取引の記帳が必要となります。
年収の申告が必要な場面
最後に、年収の申告が必要な場面について見ていきましょう。
確定申告以外での申告
自営業者は、年に一度の確定申告とは別に、様々なタイミングで自分の年収を申告する必要があります。
主な場面としては、以下の通りです。
- 住宅ローンや事業用ローンなどの融資を金融機関に申し込む際
⇒返済能力を判断するために所得証明書類の提出が求められる - クレジットカードを作成する際
⇒支払能力を確認するために年収の申告が必要となる - 保育園の入園申し込みの際
⇒保育料の算定のために世帯の所得を証明する書類の提出が必要となる - 奨学金を申請する際
⇒家計の経済状況を判断するために所得証明が求められる
以上のような場面では、税務署が発行する所得証明書や確定申告書の控えが証明書類として利用されます。
そのため、確定申告を正しく行い、これらの書類を適切に保管しておくことが重要です。
適切な年収の伝え方
自営業者が確定申告以外の場面で年収を申告する際、どのように伝えるべきか迷うことがあるかもしれません。
特に、ローン審査などで「年収はいくらですか?」と聞かれた場合、売上金額を答えてしまうと、経費を差し引く前の金額であるため、実際の所得とは大きな差が生じ、誤解を招く可能性があります。
このような場面では、一般的に確定申告書で計算された「所得金額」を伝えるのが適切です。
所得金額は、収入から経費や青色申告特別控除などを差し引いた後の金額であり、税金や社会保険料の計算の基礎となる、事業の実質的な利益を示す数字だからです。
金融機関や各種機関も、個人の返済能力や負担能力を判断する際に、それらの所得金額を重視します。
したがって、年収を問われた際には、確定申告書の「所得金額」を正確に伝えるようにしましょう。
必要に応じて、確定申告書の控えなどの証明書類を提出することで、より正確な情報を示すのも良いかもしれません。
まとめ
この記事では、自営業の年収について、定義、収入や手取りとの違い、平均的な年収、手取りの計算方法、年収を増やすための具体的な方法までを解説しました。
自営業の年収とは、一般的に売上から経費を差し引いた「所得」を指し、その所得が税金や社会保険料の計算の基礎となることをご理解いただけたかと思います。
ただ、手取り額は所得から税金や社会保険料を差し引いた金額であり、年収が高くなるにつれて税負担が増えるため、注意が必要です。
年収を増やすためには、売上を伸ばす努力はもちろんのこと、経費の適切な管理、所得控除の活用、青色申告を最大限に活かすことが欠かせません。
今後、自営業として活動していく人は、上記のスキルを活かし、事業の成長と安定した手取り収入の確保を目指しましょう。
なお、税金や経費、確定申告に関する疑問は、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。