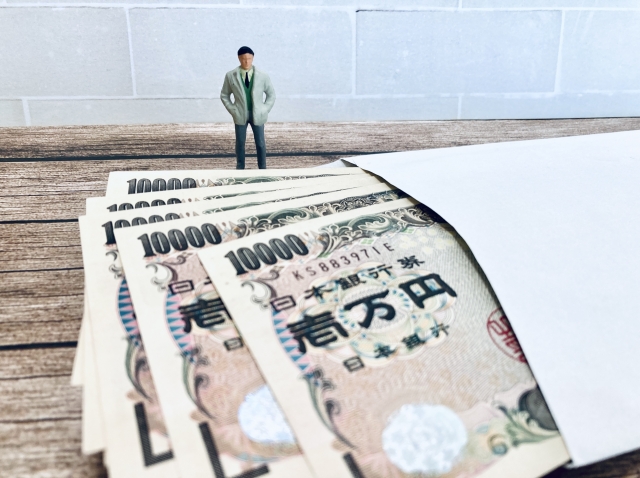雇われ社長とは何か、そして代表取締役との違いについてご存知でしょうか。
会社経営のトップである「社長」には、実はいくつかの種類があり、その中でも「雇われ社長」は、自身の会社を所有することなく、会社のオーナーなどから経営を任される立場にあります。
これから雇われ社長を目指す方、あるいは現在雇われ社長として働く方にとって、その実態やメリット、そして潜在的なリスクを理解することは非常に重要です。
この記事では、雇われ社長の定義から、オーナー社長との比較、雇われ社長になることの利点とリスク、そして辞任時の注意点まで、網羅的に解説していきます。
雇われ社長という働き方を多角的に捉え、今後のキャリアを考える上での一助となれば幸いです。

雇われ社長の定義とオーナー社長との比較

まず、雇われ社長がどのような立場にあるのか、そして、自身で会社を所有・経営するオーナー社長と何が違うのかを明確に理解しておきましょう。
ここを理解することで、雇われ社長という働き方の特徴が見えてきます。
雇われ社長とは
雇われ社長とは、会社のオーナーに雇われて経営を任されている社長を指します。
会社の所有権は持たず、株主や取締役会からの委任を受けて会社の経営を行う存在です。
代表取締役という肩書を持つのが通例で、会社を代表して契約などの対外的な行為を行う権限を有します。
ただ、あくまで雇われている立場であり、給料を受け取って働くという点では従業員と似た側面も持ち合わせているわけです。
特に、大企業や中小企業で後継者不足に悩むケースなどでは、外部から雇われ社長が選任されることが珍しくありません。
オーナー社長との相違点
オーナー社長は、自身が会社の株式の大半を保有し、会社の所有者として経営を行う立場です。
会社の所有と経営が一致しており、経営に関する最終的な意思決定権を持ちます。
対して、雇われ社長は会社の所有権を持たず、あくまで経営のプロとして手腕を発揮することを期待されるわけです。
ゆえに、経営判断においてオーナーや株主の意向が強く反映されることや、最終的な意思決定権がオーナーにある場合があるという点が、オーナー社長との違いとなります。
雇われ社長になるメリット
ここからは、雇われ社長になるメリットについて見ていきましょう。
自己資金なしで経営に携われる
雇われ社長は、自己資金をほとんど、あるいはまったく準備することなく経営に携われるのがメリットです。
自分で会社を設立するオーナー社長の場合、開業資金や運転資金など多額の資金が必要となりますが、雇われ社長はすでに存在する会社の経営を任されるため、資金を用意する必要がありません。
既存の事業基盤や資産を活用して経営手腕を発揮できるのが、魅力と言えます。
業績によってより報酬が得られる
雇われ社長の報酬は、会社の業績に連動して変動するのが通例で、業績が好調であればより報酬を得られる可能性があります。
一般社員に比べて役員報酬は高額に設定されるのが通例で、会社の成長に貢献することで自身の収入アップが可能です。
ただ、あくまで会社の業績に左右されるので、常に成果を求められるというプレッシャーも伴うでしょう。
自由な経費の裁量がある
会社のトップである社長は、業務遂行に必要な経費に関して、一般従業員よりも自由な裁量を持つことができます。
会議費や交際費など、会社の経営に関わる支出について、自身の判断で決定できるわけです。
こうした裁量権は、経営戦略を実行していくうえで欠かせない要素となるのではないでしょうか。
経営者としての経験が得られる
雇われ社長になることは、経営者としての貴重な経験を積む絶好の機会です。
会社のトップとして、経営戦略の立案や実行、組織マネジメント、意思決定など、多岐にわたる業務に携わることになります。
それらの経験は、後のキャリアにおいて財産となることは間違いありません。
自己資金を投じるリスクなく、経営の最前線で実践的なスキルを磨けるのは、雇われ社長ならではの利点に他なりません。
雇われ社長になるデメリット
ここでは、雇われ社長になるデメリットについて見ていきましょう。
株主の意向で解任される
雇われ社長は株主によって選任されるため、株主の意向に沿わない場合や期待される業績を達成できない場合は解任されるリスクがあります。
とりわけ、オーナー社長が強い影響力を持つ会社では、オーナーとの関係性が経営の継続に関わってきやすいです。
短期的な成果を求める株主と長期的な視点で経営を行いたい社長との間で意見の対立が生じることも珍しくありません。
労働者としての保護が及ばないので、突然解任される可能性もゼロではないでしょう。
会社の債務保証を求められる
会社の借入などに関して、雇われ社長に対して連帯保証人になることを求められるケースが珍しくありません。
会社の債務について個人で保証することは、万が一会社が倒産した場合に社長自身が返済義務を負うというリスクを伴います。
ゆえに、就任前に会社の財務状況を把握し、安易な連帯保証は避けるべきです。
労働法規の保護が及ばない
雇われ社長は会社の役員という立場であり、労働者とはみなされません。
このため、労働基準法などの労働法規による保護が及ばない場合があります。
例えば、残業代や休日出勤手当の支給対象とならなかったり、雇用保険に加入できないので失業保険を受け取れなかったりすることがあるわけです。
役員報酬という形で支払われるものの、労働がそのまま収入に反映されないという側面もゼロではないなど、注意が必要ではないでしょうか。
辞任でトラブルが発生する
雇われ社長が辞任する場合、会社との間でトラブルになるケースが見られます。
とりわけ、会社の業績が悪化している状況や後任が決まっていない状況で辞任しようとすると、会社側から損害賠償請求をされる可能性も否定できません。
また、辞任後の退任登記手続きを会社が行ってくれないといった問題が発生することも。
ゆえに、辞任を検討する場合は契約内容を確認し、慎重に進めることが必要です。
経営上の意思決定権に限界がある
雇われ社長は経営を任されますが、会社の所有者ではないため、経営に関する最終的な意思決定権はオーナーや株主が持っていることが一般的です。
基本的に、重大な経営判断を行う場合、オーナーの承認が必要であったり、オーナーの意向に沿わなければならなかったりすることがあります。
結果的に、自らの経営方針や戦略を十分に実行できない可能性も。
業績不振などのプレッシャーがある
雇われ社長は、会社の業績向上という明確なミッションを背負っているので、業績が思わしくない場合には、オーナーや株主からの厳しいプレッシャーに晒されます。
成果を出すことが自身の評価や雇用の継続に直結するからこそ、精神的な負担は避けられません。
とりわけ、スピード感のある業績改善を求められる場合には、言いようのない重圧を感じるかもしれません。
会社の負債に関する責任
会社の負債について、原則として雇われ社長が直接弁済する義務はありません。
ただ、会社の借入で連帯保証人となっている場合や、任務を怠ったことによる損害賠償責任を負う場合には、会社の負債に関連した責任を問われる可能性があります。
また、取引先とのトラブルや不祥事などが発生した場合、会社の代表として矢面に立って対応し、最終的な責任を負わなければならない場面も出てくるのです。
雇われ社長として働くうえでの注意事項
次に、雇われ社長として働くうえでの注意事項について見ていきましょう。
適切な報酬水準の確保
雇われ社長は会社の経営という重責を担うため、責任に見合った適切な報酬水準を確保することが重要です。
役員報酬の額は、会社の規模や業績、自身の経験や能力によって変わりますが、就任前にじっくりと交渉し、合意しておく必要があります。
月額報酬だけでなく、業績連動のインセンティブや退職慰労金なども含めて検討することで、より良い条件を引き出せます。
また、十分な年収を確保することはモチベーションの維持にも繋がりやすいです。
株式保有の交渉
可能であれば、会社の株式を一部保有することを交渉してみましょう。
株式を保有することで、株主総会での議決権を得ることができ、自身の経営における発言力や立場を強化できます。
また、会社の成長を自身の資産増加に直接繋げることも可能です。
権限と責任範囲の明確化
自身に与えられる権限の範囲と、負うべき責任の範囲を就任前に明確にしておくことは、トラブルを避けるうえで非常に大切です。
具体的には、経営に関する最終的な意思決定権が誰にあるのか、どのような事項についてオーナーの承認が必要なのかなどを具体的に確認する必要があります。
お飾り社長として、権限がないにもかかわらず重い責任だけがのしかかるような状況は避けましょう。
連帯保証の拒否
会社の債務に対する連帯保証人になることは、極めて多大なリスクを伴うため、可能な限り拒否すべきです。
雇われ社長の立場であっても、個人の財産にまで影響が及ぶ可能性があります。
もし、連帯保証を求められた場合は、リスクを十分に理解し、慎重に判断しましょう。
責任限定契約の検討
万が一、会社に損害を与えてしまった場合の賠償責任を限定する「責任限定契約」の締結を検討することも有効なリスクヘッジとなります。
ただ、責任限定契約が適用されるのは特定の役員に限られる場合があり、また、任務を怠ったことによる悪意や重過失がある場合には適用されないなど、制約があるため注意が必要です。
まずは、立場や状況を踏まえ、弁護士などの専門家に相談しましょう。
会社とオーナーの意図の理解
雇われ社長として招聘される背景には、必ずオーナーの意図があります。
なぜ自分に社長を任せたいのか、会社が抱える課題は何で、どのような成果を期待されているのかを深く理解することが必須です。
まずは、オーナーのビジョンと自らの考えが一致しているかを確認し、共通認識を持って経営に臨むことが、円滑な関係と経営の成就に繋がるでしょう。
会社の財務状況の把握
就任前に、会社の財務状況を詳細に把握することは欠かせません。
会社の売上、利益、負債、資金繰りなどを正確に理解することで、潜在的なリスクを見抜き、適切な経営戦略を立てることが可能です。
また、自身の報酬や会社の債務保証に関わるリスクを判断するうえでも忘れられない情報となります。
雇われ社長を辞めたい場合
最後に、雇われ社長を辞めたい場合について見ていきましょう。
辞任に伴う損害賠償請求の可能性
雇われ社長は、原則としていつでも辞任することができます。
ただ、会社に不利な時期に辞任したり、後任への引き継ぎを怠ったりするなど、会社に損害を与えるような形で辞任した場合、会社から損害賠償請求をされる可能性があります。
中でも、重要なプロジェクトの遂行中や会社の経営状況が厳しい時期の辞任は、慎重な判断が重要です。
円満な辞任を目指すためには、事前に会社と十分に話し合い、適切なタイミングと手続きを踏むことが大切です。
退任登記の手続き
雇われ社長が辞任した場合、法務局で役員の退任登記を行うことが必要です。
これは会社が行うべき手続きですが、会社が速やかに対応してくれない場合もあります。
登記が変更されないままになっていると、形式上はまだ社長として扱われ、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。
会社が退任登記を行わない場合は、自身で手続きを請求することを検討してみてはいかがでしょうか。
退職金の請求
雇われ社長は「退職慰労金」という形で退職の際に金銭を受け取ることがあります。
これは一般社員の退職金に相当するものですが、支給されるかどうか、またその金額や算出方法は会社の定款や株主総会の決議によって定められるのが通例です。
就任時の契約内容や会社の規定を確認し、退職慰労金の請求が可能であれば適切に手続きを行う必要があります。
定款に定めがない場合は、株主総会での決議が必要です。
まとめ
雇われ社長という働き方は、自己資金なしで経営経験を積める、業績次第で高額の報酬を得られる可能性があるなど、魅力的な側面が数多く存在します。
ただ、株主の意向による解任リスク、会社の債務保証、労働法規の保護が限定されること、辞任時のトラブルなど、特有のリスクや潜在的な問題も無視できません。
雇われ社長を目指す、あるいは現在雇われ社長として働くうえで重要なのは、これらのメリットとデメリットの両方を十分に理解し、自身の状況やキャリアプランと照らし合わせて慎重に判断することです。
適切な報酬の確保、権限と責任範囲の明確化、そして会社の財務状況の把握は、リスクを軽減し、安定した経営を行ううえで欠かせません。
もし辞任を検討するような状況になった場合は、契約内容や法的な手続きを確認し、可能であれば専門家のアドバイスを得ながら、会社との対話を大切に進めることが、円満な解決への道を開く鍵となるでしょう。
まずは、当記事で解説した情報を参考に、雇われ社長という働き方について深く理解し、今後のビジネスキャリアにおける意思決定に活かしてみてはいかがでしょうか。