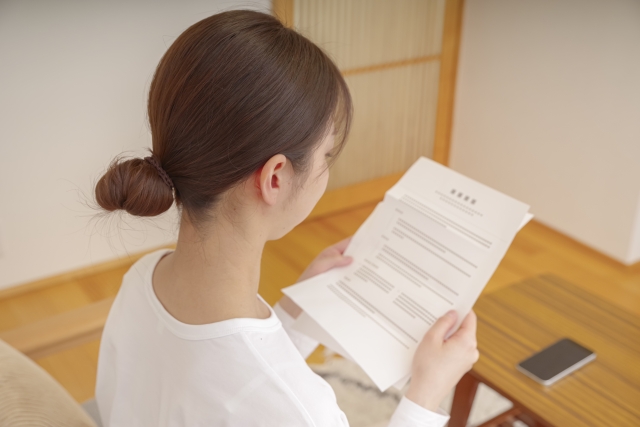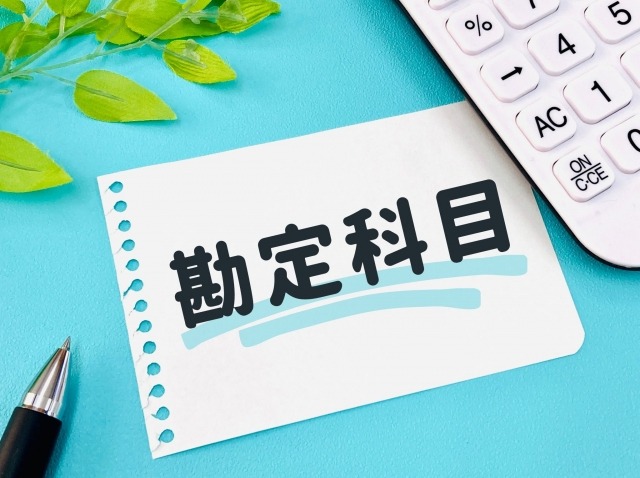事業を成長させるためには、補助金や交付金といった国の支援制度による資金調達が欠かせません。
ただ、それぞれの違いや活用方法について十分に理解できていない人も珍しくないです。
人によって補助金や交付金が何を指すのかもよくわからない人も珍しくありません。
この記事では、補助金と交付金の違いについて詳しく解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶開業資金の集め方!起業にはいくら必要?ノウハウを得ながら収入を得るお得な貯め方もご紹介!
▶独立起業/開業に失敗しないために気をつけるポイントとは?
▶起業の成功例!成功のアイデアやコツを紹介!

補助金について
まずは、補助金について見ていきましょう。
補助金の概要
補助金は、国や地方公共団体が特定の事業や活動を支援するために交付する資金です。
主に経済産業省が管轄しており、公益性があると認められる事業や、財政援助の作用を持つ事業に対して給付されます。
補助金は返済の義務がない点が特徴です。
ただ、支給を受けるには審査が必要で、補助金適正化法に基づき、定められた目的以外に使用することは禁止されています。
場合によっては申請しても交付されないので十分にお気を付けください。
なお、補助金に関しては補助金等の交付申請や決定、補助事業の遂行、実績報告など、補助事業の予算執行に関する基本的な事項を定めている補助金等適正化法があり、不正申請や不正使用の防止が徹底されています。
つまり、補助金等適正化法に従って補助金が決められているわけです。
補助金を申請する予定の方は、上記の法律に注意しましょう。
補助金の具体的な種類
補助金には色んな種類があり、目的に応じて多岐にわたるのが一般的です。
基本的に、中小企業庁が実施するものには、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金といった、事業の革新や生産性向上、販路開拓などを支援するものが含まれます。
農林水産省でも農業経営体の経営強化や農山漁村振興に向けた補助金があります。
これらの補助金は、設備投資やシステム開発、販路開拓の取り組みなど、幅広い経費が対象となるのが通例です。
また、雇用関連では助成金と呼ばれるものもあり、キャリアアップ助成金や働き方改革推進支援助成金などが労働者のキャリアアップや労働環境の整備を支援しています。
補助金の一覧は、ミラサポPlusなどのウェブサイトで確認することが可能です。
そうした補助金は、企業の成長を後押しするための支援制度と言っても過言ではありません。
交付金について
次に、交付金について見ていきましょう。
交付金の概要
交付金とは、国や地方公共団体が特定の行政目的を達成するために交付する金銭のことです。
広義には補助金も交付金に含まれることがありますが、実務上は主に国から行政機関である地方自治体へ支給される資金を指します。
交付金は、地方自治体が地域の実情に合わせて交付金の趣旨に沿った事業やプロジェクトを実施するための財源として活用されます。
補助金と同様に原則として返済の義務はありませんが、交付金は地域経済への貢献度が高い分野に重点的に支給されやすいです。
交付金の具体的な種類
交付金にも色んな種類があり、多くは地方自治体が行う特定の事業や政策を支援するために使用されます。
具体的な種類は、地方創生推進交付金、社会資本整備総合交付金、地域脱炭素推進交付金などが主です。
地方創生交付金には、結婚・出産・育児の支援、移住・定住の促進、地域を担う人材育成、観光・農林水産業・その他の産業振興に資する事業などが含まれます。
また、防衛施設の周辺地域に対して交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金や基地交付金なども存在するなど、多種多様です。
交付金は、上記の事業に要する費用に充てられ、地域活性化や住民サービスの向上などに役立てられます。
一部、国から地方自治体に交付された後、さらに自治体から事業者や個人に対して給付金という名称で支給されることも珍しくないです。
補助金と交付金の相違点
補助金と交付金はどちらも返済不要な公的資金ですが、目的や対象、お金の流れに違いがあります。
補助金は主に民間企業や個人事業主が特定の事業を行う際に、経費の一部を支援することを目的としています。
対して、交付金は主に国から地方自治体に対して交付され、地方自治体が地域の実情に合わせた行政サービスや事業を実施するための財源として使用されるのが一般的です。
交付金の場合、基本的なお金の流れは「国→自治体」となっており、さらに自治体から給付金として個人や事業者に支給されるケースも珍しくありません。
支援の対象が事業者なのか、それとも地方自治体なのかという点も両者の違いです。
補助金・交付金の利点と課題
ここからは、補助金・交付金の利点と課題について見ていきましょう。
補助金活用の利点
補助金を活用する最大の利点は、新たな事業や設備投資にかかる費用負担を軽減できることです。
返済不要の資金を得られるため、自己資金だけでは難しかった規模の投資に挑戦できます。
これにより、技術力の向上や新製品・新サービスの開発、生産性の向上などが可能になり、事業の成長を加速させることが期待できます。
また、補助金に採択されることは、事業計画が国の機関に認められたという証明になり、対外的な信用力の向上やPR効果にも繋げることが可能です。
補助金活用の課題
補助金活用にはいくつか課題も存在します。
まず、申請手続きが複雑で大量の書類作成が必要となる場合が多く、無駄に時間や労力がかかることも少なくありません。
また、補助金は原則として後払い(精算払い)で、一時的に事業資金を立て替える必要があるのも難点と言えるでしょう。
補助金は応募すれば必ず受給できるものではなく、一定の競争率があり、審査に通らないことも珍しくないです。
採択後も、事業計画に沿った適切な遂行や定期的な報告義務があり、これらを怠ると補助金の返還を求められることもあります。
また、補助金を受けた事業で収益が出た場合には、補助金の一部を国に返還する必要が生じる「収益納付」という制度もあるからこそ、それらの点には注意が必要です。
まずは条件等含め、よく確認してから申請してみてはいかがでしょうか。
交付金活用の利点
交付金の利点は、地方自治体が地域の実情やニーズに合わせて柔軟に活用できる点です。
特定の行政サービスや事業の財源として充当されるため、地域住民の生活の質の向上や、地域経済の活性化に直接的に貢献できます。
また、財政的に厳しい地方自治体にとっては安定的な収入源となるので、計画的な事業実施が可能です。
補助金と比較すると、個別の事業者に対する厳密な検査が限られている点も利点として挙げられます。
交付金活用の課題
交付金の課題としては、使途が特定の目的に限定される場合が多い点が挙げられます。
地方自治体は交付金の趣旨に沿った事業を実施する必要があります。
また、交付金の額や採択される事業は国の政策や予算に左右され、継続的な受給が保証されるものではありません。
民間企業にとって、交付金は直接申請できる機会が少ないのも課題と言えるでしょう。
上記の課題をどうクリアしていくかが求められるのではないでしょうか。
補助金を受け取るまでの手続き
ここでは、補助金を受け取るまでの手続きについて見ていきましょう。
公募開始と申請
補助金を受けるためには、関心のある補助金の公募情報を収集することが重要です。
補助金についてはミラサポPlusなどのウェブサイト、または各府省庁や自治体のウェブサイトで公募情報が公開されるので、公募要領を確認し、申請要件や補助対象となる事業内容、経費などを把握します。
申請可能な期間は限られているものが珍しくないからこそ、的確な情報収集と準備が大切です。
申請に関しては必要書類を準備し、オンラインまたは郵送でできます。
審査と採択
提出された申請書類は、補助金の目的や要件に合致しているか、事業計画の実現性や効果はどうかといった観点から審査が行われます。
審査は、書面審査に加え、必要に応じて面接審査が行われることも珍しくないです。
審査の結果、採択される事業者が決定されるのが一般的です。
基本的に採択された事業者には、採択の旨が通知されます。
交付申請と事業実施
採択された事業者は、補助金の交付を正式に申請するための手続きを行います。
具体的には、事業計画の詳細や経費の内訳などを記載した交付申請書を提出します。
事務局による審査を経て、交付決定通知書が発行されると、正式に補助金交付の決定です。
交付決定を受けた後、補助事業計画に沿った事業を実施することが可能です。
なお、交付金とは異なり、補助金は事業実施にかかった経費に対して後から支払われる精算払い方式が通例とされるので注意が必要。
実績報告と交付決定
補助事業が完了したら、事業の成果や使用した経費などをまとめた実績報告書を作成し、事務局に提出します。
この際、領収書などの証拠書類の添付が必要です。
事務局は提出された実績報告書の内容を確認し、補助事業が適切に行われたか、経費が補助金の対象として認められるかなどを審査します。
それらの審査を経て、最終的な補助金の額が確定し、交付金額が決定されるわけです。
補助金の受け取りと進捗報告
交付金額が確定した後、指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
最終的に、補助金の受け取りが完了すれば、無事に手続き終了です。
ただ、補助金によっては事業完了後も数年間にわたり事業の進捗状況や収益状況について、補助金の効果測定や適正な執行を確認するための報告が求められることもあります。
報告を怠ると後々弊害が出てくる可能性があるので、注意が必要です。
補助金申請における留意点
最後に、補助金申請における留意点について見ていきましょう。
申請書類の確認
補助金の申請においては、公募要領を熟読し、必要となる申請書類を漏れなく、かつ正確に準備することが極めて重要です。
申請書類に不備や不足があると、審査の対象とならなかったり、審査に時間を要したりする可能性があります。
とりわけ、事業計画書は審査において最も重視される書類の一つであり、事業内容やその効果、必要とする経費などを具体的に、かつ分かりやすく記載する必要があるでしょう。
資金計画の策定
多くの補助金は精算払いであるため、補助金が支給されるのは事業実施後になります。
ゆえに、事業に必要な資金を一時的に自己資金で賄うか、金融機関からの借入れなどで調達する必要があるなど、補助金を活用することを前提とした資金計画を策定しておくことが必要です。
補助金が入金されるまでの期間や金額を正確に把握し、資金繰りに問題が生じないように計画を立てることが求められるのではないでしょうか。
申請計画の遵守
採択された補助事業は、提出した事業計画に沿って忠実に実施することが必要です。
計画内容の変更が必要になった場合は、事前に事務局の承認を得なければなりません。
無断で計画を変更したり、補助金の使途を偽ったりするなどの不正行為は、補助金の返還命令や罰則の対象となる可能性があります。
申請期限の順守
補助金には、必ず公募期間と申請期限が設けられています。
この期限を過ぎてしまうと、いかなる理由があっても申請を受け付けてもらえません。
申請書類の準備には想定以上に時間がかかることもあるため、公募開始後速やかに準備に取り掛かり、期限に余裕をもって申請を完了させることが肝心です。
とりわけ、初めて申請する場合は何かと戸惑うこともあるので、早めに情報収集を開始し、計画的に準備を進めるのが良いでしょう。
まとめ
補助金と交付金は、どちらも国や地方自治体から支給される返済不要の資金であり、事業運営において大きな支えとなり得ます。
補助金と交付金の違いは、主にその目的と資金の流れにあります。
補助金は、中小企業や個人事業主の特定の事業活動を支援するものであり、交付金は、地方自治体が地域の行政サービスや事業を行うための財源として交付されるものです。
上記の違いを理解し、自社の状況や目的に合ったものを選ぶことが、効果的な資金調達の鍵です。
申請手続きには一定の時間と労力が必要ですが、適切に活用できれば、新たな挑戦や事業拡大の一助となるかもしれません。
まずは情報収集から始め、自社が活用できる補助金や交付金がないか調べてみてはいかがでしょうか。