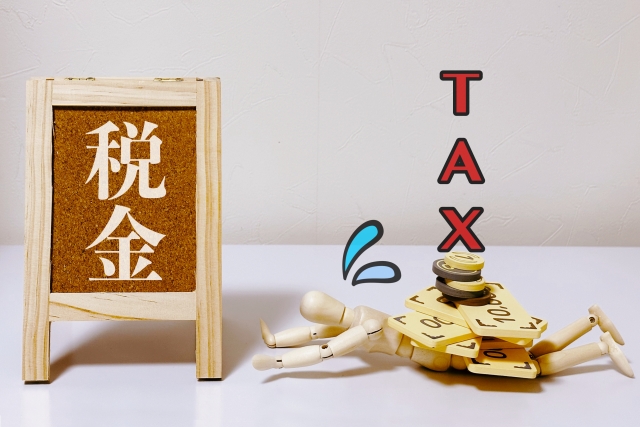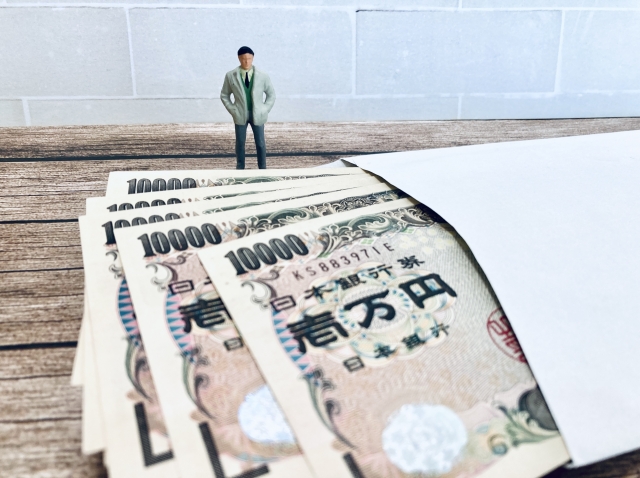毎日の仕事で辞めたいと思うことはないでしょうか?
筆者もブラック企業で働いていた時代は精神的に辛くて、毎日のように「仕事を辞めたい」と感じていた時期があったため、みなさんの気持ちはわかるつもりです。
ただ、いざ仕事を辞めたいと思っても、どう対応したら良いか迷うもの。
そこで、この記事では仕事を辞めたいと感じる理由、世帯・年代別の仕事に関する悩み、ストレスや苦痛を感じた時の対処法、辞める決断をする前のチェックポイント、辞める際のリスクや不安に向き合う方法、離職・転職の進め方、仕事を辞めたい時によくある質問と回答について詳しく解説します。
もし本当に仕事が辛いなら、辞める選択肢も考えてみませんか?
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶会社員に向いていない人の特徴とは?
▶なぜ「バイトに行きたくない・・・!」と思うのか?理由と対処法を紹介!
▶セミリタイアとは?アーリーリタイアとFIREとの意味の違いやリタイア後のビジネスをご紹介します

INDEX
仕事を辞めたいと感じる理由
まずは、仕事を辞めたいと感じる理由について見ていきましょう。
給与や報酬に対する不満
給与や報酬など、お金に関する不満も、仕事を辞めたいと考える理由の1つです。
働いた時間や成果に対して正当な給与が「もらえない」と感じたり、昇給やボーナスが見込めない状況では、仕事へのモチベーションを維持することが難しくなります。
また、現在の給与水準では日々の生活を維持することが困難であったり、貯金に回す余裕がなかったりする場合も、退職を検討するきっかけとなるわけです。
厚生労働省の調査でも、給与の低さを退職理由に挙げる人が決して珍しくないと示されており、経済的な要因が仕事選びに直結することがわかっています。
子供の面倒や両親の介護
結婚や出産、育児、家族の介護など、ライフステージの変化によって仕事と家庭の両立が難しくなり、仕事を辞めたいと考えるケースがあります。
子育て中は、子供の体調不良や行事などで急な休みが必要になることもあり、仕事との調整に負担を感じがちです。
共働き世帯の場合、夫婦間の家事や育児の分担、パートナーとの協力体制も必須です。
また、父親や母親の介護が必要になった場合、仕事の時間や働き方を見直さざるを得なくなることがあります。
人によっては、産後の体調の変化や育休中からの復帰後の環境の変化に戸惑い、仕事を続けることに困難を感じる場合もあるでしょう。
専業主婦(主夫)からの再就職の場合も、仕事と家庭のバランスに悩むことがあるのではないでしょうか。
仕事が合わない
仕事が合わないと「仕事を辞めたい」と考える理由の1つとなります。
自身のスキルや能力が求められる業務内容と一致しないミスマッチであったり、仕事の進め方や企業文化が自身の価値観と合わなかったりすると、辞めたいと思いがちです。
例えば、細かい作業が苦手なのに几帳面さが求められる部署に配属されたり、チームワークよりも個人での成果を重視する社風に馴染めなかったりするケースが考えられます。
このような状況では、業務をこなすこと自体に難しさを感じ、「できない」という思いが募り、結果として仕事のやる気が出ない状態に陥りやすいです。
また、仕事内容が自身の興味や関心とまったく異なる場合も、モチベーションの低下に繋がり、長期的に働くビジョンが見えにくくなる原因となるでしょう。
仕事内容が難しい・できない
仕事内容が自身のスキルや知識レベルに対して難しいと感じたり、何度取り組んでもできないという状況が続いたりすることも、仕事を辞めたいと考える理由になります。
新しい業務を覚えられないと感じたり、期待通りの成果が出せずうまくいかない状況が続くと自信を失い、仕事への苦手意識が強くなるのです。
十分なOJTやサポート体制がない職場で一人で問題を抱え込んでしまうと、孤立感を感じ、さらに辛い状況に追い込まれることがあるでしょう。
わからないことを気軽に聞ける雰囲気がない場合も、業務の習得を妨げ、できないという感情を助長させる可能性があるのではないでしょうか。
職場の価値観や社風のミスマッチ
職場の価値観や社風が自身の考え方と合わないことも、仕事を辞めたいと感じる理由の1つとなるかもしれません。
具体的には、成果主義で競争的な社風に馴染めなかったり、逆に年功序列で新しい意見が通りにくい環境に閉塞感を感じたりするケースが挙げられます。
会社が掲げる理念や方針が日々の業務に反映されていないと感じると、仕事への疑問や不満も蓄積しやすくなるのです。
また、普通だと感じていた働き方や人間関係が、企業の社長や上層部の考え方と異なり、理解を得られない状況もミスマッチに繋がります。
上記のような環境では、自身の意見やアイデアが受け入れられにくく、孤立感を感じることもあり、結果として退職を検討するきっかけとなるわけです。
責任やプレッシャーによる不安
仕事における責任の重さやプレッシャーによって感じる不安も、仕事を辞めたいと考える要因の1つではないでしょうか。
役職が上がったり重要なプロジェクトを任されたりすると、期待に応えなければならないという責任や失敗できないというプレッシャーを感じやすくなります。
責任感が過剰になると常に緊張状態が続き、精神的に疲弊しやすいです。
また、決断を迫られる場面で決断できないことへの不安を感じたり、もし失敗した場合の重圧を感じ、仕事への意欲が低下することも……。
体調不良や精神不安定による辛さ
仕事による体調不良や精神不安定による辛さは、退職を考える最も深刻な理由の1つです。
最近ではストレスが原因でうつ状態になったり、うつ病と診断されたり、環境の変化に適応できずに適応障害を発症したりするケースも珍しくありません。
身体的な症状としても、怪我をしたり、過敏性腸症候群のようにストレス性の胃腸の不調が出たりすることもあるでしょう。
毎朝、会社に行くのが辛いと感じたり、休日も仕事のことが頭から離れず休まらない状態が続く場合、心身が限界を迎えているサインではないでしょうか。
まずは自身の健康を最優先に考え、専門機関へご相談ください。
人間関係のストレス
職場の人間関係は、仕事を辞めたいと感じる主な理由の1つです。
具体的には、上司との関係がうまくいかなかったり、同僚とのコミュニケーションにストレスを感じたりすることが挙げられます。
理不尽な叱責や嫌がらせ、モラハラといった問題がある場合、毎日の出社が精神的な負担となり、イライラや苦痛を感じやすくなるのではないでしょうか。
また、チーム内の派閥や孤立感が人間関係のストレスに繋がることも……。
そうした場合、仕事内容自体に不満がなくても、職場の人間関係の悪化が原因で「辞めたい」という気持ちが強くなることも珍しくありません。
働きたくない・やる気が出ない状態
明確な理由はないものの「働きたくない」と感じたり「やる気が出ない」状態が続いたりすることも、仕事を辞めたいと考える背景にあります。
これらの感情は仕事内容に興味を持てなかったり、目標や「モチベーション」を見失ってしまったりすることで生じるもので、「何もしたくない」という気持ちになったり、仕事を楽しめなかったりするのが原因です。
むしろ、それは心身からの休息や環境の変化を求めるサインかもしれません。
モチベーションのない状態が続くと仕事のパフォーマンスが低下するだけでなく、自己肯定感も下がってしまう可能性があるからこそ、モチベの低下が一時的なものなのか、逆に根本的な原因があるのかを見極めることも必要となるでしょう。
評価されないことによる苦痛
自身の仕事の成果や努力が正当に「評価されない」と感じることはいずれ苦痛となり、仕事を辞めたいという気持ちに繋がります。
一生懸命取り組んだプロジェクトが認められなかったり、実績が給与や昇進に反映されなかったりすると、モチベーションが低下し、仕事へのやりがいを見失ってしまいがち。
上司の不明確な評価基準をはじめ、成果を横取りされるといった経験が不満や不信感を募らせる原因となることも珍しくないです。
評価されない状況が続くと、結果的に自身の存在意義や働く意味について疑問を感じるようになり、より評価される環境を求めるようになるのかもしれません。
労働時間(忙しすぎる・暇すぎる)
過度に忙しい状態が続いたり、長時間労働が常態化したりしている場合、体力的・精神的な負担が大きくなり、仕事を休みたいという気持ちや退職願望に繋がります。
慢性的な残業や休日出勤のある職場では、プライベートな時間を確保することが難しくなり、ワークライフバランスが崩れがちです。
逆に、極端に暇な時間が多く仕事が少ない状況が続くことも、自身の存在意義に疑問を感じたりスキルアップの機会が得られなかったりして、退職を考える理由となるでしょう。
繁忙期と閑散期の差が激しい職場も、定期的な働き方を見通しづらく、ストレスを感じる要因となるのではないでしょうか。
理不尽な扱いに対するイライラ
職場での理不尽な扱いは、イライラといった感情を引き起こし、仕事を辞めたいと感じる原因となります。
例えば、努力が正当に評価されずに不当な扱いを受けたり、根拠のない理由で怒られることが続いたりする場合、納得がいかず不満だけが募ります。
また、自分には非がないのにトラブルに巻き込まれたり、顧客からのクレーム対応を押し付けられたりすることも、理不尽さを感じさせる要因の1つです。
理不尽な状況に対して改善が見られない場合、より公平な環境を求めて退職を検討するのが普通です。
▼合わせて読みたい
会社員に向いていない人の特徴とは?
世帯・年代別の仕事に関する悩み
次に、世帯・年代別の仕事に関する悩みについて見ていきましょう。
新卒や20代が感じやすい悩み
新卒や20代の若い世代が仕事を辞めたいと感じやすい理由としては、理想と現実のギャップ、自身の能力への不安などが挙げられます。
入社前に抱いていたイメージと実際の業務内容や職場の雰囲気が異なったり、社会人としての働き方に馴染めなかったりするケースが顕著です。
ミスばかりして自信を失い、仕事の難易度に悩むことも珍しくありません。
また、初めての社会人経験で、人間関係の構築に戸惑ったり、上司や先輩とのコミュニケーションに難しさを感じたりすることも、ストレスの原因となります。
結果的に短期間での離職に抵抗を感じつつも、早期に環境を変えたいという気持ちが強くなることが珍しくないです。
30代・40代が直面しやすい悩み
30代・40代になるとキャリアや昇進、働き方の変化に関する悩みが多くなりがち。
例えば、35歳や39歳といった年齢を意識し、今後のキャリアパスや市場価値について不安を感じる方が少なくありません。
役職定年が見え始めたり、これまでのキャリアに行き詰まりを感じたりすることも、転職を検討するきっかけとなるでしょう。
30代後半からは管理職としての重圧や、後輩・部下との人間関係に悩むことも増えてくるのではないでしょうか。
また、子育てや親の介護など、家庭の事情と仕事の両立に難しさを感じ、働き方を見直したいと考える方も珍しくありません。
50代や中高年特有の悩み
50代が仕事を辞めたいと感じる背景には、体力的な衰えや健康問題、仕事内容へのやりがいの喪失、雇用に対する不安など、熟年層特有の課題があります。
長年勤めた職場での人間関係に疲れたり、役職定年などでモチベーションが低下したりすることも決して珍しくないことです。
59歳など定年が近づくにつれて、後のキャリアや生活設計に対する不安も拭えません。
新しいスキルや技術への適応に難しさを感じたり、若い世代とのジェネレーションギャップに悩んだりすることも、仕事を辞めたいと考える要因となるでしょう。
年齢を重ねることで金銭的な余裕ができたことで、時間に縛られない働き方を求めたり、趣味や地域活動に時間を費やしたいと考えたりする方もいるのではないでしょうか。
共働き世帯の悩み
共働き世帯の場合、仕事と家庭生活の両立に関する悩みが仕事を辞めたい主な理由。
夫や妻との家事・育児の分担、子供の病気や学校行事への対応など、家庭の事情と仕事のスケジュール調整に苦労することがあります。
仕事で疲れて帰宅しても休む間もなく家事に追われる状況は、心身ともに疲弊しても仕方ありません。
家族の理解や協力が得られない場合、一人で負担を抱え込み、孤立感を抱きやすいです。
経済的な理由から仕事を続ける必要性を感じつつも、精神的・肉体的な限界を感じ、家族との時間を優先したいという気持ちが強くなることもあるかもしれません。
派遣社員や非正規雇用の悩み
派遣社員や非正規雇用で働く人々は、雇用や収入の不安定さ、キャリアアップの難しさといった課題から仕事を辞めたいと感じることがあります。
派遣という働き方では、契約期間満了による雇い止めの不安がつきもの。
正社員と比較して給与水準が低かったり、昇給やボーナスがなかったりする場合も、経済的な不満に繋がりやすいです。
また、任される仕事内容が限定的であったり重大なプロジェクトに携わる機会がなかったりすると、自身のスキルアップやキャリア形成に限界を感じ、より安定した雇用形態の見込める職場へ転職を求めることがあります。
ストレスや苦痛を感じた時の対処法
ここでは、ストレスや苦痛を感じた時の対処法について見ていきましょう。
原因を整理して理由を書き出す
仕事でストレスを感じている場合、まずは原因を整理し、辞めたいと思う理由を具体的に書き出してみることが有効な対処法の1つです。
何に対してストレスを感じているのか、なぜそう感じるのかを客観的に考えることで、漠然とした不安や不満が明確になります。
例えば、業務内容、人間関係、労働時間など、ストレスの要因となっている事柄をリストアップしてみましょう。
これにより自身の問題が特定でき、それに対する具体的な対策を立てやすくなります。
もし、書き出してみても明確な理由がないという場合でも、自分の感情を紙に書き出すことで気持ちの整理に繋がり、モヤモヤとした感情の軽減に効果的です。
十分な休息を確保する
仕事で心が疲れてしまい、眠れない夜を過ごしている場合、心身の健康を回復させるために十分な休息が必須!
まずは、十分な休息を確保することを最優先に考えてください。
休職を検討したり、有給休暇を利用したりして心身を休ませるのが最優先。
どうしても眠れない場合は、寝る前にリラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりするなど、自分に合ったリラックス方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。
また、専門機関である心療内科や精神科に相談するのも良いです。
医師のアドバイスや具体的な診断を受けることで、適切な治療やサポートに繋がります。
専門医に相談する
仕事が原因で体調不良になったり、メンタル不調を感じたりしている場合、まずは自身の健康を最優先に考え、適切な対応を取るべきです。
うつ病や適応障害などの可能性がある場合は、早めに心療内科や精神科を受診し、診断書をもらうことをご検討ください。
診断書があれば会社に状況を説明しやすくなり、休むための手続きを進めやすくなります。
医師からの助言に従い、十分な休養を取ることが回復への第一歩。
無理をして働き続けることは症状を悪化させるだけでなく、回復を遅らせる原因となるからこそ、無理はしないようにしましょう。
知人や友人に相談する
周囲の人に相談することは、状況を改善することに繋がります。
身近な人であれば、家族をはじめ知人や友人、信頼できる同僚などがおすすめです。
もちろん、直属の上司や部下に相談してみても良いでしょう。
会社に直接関係のない人は、客観的な視点から助言してくれます。
状況の改善を求める場合は、直接人事担当者に相談しても良いです。
人事担当者は会社の状況を理解しているため、より具体的な解決策が見つかるのではないでしょうか。
他にもキャリアコンサルタント、公的相談窓口(総合労働相談コーナーなど)、産業医などに相談するのもあり。
- キャリアコンサルタント:キャリアや転職に関する悩みを相談できる
- 公的相談窓口:労働問題に関する相談ができる
- 産業医:面談にて直接相談できる
誰が良いかは自身の状況によって変わってくるので、まずは信頼できそうな人に相談してみてはいかがでしょうか。
リフレッシュを優先する
仕事を辞めたいと思ったら、リフレッシュを優先してください。
- 趣味の時間に没頭する
- 的確な運動やストレッチをする
- 適度な睡眠でストレス耐性を得る
- 夢を描いて現実逃避する
具体的には、趣味など好きなことに時間を費やして気分転換するのがおすすめです。
映画鑑賞や音楽鑑賞、漫画を読むことなど自分が心から楽しめる趣味であれば、よりストレスを緩和できます。
的確な運動やストレッチも、心身のリフレッシュに繋がります。
また、質の良い睡眠を確保することもストレス耐性を高めるために不可欠です。
眠れない人は、リラックスできる入浴剤を使ったり寝る前にカフェイン摂取を控えたりするなど、適度に睡眠環境を整える工夫をしてみましょう。
一時的に現実逃避にしかなりませんが、宝くじを買って「憧れの生活」を想像してみるのも良いかもしれません。
一見すると馬鹿げたことに思えても、現実から離れてみることで気分転換になることも珍しくありません。
ワークライフバランスを見直す
仕事によるストレスや疲労が大きい場合、自身のワークライフバランスを見直すことも忘れないようにしてください。
労働時間を見直し、残業を減らす努力をしたり、有給休暇を取得して休息する時間を増やしたりすることが重要です。
長期の休日を取ることで、心身ともにリフレッシュすることが大切と言えます。
休みたいという気持ちが強い場合は、休職するのも方法の1つ。
会社に休職制度があるか確認し、利用を検討してみましょう。
また、仕事とプライベートの切り替えを意識し、終業後や休日は仕事のことを忘れられる時間を持つことも肝心です。
プライベートとの両立に悩んでいる場合は、時短勤務やリモートワークなど、柔軟な働き方ができないか会社に相談してみることをおすすめします。
辞める決断をする前のチェックポイント
次に、辞める決断をする前のチェックポイントについて見ていきましょう。
本当に辞めるべき理由を整理する
仕事を辞めるという決断をする前に、まずは「本当に辞めるべき理由」を明確に整理することが重要です。
漠然とした不満や一時的な感情で辞めてしまうと、後で後悔する可能性があります。
なぜ今の仕事を辞めたいのか、根本的な原因は何なのかを深く掘り下げて考えましょう。
例えば、給与・仕事内容・人間関係・労働時間など、具体的な理由を書き出してみることで自身の置かれている状況を客観的に把握できます。
結果的に感情論ではなく論理的に退職の必要性を判断することが可能です。
自分で変えられることを見極める
仕事を辞めたいと感じる原因の中には、自身の行動や考え方を変えることで状況が改善されるものがあるかもしれません。
退職を決断する前に、今の職場で自分で変えられることはないか見極めることが大切です。
例えば、業務の進め方を工夫したり、コミュニケーションの取り方を変えてみたりすることで、ストレスが軽減される可能性があります。
上司に相談して業務内容の調整や部署異動を検討してもらうことも、環境を改善するための1つの方法。
自身のスキル不足が原因であれば、資格取得や研修参加など、自己啓発に取り組むことで、仕事への自信を取り戻せることもあるでしょう。
辞める以外の選択肢を持つことで、案外新たな発見にも繋がるのではないでしょうか。
相談や話し合いで解消できるか見直す
仕事で抱える悩みや不満の中には、役員との相談や話し合いで解消できる場合があります。
退職を決断する前に、まずは会社の相談窓口を利用したり、信頼できる上司や先輩に状況を話してみたりすることをご検討ください。
自身の抱える問題を具体的に伝えることで、部署異動の提案や業務内容の調整など、改善策を見つけましょう。
人間関係の悩みであれば、間に立ってもらったり、円滑なコミュニケーションの方法について助言をもらえたりすることもあるでしょう。
問題が個人的な感情によるものなのか、それとも職場環境に根本的な問題があるのかを見極めるためにも、一度周囲に相談してみてはいかがでしょうか。
お金やローン、生活面の準備
仕事を辞めるということは、安定した収入が一時的になくなることを意味します。
退職後の生活に困らないよう、お金やローンに関する準備は重要です。
具体的に当面の生活費としてどれほどのお金が必要か計算し、準備することが大切です。
同時に、失業保険の受給額や受給期間についても確認しておくことをおすすめします。
ローンの返済や固定費(家賃・水道光熱費・通信費)についても把握し、収入がない期間も支払いが可能かシミュレーションしておくことが欠かせません。
生活できないといった状況に陥らないためにも、退職後の生活資金計画を立てておくことを忘れずに!
必要に応じて、家計の見直しや支出の削減もやっておくと安心かもしれません。
次の仕事やキャリアの計画
仕事を辞めることを決断したら、次の仕事やキャリアについて考える必要があります。
転職を考えている場合は、どのような業界や職種に興味があるのか、自身のスキルや経験が活かせるのはどのような仕事なのかを明確にしてください。
納得のいく転職先を見つけるためには、自己分析を行い、自身の強みや弱み、価値観を理解しておくことも必要です。
転職活動のスケジュールを立て、情報収集や応募書類の用意、面接対策などを計画的に進めつつ、働きながら転職活動を行うのか、あるいは退職してから転職活動に専念するのかについても考えておきましょう。
また就職に失敗しないよう、転職後のキャリアパスについても具体的にイメージしておくのがGOOD!
辞める際のリスクや不安に向き合う方法
次に、辞める際のリスクや不安に向き合う方法について見ていきましょう。
年収への影響を考えておく
仕事を辞めると、今後の年収に影響が出ます。
退職前に、失業保険はどの程度受給できるのかなどを具体的に計算しておくことは大切ですが、就職後の年収への影響についても考えておくべきです。
転職先が決まったとしても、以前の職場より年収が下がる可能性も考慮に入れ、限られた収入でも生活できるよう支出を抑えておくのが安心かもしれません。
もしもに備えて、ある程度の貯金をしてから退職するのもあり。
パートナーの理解を得る
仕事を辞めるという人生を左右する可能性のある決断をする場合は、パートナー(夫・妻・彼女・彼氏)の理解を得ることが必要です。
自身の悩みや退職を考え始めた理由、そして退職後の具体的な計画について正直に話し、理解を得ることでサポートを受けられるかどうかが決まります。
特に、生計を共にしている場合は経済的な影響や今後の生活についてしっかりと話し合い、協力を得る必要があるでしょう。
パートナーのサポートがあることで精神的にも肉体的にも支えとなり、安心して転職活動に取り組むことができるからこそ、時間をかけて丁寧に説明し、一緒に今後のことを考えていく姿勢を見せるのが良いのではないでしょうか。
無職・転職活動中の不安対策
無職の期間が長引いたり、転職活動中に不採用が続いたりすると不安を感じるものです。
真面目な人ほど自分を責めてしまい、精神的にも肉体的にも追い詰められます。
人によっては無職・転職活動中にうつ病や適応障害を発症することもあるため、自身の心の健康状態には十分に注意を払いましょう。
不安を軽減するためには一人で抱え込まず、家族や友達、転職エージェントなどに現在の状況や気持ちを話してみてください。
また、仕事探しに集中しすぎるだけでなく適度に休息を取ったり、趣味やリフレッシュになる活動を取り入れたりすることも大事です。
運動やバランスの取れた食事も、気分の安定に繋がります。
迷惑になることを恐れない
仕事を辞めると「他の人に迷惑をかけてしまうかもしれない」と考える人もいますが、迷惑をかけることに関しては恐れなくて良いです。
担当している業務やプロジェクトがある場合、引き継ぎが間に合わないのではないか、後任者に負担をかけてしまうのではないかといった不安を感じるものですが、自分がいなくなればいなくなったで職場もどうにかします。
自身の心身の健康を損なってまで働き続ける必要はありません。
退職の意思を早めに伝え、会社の規定に基づいた手続きを踏むことで、会社側も後任者の手配や引き継ぎの準備をする時間を確保できます。
責任感を持つことは素晴らしいですが、うつ病や適応障害にならないよう自分の健康や将来を優先する勇気も必要です。
必要であれば、上司や先輩に引き継ぎ方法や退職までの業務について話し合ってみてはいかがでしょうか。
▼合わせて読みたい
脱サラとは?独立のための案件探しの方法を解説します!
離職・転職の進め方
次に、離職・転職の進め方について見ていきましょう。
STEP1.辞めたい理由を明確にする
離職や転職を成功させるためには、まず辞めたい理由を明確にする必要があります。
なぜ今この職場を離れたいのか、その根本的な原因を具体的に特定しましょう。
給与・仕事内容だけでなく、自分が抱えている不満や不安を感じる点をリストアップしてください。
こうすることで、次に求めるべき職場環境や転職先に求める条件が明確になります。
面接時にも退職理由を具体的に説明する必要があるため、自身の言葉でその理由を話せるよう整理しておくことが大事です。
STEP2.退職理由を上司へ伝える
退職の意思を上司に伝える際は、伝え方が重要です。
まずは直属の上司にアポイントを取り、退職の相談をする時間を設けてもらいましょう。
退職の意思は相談ではなく決定事項として、伝えることがスムーズな手続きに繋がります。
なお、退職理由を伝える際は、ネガティブな理由や会社への不満を正直に伝えすぎるのは避け、ポジティブな理由に言い換えるのが円満退職のコツです。
例えば「キャリアアップを目指したい」「他に挑戦したい仕事が見つかった」など、自身の前向きな意志をお伝えください。
具体的な言い方は、以下の通り。
| 「株式会社〇〇には大変お世話になりましたが、この度一身上の都合により退職させていただきたく、ご相談させていただきました。 退職の意向はすでに決まっており、〇月〇日をもちまして、退職させていただきたく思います。 ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただけると幸いです。」 |
以上のように丁寧な言葉遣いを心がけると良いです。
急に当日伝えたり、すぐに辞めたいと一方的に伝えたりするとトラブルになる可能性があるので、極力早めに伝えることをおすすめします。
STEP3.エージェントやハローワークを活用する
離職や転職活動を進める上で、エージェントやハローワークといった外部サービスを活用することは非常に有効です。
- エージェント
⇒求職者の経歴や希望に合った求人を紹介してくれる
⇒履歴書の添削や面接対策、条件交渉などもサポートしてくれる
⇒業界に精通したキャリアアドバイザーから専門的なアドバイスを受けられる - ハローワーク
⇒無料で職業相談や求人紹介を受けられる
⇒地域に密着した求人情報が豊富に揃っている
⇒雇用保険の手続きなども行ってもらえる
⇒職業訓練の情報も集められる
エージェントもハローワークも仕事探しでは心強い味方となってくれるからこそ、活用しない手はありません。
▶︎合わせて読みたい
CAREE|転職・就職を応援するWEBメディア「求人サイト比較研究所」
STEP4.タイミングを見極める
転職活動を始めるタイミングは、自身の状況や希望する業界・職種によって異なりますが、一般的に求人が増える傾向にある時期などを参考に計画を立てると良いでしょう。
多くの企業で人員の入れ替えがある年度末や期末(3月〜4月・9月〜10月)は求人が増える傾向にあります。
退職の意思表示は、就業規則にもよりますが、2週間前あるいは1ヶ月前までに直属の管理者に伝えるのが理想です。
引き継ぎなどを考慮すると3ヶ月程度の余裕を持って伝える方が円満退職に繋がりやすいのではないでしょうか。
ただ、半年(6ヶ月)といった長期的な準備期間を設けることも可能です。
経験を積み、1年あるいは2年目、3年目といったタイミングで転職を考える人もいます。
STEP5.引き継ぎや退職手続きを進める
退職が決まったら、後任者への引き継ぎと会社所定の退職手続きを進めます。
まずは直属の管理者と相談し、退職日を決定します。
就業規則を確認し、退職の意思表示を行う期日や手続きについて把握しておきましょう。
業務の引き継ぎは、後任者がスムーズに業務を行えるよう、担当業務の内容や進捗状況、取引先情報などをまとめた資料を作成し、丁寧に説明を行うと良いです。
必要に応じて、引き継ぎ期間中に質疑応答の時間を設けてください。
会社からは離職票や源泉徴収票など、退職後の手続きに必要な書類の受け取りも忘れずに。
なお、健康保険や年金、雇用保険に関する手続きも自身で行うことが必要です。
例外:退職代行サービスを頼る
直接退職の意思を伝えることが難しい場合、退職代行サービスの利用も選択肢の1つ。
退職代行サービスは、本人の代わりに会社に退職の意思を伝えてくれるサービスです。
最近では、退職代行サービスを利用する人も結構な数がいます。
利用する時はまず、サービス提供業者の種類(弁護士・労働組合・民間業者)と、それぞれができること・できないことを理解しておく必要があります。
弁護士や労働組合が運営するサービスは、職場との交渉(有給休暇の消化や未払い賃金の請求など)が可能ですが、民間業者は交渉権がない点に注意が必要です。
依頼する場合は、料金体系やサービス内容、実績などを比較検討し、信頼できる業者をお選びください。
なお、急に退職代行を利用した場合、会社から引き止められる可能性や後任への引き継ぎが十分にできないといった問題が生じる可能性もあります。
法律上は退職の意思表示から2週間で雇用契約が終了しますが、円満退職を目指す場合は、ある程度の引き継ぎ期間を設けることも考慮に入れると良いです。
うつ病や適応障害などで職場に行けなくなった人も、退職代行サービスをご活用ください。
仕事を辞めたい時によくある質問と回答
最後に、仕事を辞めたい時によくある質問と回答について見ていきましょう。
「もう仕事辞めたい」は甘え?
「もう仕事辞めたい」と感じる気持ちが、甘えなのではないかと悩む人もいます。
ただ、仕事によるストレスや心身の不調は、決して甘えではありません。
多くの人が仕事に対して辛いと感じたり、辞めたいと考えたりすることは普通のこと。
厚生労働省の調査によると、少なくとも9割以上の人が仕事に対し「辛い」「辞めたい」という感情を抱いているという結果もあるくらいです。
仕事辞めたいと考えるのはみんな同じ?
「仕事を辞めたい」と考える経験は、みんな同じように一度は通る道と言えるでしょう。
実際にたくさんの人が仕事に対して何らかの不満やストレスを感じています。
現に、9割以上の人が仕事に対して不穏な感情を抱いており、日本はまだまだ異常な労働環境となっている職場も珍しくないです。
「みんな同じ」と言うと語弊があるかもしれませんが、仕事を辞めたいと感じるのは決して珍しいことではありません。
休みたい場合はどうする?
疲労やストレスで「休みたい」と感じたら、休むのが一番!
まずは、産業医や直属の上司に現在の心身の状態についてご相談ください。
心療内科や精神科を受診し、医師の診断書をもらえば休職も難しくありません。
診断書には、病名や休養が必要な期間などが記載されます。
可能であれば、会社に休職制度があるか確認し、申請方法や期間中の給与・税金・保険料の扱いなどについて企業の規定や就業規則の確認が必須。
なお、休職期間中は治療に専念し、心身の回復を図ることが大事です。
復職のタイミングについても、医師と相談しながら慎重に判断しましょう。
まとめ
仕事を辞めたいと感じることは、多くの方が経験するものです。
その背景には色んな原因や理由がありますが、まずは一人で抱え込まず、自身の状況を整理して適切な対処法を試みることが大事と言えます。
今すぐ辞めることは簡単ではないかもしれませんが、どうしても心身の限界を感じているのなら辞めてしまっても問題はありません。
ただ、生活に困窮する可能性があるため、退職を決断する前には、本当に辞めるべきか冷静に判断し、将来の計画や生活資金の準備をしっかりと行うことが重要です。
辞めることだけが解決策ではないので、直属の管理者に相談することも大切と言えます。
まずは自身の心身の健康と、あなたがより良く働ける環境を見つけられるよう、自分の心の声に従ってみてはいかがでしょうか。