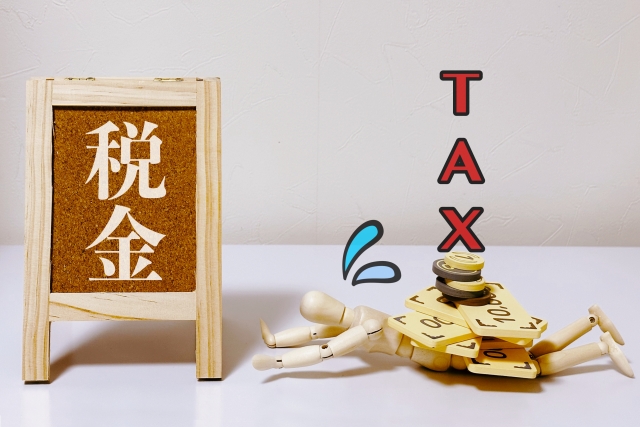近年、多くの企業でオンライン会議が当たり前になっています。
しかし、「商談がスムーズに進まない」「取引先との打ち合わせが中途半端に終わる」「ウェビナーで視聴者の反応が薄かった」など、オンライン会議が予定調和に進まないことに悩む声も増えています。
そこで今回は、なぜオンライン会議がグダグダになってしまうのか、その理由と失敗しない進行術について解説します。
失敗を回避し、オンライン会議を成功に導くためにはどうすればよいのか、一緒に考えていきましょう。

オンライン会議が上手くいかない主な理由
オンライン会議がスムーズに進まない背景には、いくつかの共通する課題があります。
商談や取引先との打ち合わせにせよ、ウェビナーにせよ、成功するオンライン会議には進行術が欠かせません。
ここでは、よくある問題点を具体的に解説していきます。
- 目的やアジェンダの不明確さ
オンライン会議が失敗する最大の理由の一つが「会議の目的」や「アジェンダ」が不明確であることです。
不明確な会議では、誰もが何を話し合うのか分からず、議論が脱線したり、結論が出ないまま終了することが多々あります。
特に商談や取引先との打ち合わせでは、要点が曖昧だと信頼を損ないかねません。
明確な目的設定とアジェンダの共有が会議成功の鍵となります。
- 参加者の準備不足
会議の参加者が事前に資料を確認していない、あるいは必要な準備をしていない場合、進行がスムーズにいきません。
このような状況では、司会者が1から説明する時間が必要となり、他の参加者の集中を途切れさせてしまうことも。
ウェビナーなどでも、この点が視聴者の満足度を下げる要因になり得ます。
- 技術トラブルとその影響
オンライン会議ならではの課題として、「音声が途切れる」「画面共有ができない」といった技術トラブルがあります。
特に商談や取引先との重要な会議の際にこれらが起きると、相手に悪い印象を与える可能性も。
進行が滞り、参加者全員の集中力を削ぐ原因になります。
- 発言のバランスが取れていない
一部の人が発言を独占してしまう一方で、発言の少ない参加者がいる場合、オンライン会議の全体的なバランスが崩れてしまいます。
ウェビナーでは特に、参加者に発言の機会を適切に与える進行術が重要です。
このバランスの欠如は、議論の質を低下させる要因となります。
- タイムマネジメントの失敗
時間配分が上手くいかないことも、オンライン会議がグダグダになる大きな理由です。
話し合いが進むにつれ予定された時間を超過したり、重要な議題が十分に議論されないまま終了したりします。
商談や取引先との打ち合わせでの時間管理の失敗は、プロフェッショナルさを欠いた印象を与えてしまうため特に注意が必要です。
グダグダにならないための準備ステップ
オンライン会議を成功させるには、事前の準備が最も重要です。特に商談や取引先との打ち合わせでは、周到な準備を行うことで、参加者にプロフェッショナルな印象を与えることができます。
また、ウェビナーのような多数の参加者を伴う会議の場合も、事前に万全の準備を整えることでスムーズな進行につなげることができます。
会議の目的を明確に設定する方法
会議の成功は、その目的が具体的で明確であるかどうかに大きく左右されます。
目的を設定する際には、以下の3つのポイントを意識しましょう:
- 会議のゴールを設定する:
その会議で何を達成すべきかを明確にしましょう。
例えば「事業提携の詳細を決定する」や「商品の具体的な改善提案を受け取る」といった具体的な成果です。
- 会議が必要なのかを検討:
目的を整理する中で「そもそも会議が必要か?」を考えます。
一部の議題はメールやチャットで簡潔に解決できる場合もあります。
- 参加メンバーを選定:
会議に必要な情報やスキルを持つ適切な人を招集しましょう。
参加者が多すぎると議論が薄まり、少なすぎると議題の解決が難しくなります。
目的が明らかであれば、会議の方向性を失うことはありません。
事前アジェンダとリマインダーの重要性
アジェンダの事前共有は、オンライン会議を成功させるための基本です。
議題を事前に知らせておくことで、参加者は必要な準備がしやすくなると同時に、会議がスムーズに進みます。
効果的なアジェンダ作成とリマインダー活用のポイントをご紹介いたします。
- アジェンダの作成:
各議題ごとに話し合う内容と、それにかける時間を明記しましょう。
「10:00〜10:15 商品改善の現状確認」のように具体的に記載することが重要です。
- 事前共有:
会議の2〜3日前(場合によっては1週間前)にアジェンダを共有し、参加者が準備できるようにします。
- リマインダーの活用:
会議当日や前日にリマインドを送り、参加者に時間やツールを再確認してもらいましょう。
これにより、準備不足を防ぐことができます。
必要なツールと技術チェックのポイント
ウェビナーや重要な商談では、技術的な不具合を防ぐことが必要不可欠です。
以下は事前に確認しておくべきポイントの例です:
- ネットワークの安定性:
会議を行う場所でのインターネット接続が安定しているか確認します。
可能であれば、有線接続を使用するのがおすすめです。
- ツールの操作確認:
Zoom、Google Meet、Teamsなど、使用するオンライン会議ツールを事前にテストしておきましょう。
特に画面共有や録画機能の必要性がある場合は事前に確認が必須です。
- バックアップツールの用意:
万一のトラブルに備え、サブのデバイスや代替プラットフォーム(例:Skypeや電話)を用意しておくと安心です。
- 音声や映像機器の確認:
マイクやカメラが正常に動作しているか、必ず事前にテストしてトラブルを避けましょう。
これらの準備を怠ると、会議の進行中に思わぬ混乱を招いてしまうことがあります。
失敗しないオンライン会議の進行術
オンライン会議を成功させるためには、進行役のスキルが重要です。
商談、打ち合わせ、取引先との会議、そしてウェビナーなど、どの場面でもスムーズかつ生産的な進行が求められます。
以下では、具体的な進行術とコツをご紹介します。
効果的な司会進行のコツ
司会役がしっかりと会議を仕切ることで、グダグダになりがちなオンライン会議も効率的に運営できます。
- 冒頭での目的確認:
会議の最初に、全参加者に対して「会議の目的」や「話し合うべき内容」を簡潔に共有しましょう。
これにより会議の軸がぶれず、全員が同じ認識を持ちやすくなります。
- 発言順序を明確にする:
一人が話し終わった後に「次に○○さんお願いします」と指示を出すことで、議論の流れが途切れることを防ぎます。
- 定期的に要約する:
一定のトピックが終わるたびに「ここまでの内容を簡単にまとめると…」と要約を入れると、話が進行状態を確認しやすくなります。
発言を活性化するテクニック
オンライン会議では、対面よりも発言が偏りやすく、一部の人だけが話す傾向が強くなりがちです。
以下の方法で、参加者全員の意見を引き出しましょう。
具体的な質問の投げかけ方
具体的な質問を投げかけることで、有用な議論が活性化されます。
例えば:
- 「商品改善案について、現時点で可能性が高いと思うものは何でしょうか?」
- 「次回に向けて重点的に進めたい事項について、意見をお聞かせください。」
また、Yes/Noで終わらず、理由を求める形式の質問を使うことで、議論が深まります。
参加者全員を巻き込む仕掛け
発言が少ない参加者を巻き込むには、積極的に名前を呼びかけることが効果的です。
例えば:
- 「○○さん、この案についてはどのようにお考えですか?」
- 「△△さんの分野では大きく関わる内容だと思いますが、意見をいただけますか?」
また、小人数のミーティングではブレイクアウトルーム機能を使用するのも有効手段です。
時間管理の徹底方法
進行役は時間管理を徹底することが求められます。
時間を守ることで、参加者全員への信頼感を高め、プロフェッショナルな会議運営が可能になります。
タイマーや進行表の活用方法
会議の開始時に、全体のタイムスケジュールを簡単に発表しましょう。
そして、進行時に明確なタイマーや進行表を使用します。
例えば:
- 「10:00〜10:15:前回会議の振り返り」
- 「10:15〜10:30:新しい議題の討議」
タイマーアプリを使いながら進行すると、一目で時間配分を確認できます。
中だるみを防ぐための工夫
長時間のオンライン会議では、参加者の集中力が低下しやすくなります。
これを防ぐためには:
- 1時間ごとに短い休憩を挟む(5〜10分)
- 場合によっては、リフレッシュを兼ねた軽い質問や雑談を挟む
これにより、参加者は疲れを軽減し、集中力を維持しやすくなります。
オンライン会議特有の問題対策
オンライン会議では、対面の会議では見られない特有の問題が発生しがちです。
商談や取引先との打ち合わせ、ウェビナーの場でも、これらの問題に適切に対応することでスムーズな進行が可能になります。
ここでは、よく発生する問題とその解決策を紹介します。
技術トラブルへの即時対応策
オンライン会議では、音声や映像、接続に関する技術トラブルが発生することが避けられません。
対策として、会議前の準備だけでなく、問題発生時の対応策を事前に整えておくことが重要です。
- バックアッププランを準備:
接続が切れた場合に備えて、サブのコミュニケーション手段(電話や別のオンラインツール)を事前に共有します。
- 技術担当の配置:
大規模な商談やウェビナーでは、トラブルの際に迅速対応できる人をあらかじめ決めておきましょう。
- 事前チェックの徹底:
ツールの動作確認やネット環境の安定性を会議開始前に確認しておきます。
定期的に社員向けのツール操作トレーニングを実施するのも有効です。
背景雑音や通信環境への配慮
周囲の音や通信環境の影響によって、発言が聞き取りにくくなったり会議の質が低下することがあります。
これを防ぐためには次の手段を取り入れると良いでしょう。
- ノイズキャンセリング機能を活用:
音声トラブルを軽減するため、マイクやオンラインツールのノイズキャンセリング機能を活用します。
- 静かな環境を確保:
可能な限り、背景雑音の少ない部屋を選ぶか、会議参加者に配慮をお願いしましょう。
- 発言時以外はミュート:
話していない時にミュートを心がけたり、司会者が全体ミュートを促進することで、不必要なノイズを排除します。
カメラオン/オフ問題の解消策
オンライン会議ではカメラのオン/オフ問題が議論されることが多いです。
一部の人がカメラをオフにしていると、会議に対する参加意識の低下や信頼感を損なう原因にもなり得ます。
- カメラオンのルール設定:
重要な商談や取引先との打ち合わせでは、できるだけ全員がカメラをオンにするルールを設けましょう。
その際、背景はバーチャル背景や適切な環境にするよう事前に依頼します。
- 参加者の自由を尊重:
場合によってはカメラオンにプレッシャーを感じる方もいるため、必須とする会議とそうでないものを使い分ける柔軟性が必要です。
- 非言語表現の確認:
カメラのオンが難しい場合でも、絵文字リアクションやチャット機能を積極的に活用することで、非言語的なコミュニケーションを補完できます。

成功するオンライン会議の事後対応
オンラインでの会議は、その場での進行がスムーズであっても、終わった後の対応次第で成果を最大化できるかが決まります。
商談や取引先との打ち合わせからウェビナーまで、会議後に正しいフォローを行うことで、次に繋げる効果的なアプローチが可能になります。
議事録の作成と共有のポイント
会議終了後は、議事録を作成し、速やかに共有することが求められます。
特に商談や取引先の打ち合わせでは、内容の認識相違を防ぎ、信頼感を高めるためにも議事録は不可欠です。
- 要点に絞ってわかりやすくまとめる:
各議題ごとに「何が話し合われたか」「次に何をするべきか」を簡潔に整理します。
- 責任者と期限を明記:
アクションアイテムには担当者と締め切りを明記し、関係者が把握しやすい形で共有しましょう。
- フォーマットを統一:
議事録のフォーマットを統一することで、誰でも一目で伝わる記録になります。見やすい箇条書きや表などを使うと効果的です。
- 共有のタイミング:
会議終了後、なるべく早く参加者全員に送付することで熱が冷めないうちに次の行動につなげます。
現在では会議にアプリケーションを参加させることでAIで議事録をまとめてくれるツールやオンライン会議自体を録画することも可能となりました。
すぐに共有することが出来るため、自分達に合った効率的な議事録の取り方をぜひ探してみましょう。
フィードバックを活用して次回改善に繋げる方法
オンライン会議の質を向上させるためには、参加者からフィードバックを収集し、実際に次回の会議に反映させることが重要です。
- 簡単なアンケートの実施:
Googleフォームや任意のツールを使って、会議について簡単なアンケートを実施します。
例として、「議事の進行速度」「議論の充実度」「雰囲気」などについて意見を聞くと効果的です。
- 評価項目の具体化:
漠然とした感想ではなく、「アジェンダの分かりやすさ」「適切な時間配分」「ツールの使いやすさ」といった具体的な項目を設けましょう。
- 次回のアクションに反映:
フィードバックで指摘された点や改善を求められた内容を整理し、次回の会議やウェビナーにおいて修正を加えます。
参加者が「今回の会議で得たことが次回に反映される」と感じることで、会議全体への満足度が向上します。
準備や進行を意識することで、オンライン会議の質を向上させ、グダグダになる事態を事前に防ぐことが可能です。
顧客や取引先にも信頼感を与えられる進行術を実践して、スムーズな会議運営を始めてみてください!