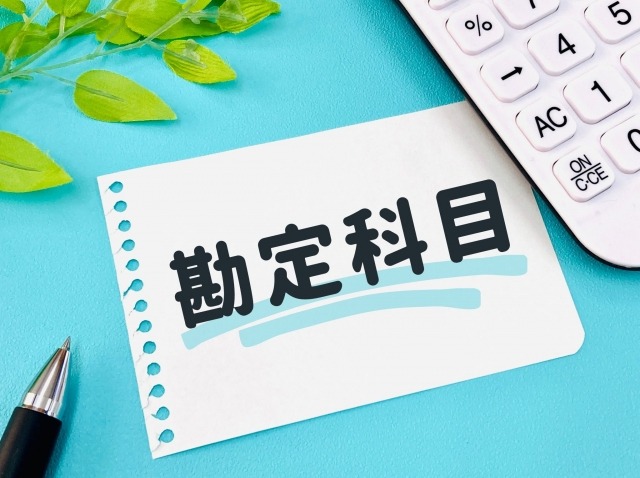会社を設立するには、具体的な流れを知っておくことが重要です。
会社設立の方法を理解し、正しい手順で進めることで、社会的信用の向上や資金調達の選択肢の拡大、節税対策など様々な恩恵を享受できるでしょう。
この記事では、会社設立の全体像を把握し、具体的な手続きや費用、その後の流れを詳しく解説します。
💡この記事を読まれている方におすすめの記事💡
▶仕入先とは?選定の基準や開拓方法を紹介!
▶新規事業の立ち上げのプロセスや進め方の解説!新規事業の探し方の例も紹介
▶開業資金の集め方!起業にはいくら必要?ノウハウを得ながら収入を得るお得な貯め方もご紹介!

INDEX
【6ステップで解説】株式会社設立の具体的な手順
株式会社を設立する具体的な手順は、大まかに6つのステップで進めることが可能です。
ここでは、それぞれのステップで何をすべきか、必要な手続きや書類などを詳しく解説していきます。
ステップ1:会社の基本事項(商号・事業目的など)を決定する
会社を設立する最初のステップは、会社の基本事項を決定することにあります。
会社の名称である「商号」、どのような事業を行うのかを具体的に示す「事業目的」、会社の所在地である「本店所在地」、事業の元手となる「資本金の額」、そして会社の事業年度の締め日である「決算期」などを決めることが重要です。
上記の事項は、定款に記載され、会社の根幹となる重要な要素となるため、慎重に検討し決定しましょう。
なお、事業目的は将来的に行う事業も考慮し、具体的に記述することが重要です。
現段階で想定しうる事業内容を記載しておくとより方向性が明確になります。
ステップ2:法人用の印鑑(会社実印)を作成する
会社の基本事項が決定したら、法人用の印鑑(会社実印)を作成します。
会社実印は、法務局への登記申請や契約書への押印など、会社の重要な場面で必要となる印鑑です。
一般的には、会社実印の他に、法人口座の開設に使う銀行印や、請求書などに押印する角印(社判)も併せて作成することが多いでしょう。
なお、印鑑の作成費用は素材によって異なりますが、セットで数千円から数万円程度が相場となるため、予算に併せて選びましょう。
印鑑は会社設立の手続きに欠かせないものだからこそ、準備は迅速に進めましょう。
ステップ3:会社の憲法となる「定款」を作成・認証する
会社の基本事項が固まり、法人印鑑も準備できたら、次は会社の憲法とも呼ばれる「定款」を作成するのが一般的です。
定款には商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、発起人の情報などを記載します。
株式会社の場合、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。
なお、上記の認証手続きには資本金の額に応じて1万5,000円から5万円の認証手数料と謄本代として2,000円程度の費用がかかるのですが、電子定款を利用すれば印紙代4万円を節約可能(専用の機器やソフトが必要)です。
定款は会社の重要な規約となるため、不備がないように正確に作成しましょう。
ステップ4:発起人の個人口座へ資本金を払い込む
定款の作成と認証が完了したら、次に資本金の払い込みを行います。
資本金は、会社の設立時に発起人が出資金として、発起人代表の個人口座に払い込みます。
同時に金融機関名、口座番号、支店名などが記載された通帳のコピーなど、払込が確認できる書類が必要です。
資本金は会社の信用度や事業規模を示す重要な要素で、1円からでも設立は可能ですが、取引先や金融機関からの信用を得るためにある程度の金額を用意することが一般的です。
ステップ5:法務局へ提出する登記申請書類を準備する
資本金の払い込みが完了したら、法務局へ提出する登記申請書類の準備に取りかかります。
必要な書類は多岐にわたりますが、主に「株式会社設立登記申請書」のほか、認証済みの定款、発起人の同意書、設立時取締役の就任承諾書、資本金の払い込みを証明する書面、発起人の印鑑証明書、印鑑届書などが必要です。
上記の書類に不備があると登記申請が受理されないため、正確に作成しましょう。
もし初めての会社設立で何をすれば良いかわからない場合は、オンラインの会社設立支援サービスなどを活用すると良いでしょう。
ステップ6:法務局で設立登記を申請し、登記完了を待つ
登記申請書類を準備したら、会社の所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。
登記申請を行うことで会社は法的に存在を認められ、会社設立日が確定します。
申請後、不備がなければ通常1週間から2週間程度で登記完了です。
登記が完了すると法務局から登記完了証が発行され、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書を取得できるようになるため、着実に進めておきたいところです。
これらの書類は、その後の様々な手続きでも必要となるため、複数枚取得しておくと良いでしょう。
法人化によって得られる5つのメリット
ここからは、法人化によって得られる5つのメリットについて見ていきましょう。
個人事業主より社会的信用度が高まる
会社を設立し法人化すると、個人事業主と比較して、事業の社会的信用度が向上するというメリットがあります。
法人登記されることで、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなるため、新たなビジネスチャンスの獲得や有利な条件での取引が可能になる場合があります。
これは、会社が法的に独立した存在として認められ、事業に対する責任体制が明確になるためです。
特に、大企業との取引や多額の資金を伴う契約を締結する際には、法人の形態であることが求められるケースも珍しくないです。
所得税や相続税などの節税につながる
法人化は、所得税や相続税の節税につながる可能性があります。
個人事業主の場合、所得が増えるほど所得税率が上がる累進課税が適用されますが、法人税は税率が一定です。
そのため、事業所得がある程度の金額を超えると、法人化した方が税負担を軽減できるでしょう。
また、法人化することで経費として認められる範囲が広がり、役員報酬や退職金などを損金算入できるため、課税所得を圧縮し、結果的に節税効果が期待できます。
一般的には、個人の所得が700万円を超えたタイミングで会社設立を検討するケースが通例です。
事業上の責任範囲が限定される(有限責任)
株式会社を設立した場合、出資者は有限責任となり、会社が倒産した場合でも、原則として出資した金額以上の責任を負う必要がありません。
上記は、個人事業主が事業上の負債に対して無限責任を負うのとは対照的です。
つまり、万が一事業が失敗しても個人の財産まで債務の弁済に充てられるリスクを低減できるため、安心して事業に専念できることを意味します。
融資や出資など資金調達の選択肢が広がる
法人化することで、融資や出資など、資金調達の選択肢が広がります。
個人事業主に比べて社会的信用を得やすいため、銀行などの金融機関からの融資を受けやすくなるほか、ベンチャーキャピタルからの出資や、株式を発行して資金を調達するといった方法も可能です。
上記に関しては、事業規模の拡大や新たな事業展開を考える上で非常に魅力的なファクターと言えるでしょう。
経営者も社会保険に加入できる
法人を設立すると、経営者自身も社会保険(健康保険や厚生年金保険など)に加入することが義務付けられます。
個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金に加入するのが一般的ですが、法人化することで、手厚い保障を受けられる社会保険に加入できるのも魅力です。
社会保険料は会社と従業員(役員含む)で折半して負担するため、個人で全額負担する国民健康保険・国民年金に比べて、将来の保障や万一の際の安心感が得られるでしょう。
会社設立前に知っておきたい3つのデメリット
ここでは、会社設立前に知っておきたい3つのデメリットについて見ていきましょう。
設立手続きに時間とコストがかかる
会社を設立するには、法務局への登記申請をはじめとした様々な手続きが必要です。
手続きには書類作成の手間や、定款認証手数料、登録免許税などの費用が発生します。
仮に株式会社の場合、設立費用として約22万〜24万円程度、合同会社の場合でも約10万円程度が目安とされており、個人事業主として開業するよりも初期コストがかかる点が難点です。
また、手続きに慣れていない場合は時間も要するため、事業準備に充てる時間が圧迫されることもあります。
赤字の場合でも法人住民税の支払いが必要
法人化すると、たとえ事業が赤字でも法人住民税の「均等割」という税金が発生します。
均等割は、会社の規模によって異なりますが、最低でも年間約7万円程度を支払う義務があるため、なかなかの負担です。
個人事業主の場合、赤字だと税金が発生しないため、法人化には法人化のデメリットがあると言えるでしょう。
会社を設立する場合は、固定費も考慮して資金計画を立てることも忘れてはなりません。
事業を辞める際にも解散手続きと費用が発生する
会社を設立して事業を辞める場合、個人事業主のように簡単に廃業届を提出するだけでは済みません。
会社を解散するには解散登記や清算手続きなど、法律に基づいた複雑な手続きが必要で、事業を辞めるだけでも一定のお金がかかるため、注意が必要です。
具体的には、官報公告費用や解散清算人選任登記の登録免許税などが挙げられます。
事業を終了する場合の手間や費用も会社設立の難点として考慮しておきましょう。
会社設立に必要な費用の内訳と相場
会社設立には様々な費用がかかるため、的確に把握しておきたいところです。
ここでは、会社設立に必要な費用の内訳と相場について解説します。
法務局に納める「登録免許税」
会社を設立する場合、法務局に納める登録免許税は必須となる費用です。
株式会社の場合、資本金の額の0.7%が登録免許税として課せられますが、最低でも15万円が必要です。
合同会社の場合は、資本金の額の0.7%または最低6万円を納めます。
例えば、資本金が1,000万円の場合、登録免許税は7万円となりますが、株式会社であれば15万円、合同会社であれば6万円を納めることになります。
なお、登録免許税は登記申請時に収入印紙で納付するか、オンライン申請の場合は電子納付すると良いでしょう。
公証役場で支払う「定款認証手数料」
株式会社を設立する際には、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があり、その際に定款認証手数料が発生します。
手数料は資本金の額によって異なり、資本金100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円が目安です。
なお、合同会社の場合は定款の認証が不要なため、手数料はかかりません。
株式会社だと電子定款を利用した場合でも認証手数料は発生するため、注意が必要となるでしょう。
定款の写し(謄本)の発行手数料
定款の認証後、定款の写し(謄本)を複数枚発行してもらう際にも手数料がかかります。
通常、1ページあたり250円程度の費用が発生するのが一般的です。
会社設立後の手続きで定款の写しが必要になる場面はいくつかあるため、数通発行しておくようにしましょう。
事業の元手となる「資本金」
資本金は、会社設立に必要な費用の中でも特に重要な位置を占めます。
事業の元手となる資金である資本金は、会社設立時に発起人の個人口座に払い込まれるものです。
法律上、資本金は1円からでも会社を設立できますが、対外的な信用度や事業運営の安定性を考慮すると、ある程度のまとまった金額を用意するのが良いでしょう。
資本金の額は、会社の事業内容や将来の資金需要に応じて慎重に決定しましょう。
登記完了後に必須となる主な手続き一覧
会社設立登記後も、事業を本格的に開始するためにはいくつか手続きが必要です。
ここでは、登記完了後に必須となる主な手続き一覧について詳しく解説します。
税務署への法人設立届出書の提出
会社設立登記が完了したら、速やかに会社の所在地を管轄する税務署へ「法人設立届出書」を提出する必要があります。
この届出書は、会社が法人として事業を開始したことを税務署に知らせるための重要な書類であり、原則として設立の日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
同時に、青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書なども提出することで、その後の税務上の恩恵を受けることが可能です。
年金事務所での健康保険・厚生年金保険の加入手続き
会社を設立し法人化すると、たとえ社長一人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられます。
社会保険の加入手続きは、会社設立後5日以内に管轄の年金事務所で行うことが必要です。
なお、社会保険料は会社と従業員(役員含む)で折半して負担するため、人件費として考慮しておく必要があるでしょう。
適切な保険手続きを行うことで、従業員の福利厚生を確保し、会社としての社会的な責任を果たすことに繋がるため、必ず行っておきましょう。
労働基準監督署・ハローワークへの労働保険関連の届出
従業員を雇用する場合、会社は労働保険(労災保険と雇用保険)への加入も義務です。
労災保険の手続きは労働基準監督署へ、雇用保険の手続きはハローワークへそれぞれ行います。
これらの保険は、従業員の安全と雇用安定を目的としたものであり、会社が保険料の一部を負担するのが一般的と言えるでしょう。
従業員を雇用した際には、速やかに上記の手続きを行い、法的な義務を果たしましょう。
金融機関での法人口座の開設
会社設立登記が完了したら、事業活動で使用する「法人口座」を金融機関で開設します。
法人口座は、会社の事業資金を管理するための重要な口座であり、個人口座と明確に区別して運用することが重要です。
なお、法人口座開設には、登記簿謄本や会社の印鑑証明書、定款の写しなど、いくつかの書類が必要です。
金融機関によっては審査に時間がかかる場合があるため、会社設立後、できるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。
自分で行う?専門家に依頼する?会社設立の方法を比較
会社設立の方法には、自分ですべての手続きを行う方法と専門家に代行を依頼する方法、そして会社設立支援サービスを活用する方法があります。
まずはどのような方法があるのか理解し、慎重に判断することが重要です。
自分で会社設立の手続きを進める場合
自分で会社設立の手続きを進める最大のメリットは、外注費用を抑えられる点です。
司法書士や行政書士に依頼する報酬が不要となるため、設立にかかる総費用を節約できます。
また、自身で手続きを行うことで、会社法や税金に関する知識が身につき、会社設立のプロセスを深く理解できるという経験的な恩恵もあるでしょう。
一方、書類作成や各機関への提出には多くの時間と手間がかかり、不慣れな場合は書類の不備などによるミスのリスクもあるため、事業準備に集中できない可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。
司法書士などの専門家に設立代行を依頼する場合
司法書士などの専門家に会社設立の代行を依頼する最大のメリットは、手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できる点です。
専門家は会社設立に関する知識と経験が豊富であるため、書類作成から法務局への登記申請まで、スムーズかつ正確に手続きを進めてくれます。
これにより、書類の不備による修正や再申請のリスクを避け、本業の準備に集中できます。
一方、それらの方法を利用すると専門家への報酬が発生するため、自分で手続きを行うよりも費用がかさむ点はデメリットです。
会社設立支援サービスを活用する場合
会社設立支援サービスを活用すれば、費用を抑えて効率的に会社設立の手続きができます。
上記のサービスは、オンライン上で必要な情報を入力するだけで、定款や登記申請書類などの作成を自動的に行ってくれるため、書類作成の手間を大幅に削減可能です。
特に、電子定款に対応しているサービスを利用すれば、通常4万円かかる印紙代を節約できるため、費用面での恩恵もあるでしょう。
まとめ
会社を設立する場合、具体的な流れとメリット・デメリットを把握しておきたいところ。
法人化は社会的信用向上や節税、資金調達の選択肢拡大といった恩恵を受けられる一方で、設立費用や維持費、複雑な手続きなどの負担も考慮しなければなりません。
ゆえに、慎重な判断が求められるでしょう。
なお、会社設立の方法としては、自分で全ての手順を進める、専門家に依頼する、会社設立支援サービスを活用するという3つの選択肢があります。
自身の状況やニーズに合わせて最適な方法を選び、計画的に準備を進めることで、スムーズな起業を実現可能です。
会社を設立するには事前の情報収集と準備が成功の鍵となるため、当記事で解説した内容を参考にし、積極的に挑戦してみましょう。