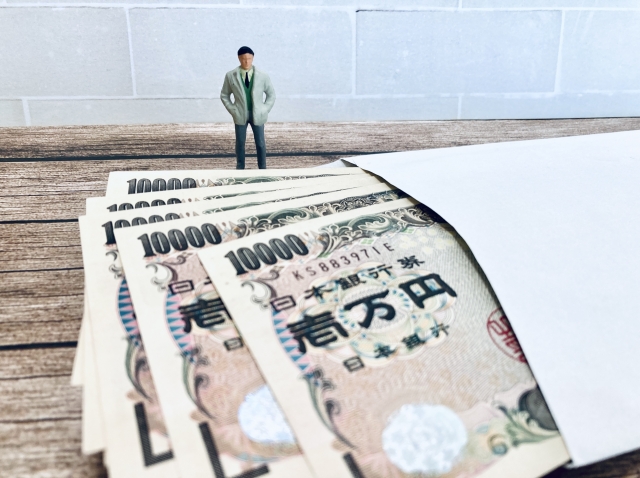弁当屋の開業を検討されている方も多いのではないでしょうか。
近年、ライフスタイルの変化に伴い、中食(なかしょく)の需要が高まっており、弁当市場は拡大傾向にあります。
弁当屋を開業したいという思いを実現するためには、様々な準備が必要です。
この記事では、弁当屋さん開業に必要な資金や資格、手続き、そして成功させるためのポイントについて網羅的に解説し、弁当屋さん開業を具体的に検討されている方が、開業するには何が必要かを理解し、次のステップに進めるように体系的な情報を提供します。

弁当屋の経営形態

弁当屋の経営形態は多岐にわたり、それぞれに異なる特徴と必要な開業資金があります。どのようなスタイルで弁当屋の経営をしていくかを明確にすることは、事業計画を立てる上で非常に重要です。ここでは、代表的な弁当屋の経営形態についてご紹介します。
店舗を構える
店舗を構えて弁当を販売する形態は、顧客が直接来店して購入するため、立地が重要です。
具体的には、人通りの多いオフィス街や住宅街などで開業すれば、安定した売上を見込める可能性がある他、顧客と直接顔を合わせることでニーズを把握しやすく、リピーター獲得にも繋がりやすいでしょう。
しかし、店舗の賃料や内装、設備に多額の初期費用がかかるだけでなく、固定費として毎月の家賃が発生する他、集客力を高めるためには、ある程度の広さの店舗が必要になることもあります。
宅配専門で営業する
宅配専門の弁当屋は、店舗を持たずに調理と配達を行うスタイルです。
調理設備と注文受付を行う場所があれば開業できるため、店舗を借りるよりも初期費用や固定費を抑えることができます。
しかし、集客は主にインターネットやデリバリープラットフォームを活用するため、広告宣伝活動が必要となる他、配達のための車両や人件費も考慮する必要があります。
オンラインでの販売が中心となるため、顧客との直接的なコミュニケーションが少なくなる点にも注意が必要です。
ゴーストレストラン形式
ゴーストレストランは、実店舗を持たずにデリバリーサービスに特化した経営形態です。
主にオンラインプラットフォームからの注文を受け、調理のみを行います。
宅配専門と同様に物件費用を抑えられ、キッチン設備のみの省スペースで運営できるのが特徴で、レンタルキッチンを利用すれば初期費用も大幅に削減できます。
集客はデリバリーアプリやSNSが中心となり、対面販売がないため、接客スキルよりもオンラインでの訴求力が重要です。
移動販売を行う
キッチンカーでの移動販売は、イベント会場やオフィス街、特定の曜日・時間に需要が見込まれる場所など、ニーズに合わせて移動しながら販売できる点が魅力です。
しかし、店舗の賃料こそかかりませんが、移動販売を行う車(キッチンカー)の購入やカスタマイズに費用が発生します。
新車の場合は300万円から、中古車であれば200万円からが目安。
イベントへの出店料やガソリン代なども運営費用として考慮する必要があります。
移動販売は様々な場所で多種多様な人に弁当を提供できる一方で、天候に左右されたり、営業場所の許可が必要になったりする場合もあるため、注意が必要です。
弁当屋開業に必要な資金
ここからは、弁当屋開業に必要な資金について見ていきましょう。
経営形態別の資金目安
弁当屋の開業に必要な資金は、選ぶ経営形態によって違うため、注意が必要です。
店舗を構える場合は、立地や規模によって変動しますが、一般的に600万円から1,200万円程度が必要とされています。
これには物件の契約にかかる敷金や礼金、内装工事費、厨房設備費などが含まれます。
宅配専門の場合は、店舗費用がかからないため、100万円程度から開業できる可能性がありますが、配達用の車両が必要な場合は車両購入費がかかるでしょう。
移動販売(キッチンカー)の場合も、車両の購入費用や設備費として200万円から300万円程度が目安となるでしょう。
なお、ゴーストレストラン形式であれば、既存のキッチンを活用したりレンタルキッチンを利用したりすることで、比較的低資金での開業が可能です。
資金の調達方法
弁当屋開業に必要な資金を全て自己資金でまかなうことが難しい場合や、リスクを分散したい場合には、様々な資金調達方法を検討することが可能です。
一般的な方法としては、金融機関からの融資が挙げられます。
特に、日本政策金融公庫は創業支援に積極的であり、比較的低金利で融資を受けられる可能性がある他、地方自治体による制度融資も利用できる場合があります。
その他、補助金や助成金制度、クラウドファンディングなどでも資金調達が可能です。
複数の方法を組み合わせることで、必要な資金を確保しやすくなるだけでなく、資金繰りの安定にも繋がる可能性があるため、様々な方法を試してみましょう。
弁当屋開業に必要な許可と資格
ここでは、弁当屋開業に必要な許可と資格について見ていきましょう。
必ず必要な資格
弁当屋の開業にあたり、食品を取り扱う施設には必ず「食品衛生責任者」を1名以上置く必要があります。
食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき、施設の衛生管理全般を行う人を言います。
なお、食品衛生責任者の資格を取得するには、都道府県知事が指定する講習会を受講し、修了試験に合格することが必要です。
調理師や栄養士などの特定の資格を持っている場合は、講習会の受講が免除されることもありますが、食品衛生責任者の資格は安全な食品を提供するために不可欠なものであり、開業準備の早い段階で取得しておくのが理想です。
その他にあると役立つ資格
食品衛生責任者の資格は必須ですが、その他にも取得しておくと弁当屋の経営に役立つ資格があります。
例えば「調理師免許」は必須ではないものの。料理の専門知識や技術を証明できるため、顧客からの信頼獲得に繋がる他、食品衛生責任者講習が免除されます。
他にも「防火管理者」など、一定規模以上の店舗で多数の人が利用する場合に設置が義務付けられる資格もあるため、必要に応じて取得しておきたいです。
上記の資格は、自身のスキルアップやお店の信頼性向上に繋がり、より質の高い弁当を提供するための助けとなるはずです。
開業に必要な手続き
弁当屋として営業を開始するためには、保健所からの「飲食店営業許可」が必要です。
営業の許可については、店舗の構造や設備、衛生管理体制などが、食品衛生法に基づく基準を満たしているかを確認するためのものです。
なお、営業許可の申請は、施設の工事着工前に保健所に事前相談を行い、施設の完成予定約10日前に必要書類を提出しておくことをおすすめします。
その後、施設完成後に保健所による立ち入り検査があり、基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。
併せて、税務署への開業届出や、従業員を雇用する場合は労働基準監督署への届出なども行っておきましょう。
弁当屋を開業する手順
次に、弁当屋を開業する手順について見ていきましょう。
コンセプトの決定
弁当屋を開業する場合、どのようなお店にしたいのか、コンセプトを明確にしましょう。
誰に(ターゲット顧客)、どのような弁当を(商品の特徴)、どのような価格帯で提供するのかなど、お店の根幹となる部分を具体的に決めます。
例えば、「健康志向の女性向けに野菜たっぷり弁当」「オフィスワーカー向けにボリューム満点の日替わり弁当」「高齢者向けに栄養バランスの取れた宅配弁当」など、ターゲット顧客のニーズに合わせたコンセプトを設定することが重要です。
コンセプトさえ明確に定めれば、事業計画やメニュー開発、資金計画などもスムーズに進められるでしょう。
事業計画書の作成
コンセプトが固まったら、次に事業計画書を作成します。
事業計画書は、開業の目的やコンセプト、具体的な事業内容、資金計画、収支予測などをまとめたものです。
計画書を作成することで、事業の実現可能性を具体的に検討できるだけでなく、金融機関からの融資を受ける際にも必要となります。
具体的な内容には売上目標や費用項目を詳細に盛り込み、現実的な収支シミュレーションを行うことが重要です。
なお、事業計画書は、開業後の羅針盤ともなるため、時間をかけてじっくりと作成しましょう。
メニューの開発
お店の顔となるメニュー開発は、弁当屋開業において非常に重要なステップです。
コンセプトに基づき、ターゲット顧客に喜ばれる魅力的なメニューを考案します。
美味しさはもちろんのこと、彩りや栄養バランス、価格設定なども考慮が必要です。
競合店のメニューを参考にしたり、試作を重ねたりしながら、オリジナリティのあるメニューを開発しましょう。
また、定番メニューに加えて、季節限定メニューや日替わりメニューなどを取り入れることで、顧客の飽きを防ぎ、リピート率向上に繋げることができます。
物件や設備の手配
事業計画ができたら、選択した経営形態に合わせて物件や必要な設備の手配を行います。
店舗型の場合は立地条件や広さ、賃料などを考慮して物件を選び、宅配専門やゴーストレストランの場合は調理を行うキッチンスペースを確保しましょう。
移動販売の場合は、キッチンカーを用意します。
厨房設備は、提供するメニューに必要な調理器具や冷蔵・冷凍庫、陳列ケースなどをリストアップし、予算に合わせて手配すると良いです。
なお、物件や設備に関しては新品だけでなく中古品やリースなども検討することで、初期費用を抑えることが可能です。
仕入れ先の選定
弁当の品質を左右する食材の仕入れは、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
安定的に良質な食材を適正な価格で供給してくれる仕入れ先を選定します。
複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく、品質、納品体制、支払い条件なども比較検討しましょう。
具体的な方法としては、地元の農家から直接仕入れる、卸売市場を利用する、食品専門の商社と契約するなど、様々な選択肢があります。
新鮮で安全な食材を確保することは、顧客満足度を向上させるのに必須です。
各種申請と届出
弁当屋を開業するためには、食品衛生責任者の資格取得や飲食店営業許可の申請など、法律で定められた様々な手続きが必要です。
これらは管轄の保健所で行います。
また、個人事業主として開業する場合は税務署への開業届出、法人として開業する場合は法務局での登記などが必要です。
従業員を雇用する場合は、労働基準監督署やハローワークへの届出も必要となります。
それらの申請や届出は、開業準備と並行して計画的に進めましょう。
必要な許可や資格を漏れなく取得することで、法的な要件を満たしたうえで安心して営業を開始するのが理想でしょう。
弁当屋経営を成功させるポイント
次に、弁当屋経営を成功させるポイントについて見ていきましょう。
独自の強みを打ち出す
数ある弁当屋の中で顧客に選ばれるためには、独自の強みを持つことが重要です。
他店との差別化を図るためには、こだわりの食材を使用する、特定のニーズに特化したメニューを開発する(例:アレルギー対応、アスリート向け、ダイエット向けなど)、手作りにこだわるといった要素をアピールするのが良いでしょう。
また、看板メニューを作ることも効果が期待できます。
ユニークで記憶に残るメニューや、地元の食材を活かしたメニューは、口コミやSNSでの拡散に繋がりやすく、新たな顧客獲得のきっかけとなるでしょう。
立地選びの重要性
特に店舗型の弁当屋にとって、立地は成功を左右する非常に重要な要素です。
ターゲット顧客が多く通行する場所に店舗を構えることで、集客に繋がりやすくなります。
例えば、オフィス街であればランチタイムの需要が見込めますし、住宅街であれば夕食や休日の需要が期待できるでしょう。
ゆえに、競合店の有無や周辺環境なども考慮し、慎重に立地を選びたいです。
移動販売の場合もイベント会場やオフィス街など、人が集まる場所を選ぶことが売上アップに繋がります。
効率的な運営
弁当屋の利益を最大化するためには、効率的な運営体制を構築することが重要です。
食材の無駄を減らすための適切な在庫管理や、調理時間の短縮、人員配置の最適化などが挙げられる他、事前予約システムやキャッシュレス決済を導入することで、注文から受け渡しまでの流れをスムーズにし、顧客の待ち時間を減らすことができます。
オペレーションを効率化することで、コスト削減に繋がり、顧客満足度も向上させることが可能となるでしょう。
適切な価格設定
適切な価格設定は、弁当屋の経営において非常に重要です。
原価や人件費、家賃などのコストを考慮しつつ、ターゲット顧客が「この価格なら買いたい」と思えるような価格を設定する必要があります。
競合店の価格を参考にすることも有効ですが、単に安くするだけでなく、提供する弁当の品質やボリュームに見合った価格にすることが重要でしょう。
また、食材価格の変動なども考慮し、定期的に価格設定を見直すことも必要になります。
適切な価格設定により、利益を確保しつつ、顧客に納得感のある価値を提供することを目指せば、いずれ成功に繋がるはずです。
自宅での弁当屋開業
最後に、自宅での弁当屋開業について見ていきましょう。
自宅開業の利点
自宅での弁当屋開業の最大の利点は、初期投資とランニングコストを抑えられることです。
新たな物件を借りる必要がないため、敷金や礼金、仲介手数料といった物件取得にかかる費用が発生しません。
また、毎月の家賃もかからないため、固定費を抑えることができる他、通勤時間がなくなることで時間を有効活用でき、家事や育児との両立もしやすくなる可能性があります。
小規模から始められるため、リスクを抑えながら弁当屋経営に挑戦したい方にとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。
自宅開業の注意点
自宅で弁当屋を開業する際には、いくつかの注意点があります。
- 自宅のキッチンを営業用に使用するためには、保健所が定める施設基準を満たすように改修する必要がある
⇒住居スペースと厨房スペースを壁などで区切る、厨房専用の手洗い場を設置するなど、大規模なリフォームが必要になるケースがある - 生活空間と仕事場が隣接しているため、オンオフの切り替えが難しくなる可能性や家族の理解と協力が必要となる
- 集客面では店舗がないため認知されにくく、オンラインでの情報発信や地域への周知活動に力を入れる必要がある。
- 近隣住民への配慮が必要となる。
自宅でも弁当屋は開業できますが、上記の点には注意が必要です。
まとめ
弁当屋の開業は、高まる中食需要を背景に魅力的なビジネスチャンスと言えますが、成功させるには事前の準備と計画が不可欠です。
まずは、どのような弁当屋を開業したいのか、ターゲット顧客や提供する弁当の特徴といったコンセプトを明確にすることが出発点となります。
次に、店舗型、宅配専門、移動販売、ゴーストレストランといった様々な経営形態の中から、自身の資金や状況、目標に合ったスタイルを選択します。
それぞれの形態で必要となる開業資金の目安を把握し、自己資金に加え、融資や補助金なども活用した資金計画を立てることが重要です。
また、弁当屋の開業には食品衛生責任者の資格取得や飲食店営業許可の申請が法律で義務付けられています。
これらの許可や資格は、安全な食品を提供するために不可欠であり、計画的に取得を進めることが必要です。
その他にも、事業を成功させるためには、独自の強みを打ち出した魅力的なメニュー開発、ターゲットに合わせた立地選び、効率的な運営体制の構築、そして適切な価格設定が重要なポイントとなるでしょう。
なお、初期費用を抑えられる方法として自宅での開業も可能ですが、保健所の基準を満たすための改修が必要になるなど、独自の注意点も存在します。
ゆえに、ご自身の状況や目標をしっかりと見極め、最適な開業方法を選択することが必要です。
まずは、当記事で解説した情報を参考に、ぜひあなたの理想の弁当屋開業に向けた第一歩を踏み出してみましょう。